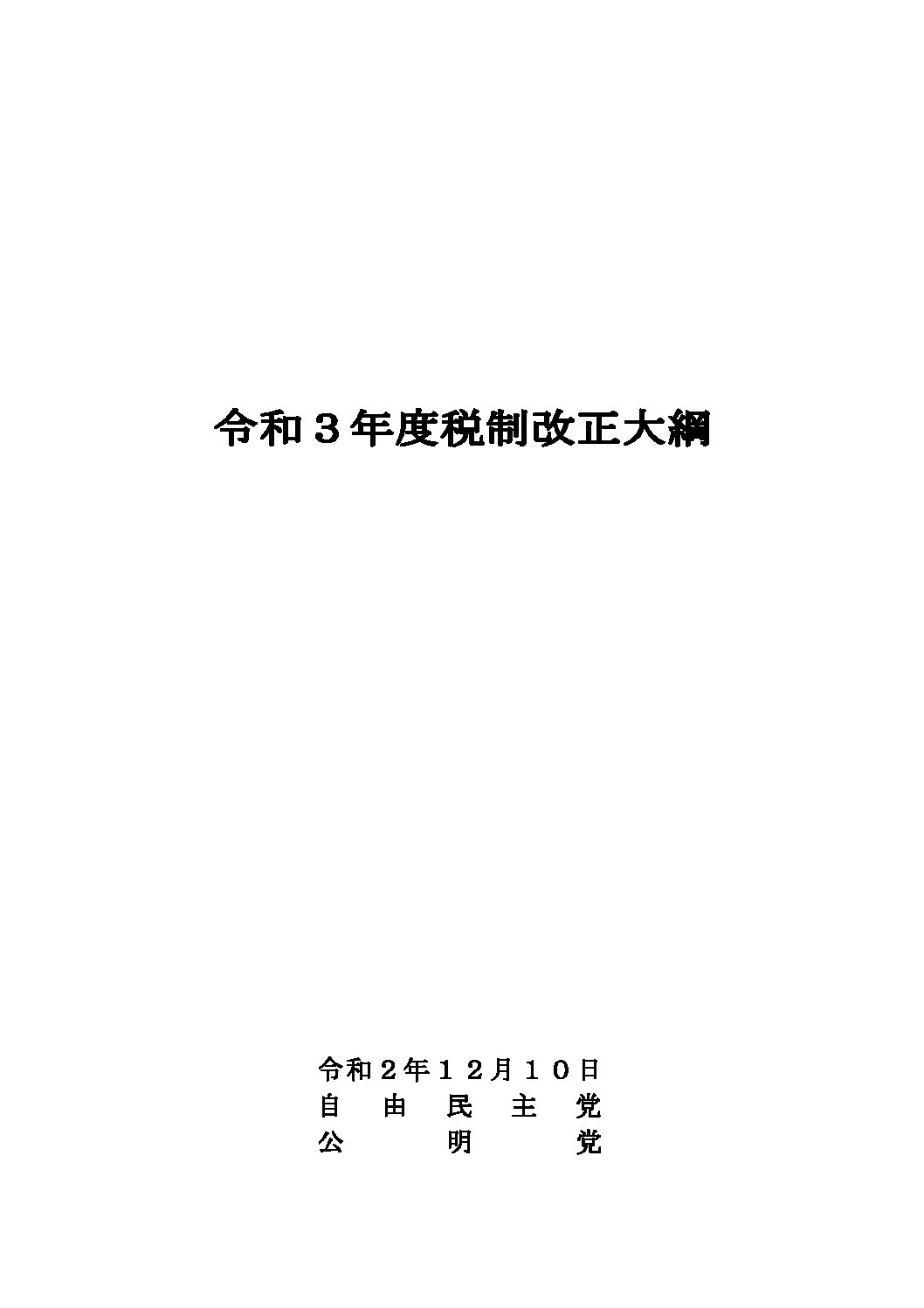大江戸は「Oedo」→「Ōedo」「Ooedo」とローマ字表記がヘボン式に!
日本経済新聞によると、ローマ字表記の目安が約70年ぶりに見直されることになったようです。
国は内閣告示で母音と子音を規則的に並べる「訓令式」を用いるとしてきましたが、英語の発音に近い「ヘボン式」を基本とする方針です。
ヘボン式が社会で定着している実態に合わせるとともに、外国人らにも読みやすくする狙いのようです。
文化審議会の小委員会が先日、ヘボン式に移行する案を大筋で了承しました。
内閣告示は審議会の答申を受け、改定される見通しです。
訓令式では「し」は「si」、「しゃ」は「sya」、「つ」は「tu」と表記していますが、ヘボン式ではそれぞれ「shi」「sha」「tsu」となります。
「ふ」は「hu」から「fu」に変わります。
ヘボン式は幕末に来日したアメリカ人宣教師が考案したとされています。
1954年の内閣告示は「一般に国語を書き表す場合」は訓令式を用い、ヘボン式は限定的に使うとしました。
ただし、実際には、ローマ字は外国人向けに固有名詞を表記する際に使われることが多く、ヘボン式が浸透しました。
文化審議会の小委員会はこうした実態を踏まえるとともに、グローバル化への対応も考慮しました。
インバウンド(訪日外国人)や日本に住む外国人は増えており、日本語を母語としない人が読みやすいようにします。
文化庁が2024年に日本で生活する外国人を対象に実施した調査では、母語や国籍にかかわらず、95%が訓令式よりヘボン式が読みやすいと答えています。
改定案は、表記の割れが目立つ長音の示し方も明記しました。
訓令式とヘボン式ではそれぞれ母音字に長音符号の「^」「¯」をつけるとされていますが、英語の影響で符号を用いない表記が広がりました。
この場合は「大野」も「小野」も「Ono」と書き、音の長短を判別しにくいのが難点でした。
このため、符号としてより社会に定着している「¯」を使用するか、符号をつけず母音字を並べるとした。例えば「大江戸」は「Ōedo」「Ooedo」と表記します。
はねる音である撥音(はつおん)の「ん」は「n」を統一的に用い、つまる音の促音は子音字を重ねて「zasshi(雑誌)」などとします。
文化庁によると、内閣告示は国として示す目安という位置づけで、強制力はないそうです。
「judo(柔道)」のように定着している表記の変更を直ちに求めるものではなく、当事者の意思が尊重されるそうです。
学校では訓令式を教えてきました。
改定されればヘボン式に変更します。
2030年度をめどに小学校で全面実施予定の次期学習指導要領でヘボン式を採用し、教科書の表記が変わる見通しです。
数年前に、こどもの宿題を見ているときに、ローマ字の問題があって、『si』とか『tu』とか書いていたので『間違えているやん。「shi」とか「tsu」でしょ。』と言ったら、『これであっているわ。教科書に書いているやん。』と怒られて、教科書を見たり、ネットで調べると、今は、僕が習った『ヘボン式』ではなく『訓令式』が使われていることを知り、カルチャーショックを受けたことがありましたが、どうも『訓令式』はなじめないので、今回、『訓令式』から『ヘボン式』に変更になると知り、嬉しかったです(笑)。
大江戸は「Oedo」→「Ōedo」「Ooedo」とローマ字表記がヘボン式になることについて、あなたはどう思われましたか?
ネットに広がる「JA不要論」をコメ農家が農家直売がスーパーよりも高くなる理由で一蹴!
2025年06月24日(火)
ENCOUNTによると、コメの価格高騰が止まりません。
農林水産省の発表によると、2025年5月18日までの1週間に全国のスーパーで販売されたコメの平均価格は5キロあたり4,285円で、前の週から17円値上がりし、2週連続で過去最高を更新しました。
昨年同時期の2倍以上の高値が続いています。
高騰が国民生活を直撃する中、ネット上では「中抜きするJAこそ諸悪の根源」という臆測をもとにした、JA悪玉論や解体論が噴出しています。
JAとはどういった組織で、仮になくなるとどんな事態が起こるのでしょうか?
SNS上でJAの必要性を力説したある農家に話を聞いています。
JA(全国農業協同組合)とは、農業従事者によって全国に組織された協同組合(農協)のことです。
組合員の農家に対する技術指導や必要資材の共同購入、農産物の共同販売や直売所運営の他、資金の融資や共済に至るまで幅広い支援を行っています。
農作物の生産をなりわいとし、流通や販売まで手が回らない農家にとってなくてはならない存在ですが、流通の過程で農作物に中間手数料が上乗せされることから、昨今の価格高騰を背景に一部でその在り方が疑問視されているのです。
そんな“JA不要論”に対し、「JA要らない。農家から直接買えば直接の利益になるし、安く買える。は妄想です」とSNS上に反論を投稿したのが、栃木県在住のあるコメ農家です。
投稿者は「ちょっとだけ想像してみてください。私は3ha(ヘクタール)の田んぼで米を作っています」と一般論を交えつつコメ作りの規模感を語っています。
1ヘクタールは100メートル×100メートルの広さの土地で、スタンドまでを含めた甲子園球場の総面積3.85ヘクタールと比較すると、おおよその大きさがイメージできるでしょう。
田んぼ3ヘクタールの稲刈りには、コンバイン1台で約10日ほどの日数がかかるとされています。
投稿ではまず、3ヘクタールある自身の田んぼで年間に収穫できるコメの量が1万4,400キロ、市場で販売される30キロのコメ袋に換算すると480袋にもなると説明しています。
その上で「私のような小さな農家でもこの量になります。では私の10倍規模の農家なら簡単に計算しても凡そ10倍。4,800袋のお米を在庫しなければなりません」「『玄米じゃなくて精米しろ』となれば精米設備も必要になりますし、米は生鮮食品なので保管するにしても『冷蔵設備完備』でないと鮮度は維持できません」と、JAを介さず直販するには多額の設備投資がかかる事情を解説しています。
さらに、仮に設備を整えたとしても、精米する時間、袋詰め、配送手配などさまざまな販売コストや人件費がかかるとし、「それ等も販売価格に上乗せしますので、結果スーパーで買うよりも高くなる事が解ると思います」と結論付けています。
JAがなくなることで、よりコメの価格が高くなる可能性をつづっているのです。
投稿は1万件以上のリポスト、3.7万件の“いいね”を集めるなど話題になりました。
「現場の声をありがとうございます JAはなくてはならない組織なんですね!」「これだけわかりやすく説明しても米農家とJA悪論で確定バイアスのかかっている人は全く理解できないだろうな」「いわゆるJA解体を掲げてる人たちは部外者が多いですよね」「JA解体したらどうせよくわからない企業や外資系とかが入り乱れて、今より荒れた状況になりそうです」といった声が寄せられています。
投稿者は、今回の投稿の意図について、「農家から直接買えば安くなるという風潮について、個人的に『果たしてそうなのか?』と感じて投稿しました。実際には収穫から販売までに多数の過程が存在し、それらの工程を経て販売に至ります。出荷し小売店の店頭に並ぶにはさまざまな業者さんがそれぞれの役割を分担している訳ですが、直販となればその負担を生産者自らが行わなければならない。安直に『生産者から直接買えば安く買える』というのは少し違うのかなと思ったので、ざっくりではありますが投稿させていただきました」と説明しています。
一連の反響については、「本当に驚きました。当初は特に何も考えず、『こんな風になってるんだよ~』と知ってもらえたらありがたいなぁと思っていただけでしたが、ふたを開けたら多くの方からコメントを多数いただきました。もちろん賛否両論ありますし、それらを否定しようとも思いませんが、生産者の裏側を少しは知ってもらえたのかなとは思っています」と話しています。
農家の方の貴重な意見ですね。
農業、特にお米はコストがかかるのは間違いありませんので、現在、米が高いのは悪みたいな感じに世の中がなっていますが、米の価格が上がってようやくお米を作っている方も利益が出るようになった(儲からないので辞める方も多い。)という事実もきちんとマスコミ等は伝えていかないといけないと思います。
個人的には、精米や保管の設備を持っている農業法人などが設備等を貸したり、持っていない農家の方から買い取って販売するということもできるでしょうから、JAは必ずしもいらないのではないかと考えています。
また、JAはきちんと値付けができる組織になれば、存在価値が出てくる(高まる)のではないかと思っています。
ネットに広がる「JA不要論」をコメ農家が農家直売がスーパーよりも高くなる理由で一蹴したことについて、あなたはどう思われましたか?
羽田空港の駐車場予約枠を高額転売か?
日本テレビによると、予約が取りにくいという羽田空港の駐車場の背景に、高額転売の可能性が出ています。
事前予約枠をめぐり、転売禁止に乗り出す事態となっています。
“東京の空の玄関口”羽田空港は、出張や旅行を控え、ただでさえ慌ただしい朝を迎えます。
月3回ほど駐車場を利用している方
「(空港の駐車場に)来たらいっぱい。冷や汗かきながら近所の駐車場探して。きょうも結構やばかったかもしれない」
月2回ほど駐車場を利用している方
「(朝)7時とかになってくると、とめられないので、できるだけ早く来ている」
駐車場の混雑を避けるため早起きをしたという人もいるようです。
3連休など繁忙期は“数時間待ち”になるなど慢性的に混雑している羽田空港の駐車場ですが、今、その「事前予約枠」をめぐり、中野国土交通大臣が「買い占めや転売が行われているとの報告を、私も運営する各事業者から受けている。1人でも多くの方に利用をしていただくということが重要であると」国が“問題視”する事態になっているのです。
そもそも羽田空港の駐車場では、およそ800台分の「事前予約」が可能となっています。
専用サイトで利用したい日の30日前から名前や車のナンバーなどを登録し、予約料金「1,000円」を支払えば利用できます。
しかしながら、羽田空港、予約代行で検索するとずらっと業者が出てきます。
ネット上には“予約代行”をうたう業者がズラリと並んでいます。
駐車場代でしょうか、中には「3万円台」で販売されているものもありました。
駐車場の「運営事業者」が調査を行ったところ、「予約代行業者」が受け付け開始後、すぐに予約枠を買い占め、高額で転売している可能性が浮上しました。
登録した車のナンバーをあとから変更するケースが見つかったといいます。
実際、羽田空港のサイトを見てみると、午前10時からの予約開始分があっという間に埋まってしまいました。
30日後の予約枠が受け付け開始とほぼ同時に埋まってしまいました。
この状況に利用者からは“不満”の声が噴出しています。
月2回ほど駐車場を利用している方
「利益がほしい人たちによって奪われるのは、憤慨。憤りを感じる」
月3回ほど駐車場を利用している方
「(Q.3万円とかで売っている)赤ちゃんがいるとか、荷物がある人は電車で来たくないから、少々お金払ってもと思う」
年に3~4回ほど駐車場を利用している方
「3万円ですよね、考えられない。僕はバカバカしくてもったいないと感じるので朝イチに来る」
駐車場の“代行業者”を利用したという方
「(公式サイトの)1か月前の(受け付け開始日)から狙いましたが ダメでした。妻が頑張ってやったけど瞬く間に赤(満車)になっちゃって、じゃあほかで頼むしかないよねと。何千円か割高かな。でも安心を買うようなもの」
every.は駐車場の「予約代行」を行っている業者を取材しました。
駐車場の“予約代行”行う業者
「客からの依頼を受けて予約を確保しているので転売ではない。予約枠を確保したら手数料をいただく」
依頼の数は月20件ほどで、「予約の枠」が少ないのが問題だと話しています。
駐車場の運営事業者は、来月から利用規約に転売禁止を盛り込み、予約後の車のナンバーの変更も禁止にするようです。
誰もが安心して利用できるよう対策を強化するとしています。
やはりお困りごとを解決することがお仕事につながりますから、ニーズに対して、こういう業者が出てくるのでしょうね。
登録した車のナンバーをあとから変更できる仕組み自体にもんだいがあると思いますので、身元確認から始まり、対策をしていくしかないでしょうね。対策したとしても、おそらく、いたちごっこになるでしょうから。
羽田空港の駐車場予約枠が高額転売されていることについて、あなたはどう思われましたか?
「アメ車」は日本で一人負けのシェア0.4%ゆえ非関税障壁より消費者の壁!
日本経済新聞によると、日本市場でアメリカ車の販売が振るいません。
2024年の年間販売台数は1996年のピークから8割減り、アメリカ車が新車販売に占める割合はわずか0.4%にとどまります。
アメリカのトランプ大統領は安全基準の違いなどを「非関税障壁」としてやり玉に挙げていますが、当事者のアメリカメーカーは影響を否定しています。
「アメ車」はなぜ日本で売れなくなったのでしょうか?
日本自動車輸入組合(JAIA)のデータからアメリカブランド車の販売台数を集計しています。
アメリカで生産しているかは考慮していません。
アメリカ電気自動車(EV)大手のテスラは地域別の販売台数を公表していないため推計しました。
2024年のアメリカ車の販売台数は約1万6,700台でした。
国内新車販売全体は442万1,494台で、アメリカ車の割合は0.4%しかありません。
輸入車販売(22万7,202台)でみても割合は1割に満たないです。
実はアメ車は日本で一人負けなのが実態なのです。
輸入車で首位がドイツのメルセデス・ベンツの5万3,195台、2位が同じくドイツのBMWの3万5,240台です。
アメリカ車はジープが9,633台と7位でようやく顔を出します。
アメリカのゼネラル・モーターズ(GM)のブランド「シボレー」は587台、「キャデラック」は449台しか売れていないのです。
なぜ日本でアメ車離れが起きているのでしょうか?
1990年代にアメ車ブームが巻き起こり、1996年に販売台数は約7万2,900台とピークに達しました。
けん引したのはフォード・モーターとGM、クライスラーの「ビッグ3」です。
シボレーのミニバン「アストロ」などを中心に人気を集めました。
そこから販売は減少の一途をたどっています。
2009年に約8,700台まで落ち込み、2016年にフォードは日本から撤退しました。
車体の大きさや燃費性能の悪さなどが消費者から敬遠されたのです。
伊藤忠総研の深尾三四郎エグゼクティブ・フェローは当時のビッグ3について「顧客へのサービスが不十分だった」と指摘しています。
一方、アメリカ勢で気を吐くジープは主力の「ラングラー」などをアメリカから輸入しているが、日本市場に合わせて右ハンドル車を導入しています。
ジープを傘下に持つヨーロッパのステランティス日本法人の成田仁社長は非関税障壁について「日本に参入しにくいと感じたことはない」とし、「顧客が求める形で提供することが大前提」と強調しています。
アメ車も変わろうとしています。
キャデラックは2025年3月に日本で発売したEVで約12年ぶりに右ハンドルを導入しました。
日本法人の若松格社長は「新しい需要を開拓する」といっています。
世界で不買運動が起きているテスラは日本で好調です。
日本車メーカーのEVが低迷しているためで、深尾氏は「日本市場に合ったEVを投入できれば、アメリカ車でも売れる余地はある」と話しています。
トランプ大統領は日本の充電規格にも不満を示していますが、中国のEV大手の比亜迪(BYD)は規格に対応したうえで、軽自動車に参入して日本の牙城を切り崩しにかかっています。
日本に対する自動車の非関税障壁の見直しは、オバマ元大統領の時から要求が続いています。
今回、日本政府は関税撤廃に向けた交渉カードの一つとして、輸入自動車への特例措置を想定しています。
しかしながら、非関税障壁が一部見直されたとしても、日本市場に合った車がなければ売れません。
今も左ハンドルは多く、燃費性能が悪い印象が消費者から持たれています。
大事なことはアメ車に対する消費者の心の壁を崩せるかです。
僕も昔、アストロとかハマー3とかを買うことを考えたことがありますが、大きさ、左ハンドル、燃費の悪さなどを考え、買いませんでした。
今だと、ガソリン価格も当時の2倍くらいになっていますから、なかなか買う人は少ないでしょうね。
トランプ大統領は、関税が原因のようなことを言っていますが、関税では何も解決しないと思いますね。
プロダクトアウトかマーケットインかの話しのように感じます。
「アメ車」は日本で一人負けのシェア0.4%ゆえ非関税障壁より消費者の壁!があることについて、あなたはどう思われましたか?
「何てことをしてくれたんだ」とシャインマスカット農家はショックを隠し切れず!
信越放送によると、長野県須坂市が、地元産ではないシャインマスカットをふるさと納税の返礼品にしていた問題について、生産農家はショックを隠し切れないようです。
吉池果樹園 吉池拓也代表:「そういうことされたらもう信用がないじゃないですか」
3年ほど前から須坂市の返礼品としてシャインマスカットを出荷する吉池拓也さん。
吉池果樹園 吉池拓也代表:「信頼していた部分が大きかったのでとてもショックです。何てことしてくれたんだと」
吉池さんは偽装の情報を知ってすぐに、日本グルメ市場との取引の中止を決めたといいます。
吉池果樹園 吉池拓也代表:「まずは信頼できる業者を市が判断して頂いた方が、ブランドもあるのでそこら辺を農家と話し合いながら進めていければ」
市民の反応は…。
須坂市民:「ブランドを傷付けるような行為なので迷惑で今後どうなっていくか不安。把握した段階で是正すれば、仕方ないことはないが対応できたのかなと。隠したのは完全にアウトだと思います」
須坂市民:「皆さん産地偽装を知らないで買い求めている。それを知ったらショック」
日本グルメ市場の長野営業所はSBCの取材に対し、「社長が長野に訪れる予定はしばらくない」と説明しています。
こういった事件が出てくるとは思っていましたが、やはり出てきましたね。
当然、農作物などは収穫量が天候や病気等に左右されるわけですし、人気のあるものには申し込みが殺到するわけですから、きちんと数量管理をして、申込件数を制限しないと、同じような事件は今後も出てくるのではないかと思います。
今回、日本グルメ市場は、長野県ではなく和歌山県の会社ですから、業者も市内とか県内とかに制限する方が、ふるさとへの貢献にもつながるのではないかと思いました。
「何てことをしてくれたんだ」とシャインマスカット農家はショックを隠し切れないことについて、あなたはどう思われましたか?
ドバイに続く「億万長者の街」として世界の富裕層がバンコクへ!
日本経済新聞によると、タイの首都バンコクに世界の富裕層が集い始めているようです。
東南アジアの比較的温暖な気候や豊かな食文化が生活拠点として評価され、中国や欧米の資産家の移住先として人気が高まっています。
ドイツのポルシェやフランスのバカラなど欧州ブランドが手掛ける高級マンションの建設も相次ぎ、ドバイやシンガポールに続く「億万長者の街」として注目されています。
バンコク中心部にそびえる高さ314メートルの「キングパワー・マハナコン」の66階の住居フロアに個人投資家の与沢翼さん(42)とその家族が居を構えています。
2024年に、3年ほど住んだドバイを離れてバンコクに移り住んだのです。
「物価や食事、教育面などを総合的に考えればタイが一番」と与沢さんは語っています。
ドバイやマレーシア、日本にマンションなど複数の物件を保有していますが、将来はタイへの投資に集中する考えのようです。
2025年3月にはおよそ2億バーツ(約8億8,000万円)の新規物件を購入しました。
「高級住宅市場が急速に立ち上がっている。富裕層がバンコクに移る動きも出ている」とのことです。
富裕層向けの投資コンサルティング会社、イギリスのヘンリー・アンド・パートナーズによると、100万ドル(約1億5,000万円)以上の流動資産を持つ富裕層のタイへの流入数は2024年におよそ300人と、2023年比で倍増しました。
アラブ首長国連邦(UAE、6,700人)やアメリカ(3,800人)に数は及ばないものの、伸び率は世界最大です。
ヘンリー・アンド・パートナーズのアンドリュー・アモイル氏は「富裕層がバンコクに向かう流れは2025年にさらに加速する」とみています。
充実した教育制度やナイトライフなど生活の利便性も人気の理由だそうです。
周辺に150を超えるインターナショナルスクールがあり、年率2桁のペースで増えています。
イギリスのユーロモニターによると、2024年にバンコクを訪れた外国人観光客は3,240万人と世界の主要都市で最多でした。
旅行でこの街を気に入り、移住を考える富裕層も多いようです。
バンコク市内では、富裕層の流入を見越した高級マンションの開発ラッシュが起きています。
バンコクの目抜き通り「スクンビット」の一角で、ドイツの高級車ブランド「ポルシェ」の名前を冠した超高級マンションの建設が進んでいます。
2028年にも完成する22戸は平均価格が1,500万ドル(約22億円)です。
最高級は4,000万ドルと、タイの分譲マンションで過去最高額となる見通しです。
開発会社ポルシェ・ライフスタイル・グループのステファン・ビュッシャー最高経営責任者(CEO)は「新たな生活体験を求めて、金に糸目をつけない富裕層が購入意欲を示している」と話しています。
ポルシェはドイツのシュツットガルト、アメリカのマイアミに次ぐアジア初のマンション開発地にバンコクを選んだのです。
ビュッシャー氏はその理由として「街の活気」を挙げています。
東京や上海も候補として検討したようですが、高額物件の需要に加え、都心の一等地を確保しやすく建設費が比較的安いことも決め手になったそうです。
不動産調査会社C9ホテルワークスによると、ホテル名などを冠した高級マンションの販売総額は2024年末時点でタイが62億ドルと、アジア圏で最大、日本のおよそ7倍に及びます。
フランスのバカラは現地の不動産開発大手と提携し、自社がデザインを手掛ける高級住宅の開発を進めています。
戸数は4戸限定で価格は48億円です。
高級ホテルブランド「アマン」も2023年に竣工した東京都港区の「麻布台ヒルズ」に続き、バンコクの中心部に高級マンションを開発中です。
タイの不動産市場に詳しいCBREタイランドのアティタヤ氏は「ドバイの物件は投資対象として人気だが、バンコクは住居用の需要が高い」と解説しています。
バンコク中心部の一等地を保有し、タイ最大の「地主」とされるタイ王室も富裕層の誘致に一役買っています。
王室財産管理局は不動産開発会社を傘下に置き、ドイツの高級ホテル系などのマンション開発を手掛けています。
民間最大の投資プロジェクト「ワンバンコク」や老舗ホテル「デュシタニ・バンコク」の再開発にも王室が保有する土地をマンション用地として拠出しました。
タイ政府住宅銀行がまとめた2024年1〜9月のタイ国内における外国人の物件購入件数は1万1,036件で、そのうち4割が中国人でした。
ヘンリー・アンド・パートナーズは、中国の富裕層の国外流出数が2024年に1万5,200人と過去最多になったと推計しています。
経済成長の鈍化や政府当局による監視強化を避けて国外移住する富裕層が増えているとみられ、バンコクが受け皿の一つになっているのです。
アメリカのトランプ大統領は2025年2月、外国人が500万ドル(約7億5,000万円)を支払えば米国で永住権を得られる「トランプ・ゴールドカード制度」の創設を表明しました。
「100万枚以上売れるだろう。世界の富裕層がアメリカに集まり、大成功を収める」と唱えました。
世界各国で富裕層の誘致競争が過熱しているのです。
資金力のある個人を自国に呼び込み、経済の活性化や投資の促進につなげようとしています。
シンガポールは2004年に「グローバル投資プログラム」を導入し、外国人の一定規模の投資家や起業家に永住権の取得を可能にしました。
タイは2022年に純資産額1,00万ドル、年収8万ドル以上の富裕層向けに長期滞在ビザを設けました。
インドネシアやマレーシアでも同様の仕組みが始まっています。
富裕層の流入数でトップのドバイは永住権制度はありませんが、預金額200万ディルハム(約8,100万円)以上などの条件で最長10年のビザを提供しています。
一方、国内の不動産価格の高騰や安全保障上の理由から、富裕層への永住権や長期ビザの発行を取りやめる動きもあるようです。
イギリスやオランダが近年廃止したほか、スペインも2025年4月に長期ビザ制度を終了します。
国際社会では、税制優遇などで富裕層を呼び込む手法が課税逃れやマネーロンダリング(資金洗浄)につながっているという批判もあります。
■富裕層■
一般的に日本では1億円以上、国際的には100万ドル(約1億5,000万円)以上の流動資産を保有する個人や世帯と定義されています。
イギリスのヘンリー・アンド・パートナーズの推計では、100万ドル以上の「ミリオネア」は世界におよそ1,700万人、全人口の0.2%に相当します。
国別の居住者数は2023年末時点でアメリカが549万人と最多で、以下、中国(86万人)、ドイツ(80万人)、日本(75万人)と続きます。
10億ドル以上の「ビリオネア」となると世界で2,650人に限られます。
より良い生活環境や税制などの好条件を求めて外国に移り住む富裕層も多くなっています。
2024年に国外移住した富裕層は12万8,000人と、2014年比で2.2倍に増えました。
色々な国が富裕層の誘致に力を入れているんですね。
日本は、都道府県では移住に力を入れているところ(我がうどん県もそうだと思いますが。)もありますが、所詮、日本国内での奪い合いであり、世界的には取り残されているような気はしますが。
まぁ、複雑な税制を根本的にシンプルなものに変えないと無理でしょうね。
あとは、先日のミャンマーの地震で1,000キロメートル以上も離れたバンコクの建設中のビルが倒壊したりしていましたが、これが影響を及ぼすかもしれません。
ドバイに続く「億万長者の街」として世界の富裕層がバンコクへ移住していることについて、あなたはどう思われましたか?
顧問税理士が語った中居正広さんとの“30年”の関係!
FLASHによると、20代女性との性的なトラブルで、解決金を払ったと「NEWSポスセブン」「文春オンライン」に報じられた、タレントの中居正広さんですが、女性との仲介役として、フジテレビの編成幹部社員が関与した疑惑も浮上し、フジテレビの港浩一社長が緊急記者会見を開くなど、社会問題にまで発展しています。
そうした影響で、中居さんがレギュラー出演していたテレビ番組5本、ラジオ番組1本の全6本はすべて消滅することになりました。
中居さんは2025年1月23日、芸能界からの引退を発表しました。
中居さんは1987年にジャニーズ事務所に入所し、翌1988年に結成されたアイドルグループ・SMAPに加入し、リーダーとなりました。
2016年12月末にSMAPが解散した後は、ソロ活動に入り、2020年2月19日に個人事務所「のんびりなかい」を設立しました。
代表取締役社長に就任し、2020年3月末にジャニーズ事務所を退所しました。
中居さんの個人事務所は、都内のオフィス街の一角にある、古いマンションの1室に法人登記されています。
代表取締役である中居さんの住所も、登記上は同じ住所になっていました。
FLASHの記者がそのオフィスを訪ねると、ドアには「〇〇税務会計事務所」という表記が貼られていたようです。
ドアをノックすると、年配の男性が対応しました。
記者が名刺を差し出すと、男性は理解したようで「ああ、中居さんの件?」と言い、こう話し始めました。
「私は、中居さん本人と会社の顧問税理士です。登記簿謄本に『のんびりなかい』の本社と中居さんの自宅住所をのせるのに、本当の住所をのせたくないということで、中居さんのほうから、本社の住所と自宅住所をここに置かせてください、ということで、こちらの住所になっています。ただ、今回の件は何も聞いていませんので、ノーコメントでお願いします」
さらに聞くと、この男性は、中居さんの顧問税理士になってから30年近いのだそうです。
「1995年か、1996年ころからです。いまほど(中居が)有名ではないころですね。そのくらいから、中居さん個人の確定申告をやっています。それまでは、お母さまがされていたそうです。
もともとジャニーズにいたマネージャーさんから、『中居さんが顧問税理士を探している』という話があり、私が引き受けることになりました。そういう関係ですから、今回のことはびっくりしています。
(中居さんは今年の収入が激減して、去年の所得分の税金を払うのに大変では?)
まあ、細かいことは言えませんけどね。
その辺はちょっと、まだ連絡もないし。2024年の3月ごろに、確定申告の件でお会いしたのが最後ですね。
『のんびりなかい』のほうは3月決算、5月申告ですので、個人と会社の確定申告の件でした。
中居さんとは毎年1、2回会うくらいです。
ここには1回も来たことはないです。
ここを調べたようで、中居さんのファンの方がお見えになったことがあります。
女性の方が3、4人で『会わせてください』と。
こちらは、オフィスのなかを見てもらいながら、顧問税理士の事務所であることを説明し、お引き取り願いました。
不満そうな顔をして帰りましたけど。
『中居さんの弟子になりたい』と話す、若い男性の方も来ましたね。
(中居さんの収入がどんどん増えていくのを目の当たりにされたのですね?)
長者番付が発表されていたころには、タレントさん部門で中居さんはトップになったこともありましたね」
中居さんは2002年度の確定申告では、俳優・タレント部門で2001年まで5年連続トップだった、とんねるずの石橋貴明さんを抑え、所得税額1億6,808万円と、初の1位に躍り出ていました。
中居さんの人柄については、こんなエピソードも。
「中居さんは、私から見るとまじめな方ですよ。
昔、『SMAP×SMAP』(フジテレビ系)をやっているころ、収録の合間にスタジオでよくお会いしました。
夏で暑くて、私は最初、アイスコーヒーを飲んでいたのですが、クーラーが効いて、途中からちょっと寒いと感じていたところ、中居さんは気をきかせて『温かいコーヒーを頼みましょうか』と。気配りのできる方でした。
2002年か2003年ころからは、草彅剛さんの個人の確定申告も、私がやっています。
草彅さんの所属事務所・CULENの飯島三智社長の紹介です。
飯島さんの確定申告もやっています。
昔は事務所に4人ほどいたのですが、いまは事務所を縮小して、私ひとりでやっています」
芸能界から姿を消した中居さんですが、今後、税金の支払いはどうしていくのか、気になるところです。
顧問税理士に話しを聞くというのもスゴいと思いますが、顧問税理士は答える必要はあったのでしょうか?
詳細が分からないので何とも言えないですが、中居さんの行為は問題があったとは推測されますが、当事者間で示談が成立しているわけであり、引退する必要はあったのでしょうか?
司会者や俳優としても才能があり、長者番付トップになったことがある方ですから、非常に残念でなりません。
芸能界が昭和時代のままなのかもしれませんが、この件を機に令和時代に変わって欲しいなぁと思います。
一方、フジテレビの対応はあまりにもひどかったのではないかと感じています。
報道機関でありながら、クローズの記者会見はありえないのではないかと思いました。
この事件があって、急に労働組合への加入者が増えているようですが、フジテレビも特殊な世界なんでしょうね。
以前、株式を保有していて好きなテレビ局ですが、今回、膿を出し切って変わらないと将来はないのではないかと思います。
第三者委員会の報告がきっかけとなることに期待したいですね。
顧問税理士が語った中居正広さんとの“30年”の関係について、あなたはどう思われましたか?
なぜ外資系高級ホテルの進出計画が続々と瀬戸内に?
中国新聞によると、瀬戸内で外資系の高級ホテルの出店計画が相次いでいます。
音戸の瀬戸公園(広島県呉市)での計画に加え、アメリカ大手ヒルトンは2028年に廿日市市宮島口西に高級ホテルを開業します。
複数の外資系高級ホテルができることで、面としての魅力が高まり、外国人観光客の集客につながりそうです。
音戸の瀬戸公園の事業で、ひろぎんホールディングス(HD、広島県広島市中区)のグループ企業は資金調達やコンサルティングなどを担っています。
ひろぎんHDは、外国人観光客にとって音戸の知名度は低いですが、高級ホテルの誘致などを通じて人気を高められると評価しました。
部谷俊雄社長は「瀬戸内には観光資源がたくさんあるのに、高級ホテルがあまりなかった」と説明しています。
広島市、呉市、尾道市でのクルーズなど「面的に瀬戸内海をうまく使うことを考えなければいけない」と語っています。
ヒルトンが宮島の対岸に開業するのは、上級ブランド「LXRホテルズ&リゾーツ」です。
ひろぎんHDのグループ社員向け保養施設の跡地に建てます。
「厳島神社を望む海辺で、ぜいたくで唯一無二の体験を提供する」とし、国内で高まる高級ホテルへの需要に対応する考えです。
広島県内では、世界的高級ホテル「アマン」の創業者が手がける新ブランドの旅館「アズミ瀬戸田」が2021年、尾道市瀬戸田町に開業しました。
四国でも、香港拠点のマンダリンオリエンタルホテルグループが2027年夏、国内2か所目のホテルを我が香川県高松市にオープンする計画です。
香川県の直島にも富裕層向けの古民家風ホテルを2027年に開業します。
観光庁の宿泊旅行統計によると、2023年に広島県に宿泊した外国人は延べ144万人と10年前の約3倍に増えました。
安田女子大国際観光ビジネス学科のジョアン・ロマォン准教授(観光学)は「繰り返し日本を訪れたい外国人は、混雑を避けられる観光スポットを瀬戸内に求めている」と分析しています。
多島美や瀬戸内しまなみ海道のサイクリングなどの魅力が広く知られるようになったのも要因とみています。
我が香川県の話しは当然知っていますが、広島でもたくさんできているんですね。
昨年、広島市に久しぶりに行ったときに、路面電車や原爆ドームなどは外国人だらけだなぁと思いましたが、外国人観光客向けとしてはいいんでしょうね。
先日、広島にお住まいの方が、広島は外国人がたくさん来ているけれど、富裕層ではないので、お金はあまり使わないとおっしゃっていましたが、どうなるんでしょうね。
札幌・東京・名古屋・大阪・福岡だけではなく、中四国地方にも来て、お金を使って欲しいと思っていますので、期待したいですね。
なぜ外資系高級ホテルの進出計画が続々と瀬戸内に?について、あなたはどう思われましたか?
「ついにナイキ王国落城へ」箱根駅伝の厚底戦争で新首位候補の”2社”が完全包囲!
PRESIDENT Onlineによると、2025年の箱根駅伝のレースの行方とともに、毎年注目されるのが選手が履くシューズのようです。
ナイキが2017年に厚底を投入後、ずっとシェア率のトップを突っ走ってきましたが、最近はライバル社も猛追しています。
スポーツライターの酒井政人さんがシューズ戦争の最新事情を報告しています。
国民的行事となっている箱根駅伝ですが、近年は箱根ランナーたちが着用するシューズも注目を浴びており、スポーツブランドの“戦い”が過熱しています。
ナイキが2017年に反発力のあるカーボンプレートを軽量でエネルギーリターンの高いフォームで挟んだ“厚底シューズ”を投入すると、シューズ革命が起こりました。
駅伝やマラソンのタイムが大幅短縮したのです。
箱根駅伝を走る選手のシューズシェア率は2018年大会からナイキがトップを独走しています。
2021年大会では95.7%(210人中201人)に到達して、1社独占のような異常事態となったのです。
その間、他社もカーボンプレート搭載の厚底モデルを開発しています。
近年はナイキの圧倒的優位が崩れているのです。
前回の2024年大会(記念大会で230人が出場)はナイキが42.6%(98人)でトップを守るも、アシックスが24.8%(57人)まで上昇しました。
アディダスも18.3%(42人)と肉薄しました。
さらにプーマが8.7%(20人)と大躍進しました。
他にもミズノ(5人)、オン(3人)、ホカ(2人)、ニューバランス(1人)、アンダーアーマー(1人)、ブルックス(1人)がいて、過去最多となる10ブランドが新春の舞台を駆け抜けたのです。
箱根駅伝のシューズシェア争いは“群雄割拠”の時代に入ったと言っていいでしょう。
そして2025年大会ですが、「ついに王者・ナイキが首位から陥落する」との予測も出てきました。
では、新王者はどこなのでしょうか?
候補はアシックスとアディダスです。
アシックスは2017年大会でシェアトップでしたが、2021年大会でまさかの0人となりました。
かつての王者が屈辱的な大惨敗を喫したのです。
崖っぷちに立ったアシックスは2019年11月にトップアスリートが勝てるシューズを開発すべく各部署の精鋭を集めた社長直轄組織「Cプロジェクト」を発足しました。
2021年3月にランナーの走り方に着目した「METASPEED」シリーズを発売したのです。
ストライド型(歩幅を伸ばすことでスピードを上げる)のランナーに向けた「SKY」と、ピッチ型(ピッチの回転数を上げることでスピードを上げる)に向けた「EDGE」の2種類があり、ともにストライド(歩幅)が伸びやすい仕様になっています。
同モデルを履いた当時33歳だった川内優輝選手が、25歳の時に出した自己ベスト(2時間8分14秒)を大幅に塗り替える2時間7分27秒をマークしたのです。
「METASPEED」が脚光を浴びるようなると、アシックスが反撃を開始しました。
箱根駅伝は2022年大会でシェア率を11.4%まで取り戻して、2023年大会で15.2%にアップしました。
前回大会で24.8%まで引き上げて、ナイキの背中がグンと近づいてきたのです。
2024年3月にはパリ五輪を前に「METASPEED PARIS」シリーズを発売しました。
新採用された「FF TURBO PLUS」というミッドソール素材が従来素材と比較して、約8.0%軽く、反発性は約8.2%、クッション性は約6.0%向上しました。
その結果、「SKY」は約20g、「EDGE」は約25g軽くなったのです。
また「SKY」はカーボンプレート前足部の幅を拡大、「EDGE」は前足部の厚みを3mm増加させたことで反発性がアップしました。
今季の学生駅伝は前年と比べて、10月の出雲駅伝で4.4%、箱根予選会で7.6%、全日本大学駅伝大会で2.7%も着用率がアップしました。
先日行われた全国高校駅伝でもアシックスの着用者が目立っていました。
前回の箱根駅伝は青山学院大学が往路をぶっち切ると、復路も独走しました。
優勝の立役者となったのが、花の2区で区間賞を獲得した黒田朝日選手と、3区で日本人最高記録を叩き出した太田蒼生選手です。
このふたりは8万2,500円(税込)のスーパーシューズ「アディゼロ アディオス Pro EVO 1」で爆走しました。
従来のレース用シューズより40%軽い片足138g(27.0cm)という超軽量モデルが彼らのポテンシャルを引き出したのです。
「抜群に軽さが違っていて、履いていても、シューズが気にならないくらいに軽いんです。僕はなかなかすごいペースで入ったんですけど、後半に何回も仕掛けることができた。脚に余力があったのは、シューズのおかげでもあるのかなと思います」と太田選手は振り返っています。
「アディゼロ アディオス Pro EVO 1」は大量生産が困難なモデルで、前回大会の着用者は3人しかいませんでした。
徐々に有力選手への提供も進んでおり、着用者が大幅に増えそうです。
今大会でもレースの命運を左右する存在になるかもしれません。
アディダスは最新のレーシングモデル「アディゼロ アディオス プロ 4」を11月27日、世界に先駆けて日本国内限定で先行発売しました。
箱根駅伝ではこちらが主要モデルになるでしょう。
また、國學院大学のエース平林清澄選手(4年)はさほどソールが厚くない「アディゼロ タクミ セン ナイン」を愛用しています。
アディダスは2025年の箱根駅伝で「ブランドシェアNo.1」を目標に掲げていますが、正月決戦の前哨戦ともいえる11月の全日本大学駅伝(関東15校)のシューズシェア率はナイキの32%に迫る28%でした。
前年(59%)を27ポイントも下落したナイキに対して、アディダスは前年を8ポイントも上回ったのです。
また、プーマも前年の6%から17%に伸ばしています。
プーマは全日本大学駅伝での着用者が2021年0人、2022年3人、2023年10人、2024年22人と右肩上がりです。
箱根駅伝でも着用者が倍増するでしょう。
山口智規選手(早稲田大学3)、斎藤将也選手(城西大学3)、青木瑠郁選手(國學院大学3)、馬場賢人選手(立教大学3)らレースのカギを握る選手が着用予定で、新たなドラマをつくるかもしれません。
最近はアディダス、アシックスらに押され気味のナイキですが、世界の舞台では結果を残しています。
2023年9月のベルリンマラソンで「アディゼロ アディオス Pro EVO 1」を履いたティギスト・アセファ(エチオピア)が2時間11分53秒の世界記録(当時)を打ち立てて、関係者を驚かせましたが、2024年10月のシカゴマラソンでその記録を今度は「ナイキ アルファフライ 3」を着用したルース・チェプンゲティチ(ケニア)が2時間9分56秒という驚異的なタイムで塗り替えたのです。
ナイキが現在販売中の最新レーシングシューズは「アルファフライ 3」と「ヴェイパーフライ 3」というモデルです。
しかし、ナイキは水面下で「ヴェイパーフライ 4」と思われる一般発売前のモデルを一部選手にプッシュしているようで、その影響がどれぐらいあるのでしょうか?
それから前回の箱根駅伝で3人が着用したオンにも注目です。
全日本大学駅伝は5人の選手がオンのシューズで出走しました。
国内ではまだ未発売の「Cloudboom 4」というモデルを着用した駒澤大学・篠原倖太朗選手(4年)が7区で青山学院大学・太田蒼生選手(4年)、國學院大学・平林清澄選手(4年)らを抑えて、ハイレベルの区間賞をゲットしたのです。
また、全日本大学駅伝では3区でトップを突っ走った青山学院大学・折田壮太選手(1年)、創価大学・吉田凌選手(4年)という実力者もオンを着用していました。
ふたりが使用していたシューズがまた斬新だったのです。
2024年7月に発表した最新テクノロジーを搭載した「Cloudboom Strike LS」というモデルになります。
自動化されたロボットアームで素材をスプレー噴射することで、接着剤フリーのつなぎ目のないアッパーを実現しています。
超軽量の立体成型のため、極薄でシームレスなつくりで靴紐なしで着用できるのです。
とにかく足へのフィット感が抜群で、サポート性を発揮しています。
インソールも中敷きもなく、足が直接ハイパーフォームに接するため、エネルギーのロスも少ないのです。
ビジュアル面でも目立つ“近未来シューズ”で快走する選手が出てくると一気に話題になりそうです。
王座奪還を目指す駒澤大学のキーマンとなる佐藤圭汰選手(3年)もオンを着用する可能性が高いです。
前回はシューズシェア率が1.2%(3人)だったブランドが、箱根駅伝2度目の登場で強烈なインパクトを残すかもしれません。
結果は、青山学院大学の優勝でしたね。
Runtripの速報によると、アディダスが76名で着用数トップでした。
今大会の出場全210選手のうち、ブランド別着用率ではアディダスが36.2%(76名)となり大きく躍進しました。
METASPEEDシリーズを展開するアシックスが25.7%(54名)と続く形となりました。
そして、ナイキの着用率は23.3%(49名)でした。
2017年にヴェイパーフライ 4%登場以来、ヴェイパーフライやアルファフライといったナイキのレーシングシューズを着用する選手が数多く見られましたが、その情勢が変化する結果となりました。
すでに登場しているアルファフライ 3やヴェイパーフライ 3のほか、ヴェイパーフライ ネクスト% 4プロトタイプを着用する選手も見られました。
さらに、プーマは11.9%(25名)、Onが1.4%(3名)、ミズノ、ニューバランス、ブルックスがそれぞれ0.5%(各ブランド1名)と続きました。
全10区間の区間賞選手の着用シューズに絞ると、10選手中着用シューズの最多は6名のアディダスでした。
全体のシューズ着用率のみならず、“速さ”においてもその勢いが現れました。
なお、アディダスを着用した選手の中でも最新モデルのADIZERO ADIOS PRO 4を着用して区間賞を獲得した選手は4名、極めて軽量なモデルとして注目を集めるADIZERO ADIOS PRO EVO1を履いて区間賞を獲得したのは2名と、選手たちの中でも選択は分かれた模様です。
なお、7区区間新記録で区間賞を獲得した駒澤大学・佐藤圭汰選手はOnのCloudboom Strikeを着用してレースに出走するなど、話題となりました。
そのほか、9区区間賞を獲得した城西大学・桜井優我選手をはじめプーマ『ディヴィエイト ニトロ エリート 3』を着用した選手も多く見られました。
沿道にも多くの観客が駆けつけ、210名の選手たちが力走する姿に声援が送られた第101回箱根駅伝ですが、選手たちを支えるシューズの今後の動向にも、注目が集まりますね。
個人的には、マラソンとかをするわけではないですが、ニューバランスとかアディダスとかプーマとかアシックスとかが好きなので、頑張って欲しいですね。
「ついにナイキ王国落城へ」箱根駅伝の厚底戦争で新首位候補の”2社”が完全包囲したことについて、あなたはどう思われましたか?
厚生労働省が次期年金制度改革での専業主婦優遇「3号」廃止を見送り!
毎日新聞によると、厚生労働省は、2025年の通常国会に法案の提出を目指している年金制度改革で、会社員らに扶養される配偶者が年金保険料を納めなくても基礎年金を受け取れる「第3号被保険者制度(3号)」の廃止を盛り込まない方針だそうです。
パート従業員らの働き控えを招く「年収の壁」の温床と批判され、日本商工会議所や連合などが将来的な廃止を求めていました。
直ちに廃止すると不利益を被る人が多いため、本格的な議論は5年後の次回以降になるとみられます。
公的年金制度の加入者には3つの区分があります。
自営業者やフリーランスなど国民年金の保険料を自ら納める「第1号被保険者」と、会社員や公務員など労使折半で厚生年金保険料を支払う「第2号被保険者」に加え、3号です。
3号の主な加入者は専業主婦やパート労働者らで、勤務する企業の規模が従業員50人以下なら年収130万円、51人以上なら同106万円未満であれば3号にとどまれます。
3号は1985年に、サラリーマン世帯の専業主婦でも自分名義の年金権を確保できるよう創設されました。
当時は約1,093万人が加入していましたが、共働き世帯の増加を背景に2024年5月時点で約676万人に減少しています。
20代女性で3号の人は1割未満ですが、35歳以上になると約3割を占めています。
2024年10月以降、連合や日本商工会議所、経済同友会が中小企業の人手不足を背景に「将来的な廃止」を求める提言を公表しました。
共働きが増加する中、働かずに年金を受け取れることに不公平感も残り、男女の賃金格差を助長するとの批判も上がっています。
年金制度改革を議論する厚労省の社会保障審議会年金部会では、これまで3号のあり方を複数回議論しています。
委員からは「女性の就労を阻む」と廃止を求める意見が上がる一方、「3号には所得保障機能がある」などと存続を求める声もあり、現段階で議論は収束していません。
年金制度は5年に1度見直されており、厚生労働省は次回以降、廃止するかどうか本格的な議論を始める方向です。
当面はパート労働者が厚生年金に入りやすくなるよう要件を緩和し、3号からの移行を目指しています。
個人的には、3号が人手不足の一因だと考えていますし、優秀な方が労働市場に出てこず、日本経済にとってマイナス効果を与えていると思いますので、5年後と言わず、早めに廃止等の検討して欲しいと思います。
厚生労働省が次期年金制度改革での専業主婦優遇「3号」廃止を見送ることについて、あなたはどう思われましたか?
王子ファイバーがマイクロプラスチック汚染対策で人工芝を紙製に!
日本経済新聞によると、細かく砕けたプラスチック片が分解されずに海中を漂う「マイクロプラスチック」は、排出源としてレジ袋や飲料ボトルを思い浮かべがちですが、実は人工芝が大きな原因であることが明らかになってきたようです。
健康や生態系への悪影響が懸念されるなか、日本のメーカーが対策に乗り出しました。
「紙から人工芝を作る。」と、2024年9月中旬、王子ファイバー(東京都中央区)の幹部らが研究開発の進捗について議論しました。
「引っ張る力に対しては合成繊維に負けない強度になってきた」「屋外のスポーツで使うためにさらに摩擦にも強くしていこう」
紙原料の糸の製造を手掛ける王子ファイバーは、技術力の応用展開の一環として2023年から人工芝の販売を始めました。
紙幣にも使われているマニラ麻の繊維で紙をつくり、それを独自の製法で糸にして編み上げます。
水に弱い紙の弱点は克服し、環境に負荷をかけない生分解性を強みとして屋内向け市場に参入する段階まできました。
「すでに家庭やオフィスのラグの引き合いがある」(平井雅一社長)ようです。
次のステップは市場規模が大きい屋外向けの人工芝です。
サッカーや野球などスポーツのフィールドに使うには、まだ耐久性が十分ではありません。
張り替えの頻度を踏まえると、価格は通常製品の4〜5倍程度にしなければ収益化しません。
販売開始は2025年度、3年ほどで年間10億円規模の売上高が当面の目標です。
コスト削減に向けて他の原料も模索するなど試行錯誤が続いています。
プラスチックごみ問題は深刻度を増しています。
経済協力開発機構(OECD)の2022年の発表によると、2019年には世界で年間2,200万トンのプラスチックが海や陸上などに流出しました。
プラごみのなかでも5ミリメートル以下のマイクロプラは、飲み水や魚から人間へと取り込まれるリスクが高くなっています。
世界自然保護基金(WWF)の資料では、クレジットカード1枚分に相当する約5グラムのマイクロプラが世界の人々の口に毎週入っている可能性が示唆されました。
人体への影響については、世界の様々な機関で研究が行われている段階です。
名古屋大学の春里暁人特任講師が海などを漂うマイクロプラを再現したものを、通常実験で使われる投与量の1,000分の1以下にして2か月間、水に含ませてマウスに与えたところ、腸の免疫の働きが落ちました。
「ごく微量の投与で安全を確認するつもりだったが、健康に何らかの影響が出るという懸念が残った」(春里氏)
人工芝が問題視されるのは、スポーツ競技などで摩耗するとマイクロプラの排出源となるためです。
パイルと呼ぶ芝部分と根元の隙間を埋めて人の足腰の負担を和らげる充塡剤で構成されるが、パイルはプラスチック製、充塡剤はゴムチップ製が主流です。
環境問題に取り組むピリカ(東京都渋谷区)は2020年から2021年にかけて、国内120地点で河川や海などに流出したマイクロプラを調査しました。
質量でみると、人工芝が25.3%を占めて最多でした。
発生源を突き止めたピリカの調査手法は国連でも導入されました。
小嶌不二夫社長は「企業は予防的に対処すべきだ」と話しています。
規制の動きも出ています。
欧州連合(EU)では2023年9月、充塡剤などマイクロプラの原因となる部材を意図的に添加した製品の域内での販売を2031年以降に禁止することを決めました。
2024年3月には東京都多摩市が国内で初めて独自の人工芝のマイクロプラ流出対策ガイドラインを公表しました。
人工芝はパイルなどの原料を仕入れて編めば一定の品質の製品になるため、中小企業や地場の織物企業が取り扱う事例も多いようです。
世界の参入業者が正確につかめないなか、環境対策の先頭に立つのは日本の大手企業となります。
住友ゴム工業はピリカの調査結果を受け、2021年から独自システムの実証実験を始めました。
流出経路となる排水溝と施設を囲むフェンスにフィルターやネットを設けたり、人工芝の外周部に流出しづらい高比重の充塡剤を使ったりする仕組みです。
定期的なメンテナンスは必要ですが、流出をほぼ防げるそうです。
住友ゴム工業は新設と張り替えの合算で年間にテニスコート約400面、サッカー場70面ほどの人工芝の敷設を手がけ、国内の面積シェアは4割程度とみられます。
ハイブリッド事業本部の長谷川浩氏は「全件にシステムを設置するべく根気よく説明を続ける」と語っています。
ミズノはマイクロプラの流出を抑えた人工芝を2014年から販売し、現在は人工芝の売上高のほとんどを占めています。
パイル1本ずつが縮れる特殊な加工を施し、ちぎれにくくしました。
充塡剤の流出は従来品と比べて新品で84%、摩耗後でも70%少ないそうです。
環境省が2023年に「環境技術実証事業」に選定し、2023年12月には台湾の「台北ドーム」でも採用されました。
足元では毎年10%ほど売上高が伸長しており、スポーツ用品で販売網のある海外展開の拡大を視野に入れています。
カネカは人工芝への導入を視野に同社が開発した生分解性プラ原料の耐久性強化などの研究を進めています。
海に流出しても微生物が分解し、最終的に二酸化炭素と水になる強みがあり、使い捨てのストローやフォークなどで利用の裾野が広がっています。
調査会社のグローバルインフォメーションは、人工芝の世界市場が2030年には2023年比で63%増の57億8千万ドル(約8,500億円)に達すると予測しています。
具体的な健康被害が出てからでは遅いです。
将来のリスクを率先して極小化する努力は、高い技術力を持つ日本企業が販路を拡大するための武器にもなるでしょう。
少し前から、『マイクロプラスチック』のことがニュース等で取り上げられ、ペットボトルなどが結構気になっていましたが、人工芝が大きな原因なのと、対策は日本企業が進んでいるということを知り、驚きました。
スポーツに影響を及ぼしてはいけないと思いますし、日本企業の技術力の高さを世界に示し、対策ができるといいですね。
王子ファイバーがマイクロプラスチック汚染対策で人工芝を紙製にすることについて、あなたはどう思われましたか?
タリーズの顧客9万人の情報漏洩の可能性!
朝日新聞によると、タリーズコーヒージャパンは、先日、通販サイト「タリーズオンラインストア」が不正アクセスを受け、会員登録していた顧客9万2,685人の個人情報が漏えいした可能性があると発表しました。
このうち5万2,958人は、クレジットカードの情報が流出したおそれがあるそうです。
タリーズコーヒージャパンは、2024年5月、不正アクセスによって顧客情報が漏れた可能性があると発表し、サイトを一時閉鎖し、第三者調査機関による調査を進めてきました。
漏えいした可能性があるのは顧客の氏名や住所、電話番号、メールアドレスなどです。
さらに、2021年7月以降に通販サイトの決済で使ったクレジットカードについて、カード番号と名義人名、有効期限、セキュリティーコードが漏れた可能性があります。
対象者にはメールや郵送で個別に連絡しているそうです。
タリーズコーヒージャパンは「今回の公表に至るまで時間を要しましたことを深くおわび申し上げます。このたびの事態を厳粛に受け止め、再発防止を図ってまいります」などとコメントしました。
クレジットカードのセキュリティーコードが漏れた可能性があるというのがよく分からないのですが、セキュリティーコードを保存しているのでしょうか?
一律に補償(お礼?)するにしろ、かなりの額になると思いますし、委託先とかから漏れていたのかもしれませんが、そういうところに委託することに責任があるわけですから、タリーズコーヒージャパンは信用をかなり失ったでしょうね。
タリーズの顧客9万人の情報漏洩の可能性について、あなたはどう思われましたか?
金融庁がビッグモーターの不正で大型保険代理店に新規制!
日本経済新聞によると、金融庁は大規模な保険代理店の規制強化に乗り出します。
複数の保険会社の商品を扱う一定規模以上の乗り合い代理店に対し、コンプライアンス(法令順守)担当者の設置を義務づけるなど複数の案を検討します。
内部管理体制の拡充を求めることで、中古車販売店大手の旧ビッグモーターによる保険金不正請求のような不正が再発する事態を防ぎます。
鈴木俊一金融相が、金融審議会(首相の諮問機関)総会で、新規制の検討を諮問する見込みです。
金融庁は2024年9月中に新たな会議体を立ち上げ、有識者を交えた議論を始めます。
2025年に保険業法改正案を国会に提出することを視野に、新規制案の具体化を急ぎます。
15社以上の保険会社の商品を扱うなど一定規模以上の代理店は現在、保険会社から受け取る手数料などを記した事業報告書を年1回提出する必要があります。
こうした代理店は500社程度あるとみられます。
新たに上乗せする規制では対象の代理店を更に絞り込んだうえで、法令順守の強化につながるルールを追加で課していく方針です。
法令順守担当者の配置や、内部通報体制の構築を義務づける案などを検討する見通しです。
新規制の対象となる代理店を決めるため、保険会社に取引関係がある大規模代理店の保険料収入の提出を求めるなど現状把握のための調査を進めます。
調査結果を基に、保険料収入や従業員数といった新たな大型代理店の基準を設けた上で、規制を適用していく方向です。
金融庁が大規模な乗り合い代理店に照準を合わせる背景には、旧ビッグモーターによる大規模な不正の発覚があります。
旧ビッグモーターでは、会社法上の要件を満たす取締役会を開いていなかったり、内部通報の規定が整備されていなかったりするなどガバナンス(企業統治)上の不備が多数見つかりました。
金融庁は、不適切な内部管理体制が不正の拡大を招いたとみています。
大型代理店は顧客の数が多く、不正が実行された場合の被害も大きくなる可能性があるため、規模の小さな代理店よりも厳しい規制が必要だと判断しました。
ブローカー(保険仲立ち人)の活用促進に向けた議論も始めます。
今の規制ではブローカーと保険代理店が協業することはできませんが、この規制の緩和を検討し、企業がブローカーと代理店の両方を使って、より良い内容の保険契約を結べるようにします。
2023年に発覚した大手損保による企業向け保険の価格調整問題では、企業が自社グループの代理店に依存し、不適切な保険契約を見破れない実態も浮き彫りになりました。
より中立的な立場のブローカーが関与することで、企業が対等な立場で保険会社側と交渉し、カルテルなどの不正が起きないようにします。
金融庁は大型代理店に対する新規制の検討と並行して、資金決済法の見直しについても議論を始めます。
同法は銀行以外の事業者にも一定の決済サービスなどの提供を認める「資金移動業」を規定しています。
この資金移動業の登録に関する要件が、現在の金融サービスの状況に合っているかを検討します。
例えば、近年増えている後払い決済サービスを提供する事業者は資金移動業の登録対象になっていません。
利用者から資金を事前に預かり、支払いに充てる従来の決済サービスとは異なるためです。
ただ、事前に資金を預かっていないとしても、提供しているサービスの質は同等だとの指摘もあります。
金融庁関係者は「世の中の動きに法律が追いついていないなら必要な部分は見直していきたい」と語っており、今後立ち上げる金融審議会の作業部会で議論していく考えのようです。
自己の利益のために、お互いが修理を依頼したり、保険の契約を取っていたりしていたわけですから、その辺りはきちんと規制して欲しいですね。
あと、保険会社が大手代理店に広告費を支払うなど、自分のところの保険を扱ってもらうために渡したり、大手代理店に出向した保険会社の職員が個人情報を漏らしたりしているわけですから、コンプライアンスの面も含めて、保険会社と大手代理店のおかしな関係を断ち切って欲しいですね。
金融庁がビッグモーターの不正で大型保険代理店に新規制をすることについて、あなたはどう思われましたか?
日本生命の元職員が顧客個人情報を公開など生保会社で客の金銭詐取が続出の理由!
日本生命保険の元女性職員が、インターネット上にプロ野球球団・読売巨人軍の選手への殺害予告を30回以上にわたり投稿し、威力業務妨害の容疑で逮捕されました。
女性は日本生命の顧客情報管理システムの当該選手の画面を撮影し投稿していました。
なぜ生保職員・元職員による不正や犯罪が絶えないのでしょうか?
Business Journalが、業界関係者の見解を交えて追っています。
生保元職員による不正事件として世間から大きな関心が寄せられたのが、2020年に発覚した、第一生命保険の元・特別調査役の女性による約19億円の金銭詐取事件でした。
女性は計24人の顧客に架空の金融取引を持ちかけていたが、第一生命保険では他にも元職員による複数の金銭詐取事案が発覚し、被害総額は20億7,690万円に達しました。
2023年には、日本生命の元営業職員が90代の女性に架空の保険契約を提案するなどし、約1,532万円をだまし取っていたことが発覚しました。
先月には明治安田生命保険の元営業職員が顧客10人から約1億3,000万円をだまし取っていたと発表しました。
1994年から2021年までの間、保険料を着服したり、顧客から預かった通帳を使って、契約した保険を担保にお金を借りる制度を悪用して振り込まれたお金を着服していたのです。
なぜ生保職員による不正が相次いでいるのでしょうか?
大手生保社員は言っています。
「現場の生保レディは顧客と非常に親密、かつ何年ものお付き合いをするケースも珍しくなく、顧客から心を許されて通帳を預けられることもある。顧客のなかには高齢で高額な資産を持つ人もおり、業務で扱う金額は何千万単位と高額で金銭感覚が麻痺しやすいうえに、生保レディの給与はそれほど高いわけではない。こうした事情が重なり、『自分もちょっとぐらい得していい』『相手の判断能力が低下しているからバレない』と勘違いして不正に走る人が出る。もっとも、生保会社で働く営業職員は全国で20万人以上おり、確率論的に悪いことをする人が一定数出てくるのは避けられない」
不正が相次ぐ生保会社だが、その業務は金融庁によって厳しく監督されています。
発売する商品や各種契約書類などはすべて金融庁の認可が必要であり、保険募集においては顧客への情報提供や意向把握が義務化されており、逸脱行為があれば金融庁から業務改善命令や業務停止命令などの行政処分を受けます。
そんな生保の営業現場を支えてきた営業職員の労働環境は、独特であることが知られてきました。
いわゆる「ターンオーバー」といわれる大量採用・大量離職が常態化し、かつては入社2年後の離職率は7~8割にも上るといわれ、人の入れ替わりが激しかったのです。
背景には過酷なノルマと歩合給があります。
飛び込み営業を強いられ、ノルマ未達の際には知人に名義を借りて新規の保険契約をつくり、自腹で払う「自爆営業」も横行しました。
給料のうち歩合給の割合が大きいため、契約が取れないと給料が著しく落ち込む仕組みも長く続いていたのです。
「親戚や知人の生命保険契約を切り替えさせ、契約に入ってくれる知り合いがいなくなれば辞めてもらうという“使い捨て”が当たり前だった」(同)
そんな環境がここ数年、大きく変化しています。
日本生命は採用数の目標値を撤廃し、2021年度の採用数は前年度より15%程度減少するなど、各社は年間の採用数を抑制しています。
平均賃金を一律で引き上げ、固定給の割合を増やしたり、既存顧客の継続率やアフターフォローへの取り組みを評価に組み入れるなど“新規契約獲得主義”からの脱却を進めつつあるのです。
「かつて生保の支店や営業所では、営業職員の成績を壁に貼りだしたり、成績が悪い職員を怒鳴ったりといったことが普通に行われていたが、今ではどの大手でも、そのような光景はほとんどみられなくなったのではないか。
ネット生保や保険ショップの台頭により、対面の営業職員経由での新規契約の数が減っているものの、いまだに対面営業は主要な販売チャネルではことには変わりない。
だが、“生保の営業の仕事はキツイ”というイメージが定着していることや、全業界での人手不足で他にも仕事がたくさんあることも影響して、かつてのように黙っていても営業職員のなり手が集まるという状況ではなくなった。
なので生保各社は、待遇を引き上げる一方で人材を厳選して採用するようにし、優秀な人材には長く働いてもらえるよう努力するようになった。
かつてのような“ムチで叩く”やり方ではすぐに人が辞めてしまうため、研修を充実させるなどして職員一人ひとりのスキルとモチベーションを向上させてパフォーマンスを発揮させるという方向に大きくシフトした。
要は、長い年月を経て生保業界もやっと、まともになったということ」(前出・大手生保社員)
また、金融業界関係者は言っています。
「かつては昼休み時間に生保レディが職場に出入りして社員に声をかけ、グッズやパンフレットを配って営業活動する光景がみられたが、現在ではオフィスビルのセキュリティーが厳しくなったこともあり、ほとんどなくなった。
会社の受付に備え付けられた内線電話前に陣取って、片っ端から社員に内線で営業電話をかけたり、若い男性社員をターゲットに合コンを設定して囲い込みを図る猛者もいたが、最近ではそれすらも難しくなっており、生保レディたちはいろいろな工夫をして見込み顧客への接触を図ろうとしている。
生保各社は営業職員の評価基準に既存顧客の契約継続率や顧客訪問の頻度といった項目も加えて評価軸の多様化に努めているが、依然として新規獲得件数が最重要視される傾向は変わらない。
業界特有の、入社3年目くらいから固定給が減る仕組みも残っている。
加えて、最近では顧客者側も保険の購入を検討する際には自分で情報を入念に調べたりフィナンシャルプランナーに相談したりして知識が豊富になっており、営業職員はこれまでのようなGNP(義理・人情・プレゼント)が通用せず、自社・他社の商品に関する知識量とロジカルな説明スキルが求められるようになった。
こうした変化も踏まえ生保各社は、営業職員の採用で厳密な選考を行い人材をより厳選する一方、優秀な職員には長く残ってもらうように取り組み始めた。
要は人材の取捨選択の度合いを強めている」
僕の担当者も過去に何人か変わっていますが、個人情報保護法やコロナなどでなかなか会うこともできず、生保レディも大変なんでしょうね。
まったく話しのかみ合わない飛び込みの生保レディも過去に何人かいましたが。
あとは、商業施設などに来店型の保険代理店も結構入っていますから。
日本生命の元職員が顧客個人情報を公開など生保会社で客の金銭詐取が続出の理由について、あなたはどう思われましたか?
イオンが定額減税で「4万円均一」消費喚起セール!
日本経済新聞によると、イオンは先日、全国の総合スーパー(GMS)の500店舗で定額減税に伴うセールを順次、始めると発表しました。
GMS子会社のイオンリテールでは関東や関西など本州の店舗で寝具やベビーカーなどの「4万円均一」商品を用意しました。
トマトなど野菜の値下げ品も企画します。
インフレで低迷する消費を喚起し、6月の売上高を前年同月に比べ1割増やします。
セールはイオングループの北海道から沖縄まで全国に出店する500のGMSでそれぞれ実施します。
対象とする商品や数量などセールの中身は、地域によって異なります。
このうち、イオンリテールは本州の380店でセールします。
6月のセール企画は前年に比べて2倍の19種類を投入し、セール対象品は前年同月比2倍の850品目に及びます。
まず、税抜きで4万円均一の企画ではマットレスと枕とベッドのセット品やコードレスの掃除機、ベビーカーなどメーカー製品を中心とした11品目を数量限定でそろえました。
通常は5万円~6万円程度の商品で、最大4割引きで提供します。
また、トマト1個やジャガイモ3個などで「105円」均一などインフレで節約志向の強い消費者の購入を促すセール企画も提供します。
小売り各社も動きます。
スーパー大手の西友は13日から加工食品や日用品などを最大3割引きで特売しています。
百貨店の松屋は1日から松屋浅草店(東京都台東区)で和牛や果物など食料品の一部商品を1〜2割引きで提供しています。
定額減税は、政府が近年の税収増を還元して家計支援につなげる目的で6月から実施しています。
1人当たり所得税から年3万円、住民税から年1万円を差し引きます。
納税者本人だけでなく配偶者や子供ら扶養親族も対象になり、家計負担の一定の軽減につながると期待されています。
ただし、インフレに伴う消費動向は冷え込んでいます。
物価変動の影響を除いた実質賃金は3月に24か月連続でマイナスになりました。
3月の家計調査でも、2人以上世帯の消費支出は実質で13か月連続のマイナスを記録しています。
公的年金は2024年度に前年度から2.7%引き上げられましたが、生鮮食品を除く総合の物価上昇率の3.1%(2023年)より低くなっています。
大企業では賃上げが広がりましたが、中小企業まで波及は厳しく、年金受給者も余裕ありません。
先日、イオンスタイル品川シーサイド(東京都品川区)を訪れた30代女性は「野菜の価格が高騰し、子供の離乳食用には買うけど大人の分は安いカット野菜で済ませている。定額減税はあまり意識していなかったが、安ければ買いたいと思う」と話していました。
イオンリテールの伊藤竜也営業企画本部長は「インフレで生活防衛意識が高まり、国内消費は低迷している。イオングループとして定額減税をきっかけとして消費を喚起し、日本を元気にしたい」と語っています。
個人的には、一度に1人当たり4万円支給・減税されるわけではないので、4万円均一のセールをしたところでそれほど効果はないのではないかと思います。あとは、セールによる値下げ分をイオンが全額負担するのであれば構わないと思いますが、おそらく仕入先にも負担させているので、仕入先は大変だろうなぁと思います。特に、野菜を作っている法人や個人事業主は、需給関係によって価格が決まるため、物価高騰などによるコストアップ分を販売価格に転嫁できていないところが多いと思いますので。
いつもイオンなどを見ていると、消費者のためということで値下げとか価格据え置きとかやっていますが、買いたたかれる仕入先の役員・従業員・従業員(そのご家族)も結局、消費者なので、仕入先の方の給料が上がらず、消費に回らないという誰も得しないことになっているのではないかと思いますね。
やはり、安ければいいということでなく、適正な価格で売るというのが重要なのでないかと考えます。
イオンが定額減税で「4万円均一」消費喚起セールをしていることについて、あなたはどう思われましたか?
ホタルイカ大漁は南海トラフ地震の前兆か?
暗闇の中、海面を神秘的に青白く照らす無数の光、その正体は「イカ」です。
週刊現代によると、今春、富山湾でホタルイカが文字通り“爆湧き”しているようです。
2024年3月の漁獲量は、昨シーズンの16倍、1953年の統計開始以来最も多かったようです。
当然、地元は大喜びかと思いきや、この奇妙な現象に一抹の不安を抱えていました。
滑川漁港のベテラン漁師は言っています。
「イカ漁師の間では、大地震の前にはイカがよく獲れるってのは、有名な話さ。おらの親父も南海地震が起きた年(1946年)は、イカが豊漁だったと言ってたな。能登半島地震が起きたばかりだけど、もうすぐでっかい地震が来るかもな」
地震大国の日本では、古くから様々な自然現象を大地震の予兆と捉えてきました。
海の生物の異常行動もその一つです。
2011年の東日本大震災、さらに1995年の阪神・淡路大震災でも、直前にイカの漁獲量が大きく増えています。
これは偶然ではありません。
2024年4月に入り、研究者たちの間でにわかに大地震、マグニチュード(以下M)8~9クラスの南海トラフ地震への警戒度が高まっているのです。
東京大学地震研究所名誉教授の笠原順三氏が警鐘を鳴らしています。
「4月以降、日本列島近辺でフィリピン海プレートがユーラシアプレートに沈み込む動きに起因する地震が多発しています。プレートの境界である南海トラフにひずみがどんどん蓄積しているのは間違いありません」
4月3日、台湾をM7.7の大地震が襲ったことはまだ記憶に新しいですが、震源に近い花蓮県では震度6強を記録し、高層ビルの倒壊などで多くの死傷者を出しました。
それからわずか5日後の4月8日、鹿児島県・大隅半島東方沖を震源とするM5.1の地震が発生しました。
「地震の波がじわじわと日本のほうへ近づいているのではないか……?」
その不安は現実となりました。
4月17日、今度は愛媛県と大分県に挟まれた豊後水道を震源とするM6.6の地震が起きたためです。
同地域では実に56年ぶりの大規模地震です。
とはいえ専門家の中には「豊後水道の地震と南海トラフ地震とは関係しない」と主張する者も少なくないようです。
その論拠は、豊後水道の地震が、プレートを引き裂くような引っぱりの力が働いて起こる「正断層」型だったという点にあります。
他方、南海トラフ地震はプレートを押し潰すような圧縮の力が働いて起こる「逆断層」型ということがわかっています。
そもそも2つの地震はメカニズムが異なる、というわけです。
ところが、笠原氏の考えはまったく違います。
「正断層型と逆断層型が連動することを多くの人は見落としています。2006年に千島列島沖で起きたM7.9の大地震がよい例でしょう。この時は最初に逆断層型が、その直後に正断層型の地震が起き、研究者をはじめ皆が驚きました。したがってその逆、正断層型により逆断層型が誘発されることも想定できます」
台湾もいまだ予断を許さない状況が続いています。
4月23日には再びM6.6の大きな地震を観測しました。
笠原氏が続けています。
「台湾で相次ぐ揺れは、当初こそ3日の余震と考えられていましたが、今では群発地震の様相を呈しています。南海トラフに関連する場所での地震に引き続き警戒する必要があります」
ついつい大きな地震にばかり目がいってしまうかもしれませんが、「小さな地震」にも注視したいですね。
気象庁の調べによれば、4月16日~22日の1週間に観測された地震活動は6,000回以上です。
そのうち、豊後水道だけで2,079回にものぼっています。
その大部分を占めるのが震度1程度の「人間が感じることのできない小さな揺れ」です。
個人的には、兵庫県で阪神・淡路大震災、東京都で東日本大震災を経験していますので、地震はすごく気になるのですが、先日、こどもたちの小学校の参観の時に、『南海トラフ』の授業をやっていましたが、我が香川県は南海トラフがいつ来てもおかしくない状況でしょうね。
個人的には、物流はどうなるのだろうか?、四国が孤立化するのではないだろうか?、瀬戸内海では津波はどうなるのだろうか?などと色々考えています。
備えられることは、備えていきたいと思いますね。
ホタルイカ大漁は南海トラフ地震の前兆か?について、あなたはどう思われましたか?
和牛の子牛価格は暴落しブロッコリーは高騰!
テレビ朝日によると、物価高や異常気象で食材の価格の波が大きくなり、消費者の負担が増しています。
一方で、生産者も高騰や暴落に頭を悩ませていて、沖縄では日本が世界に誇る和牛に異変が起きています。
石垣島で30年以上、親子三代で牛の繁殖農家を営む宮良妙子さん(62)は現状をこう話しています。
宮良さん
「1頭70万~80万円で売れていた牛が、コロナ禍で50万円ぐらい下がって、今は30万円ぐらいになってますね」
今月ここまで行われていた市場の平均価格は1頭あたりおよそ40万円です。
去年の同じ月と比べ、マイナス7万円になりました。
JA沖縄によると、その要因の一つは、物価高だといいます。
比較的安い鶏肉や豚肉などへ消費の流れが変わり、和牛の価格が上がりにくくなっているのです。
それに加えて、ウクライナ侵攻や円安の影響で、エサ代が高騰しています。
石垣島という立地にも理由がありました。
宮良さん
「特に離島は遠いので、飼料も牛自体も運搬する上でのハンディもある。(買い手は)ちょっとためらうのではないかなと思います」
宮良さんの農家では、(メスの子牛の場合)30年前ならば子牛をセリに出すまで18万円ほどかけて育て、36万円ほどで売れていました。
現在は育てるまでに40万円もかかるため、平均販売価格のおよそ35万円で売ると5万円の赤字になってしまいます。
宮良さん
「子牛を育てれば育てるほど、赤字が増えるという現状があります」
同じ石垣島の繁殖農家の中には、専業から離れる決意をしたという人もいるといいます。
繁殖農家 歴3年 30代男性
「兼業がもし赤字補填できるほどにうまくいかなければ、いずれは体力が尽きて離農するしかなくなるのかなという感じはしますね」
男性のように兼業に切り替えたり、農業をやめたりした人が増えたといいます。
畜産農家の努力だけでは、もはやどうにもならないと宮良さんは話します。
宮良さん
「和牛は本当に世界的なブランドなので。和牛が潰れてしまう、和牛を守る手立てを政治が考えてほしいと思います。一生懸命育ててるのにね。消費者にきちんと届いてくれたら、本望だと思うんだけど」
価格が暴落する食品もあれば、反対に高騰している食品もあります。
ブロッコリーの価格が跳ね上がっているのです。
買い物客
「最近しばらく買ってない」
「(Q.きょうは398円)買わない」
青果店の店主も、あきれるほどの高値です。
千駄木金杉青果店 鈴木孝弘店主
「150円から高くても180円ぐらいで売れていたかなという記憶はあるんですけど、398円はちょっと高すぎますよね」
ブロッコリーの仕入れ値は通常、1株100円から150円でしたが、直近では378円で仕入れたといいます。
398円で売っても、ほぼ利益が出ません。
先週はキャベツの店頭価格が1,000円を超える事態になったため、店主は頭を抱えています。
鈴木店主
「(Q.キャベツとブロッコリーの価格高騰について)八百屋さんでは上位の人気野菜で、皆さん大体買われるので。それが高いというのは、売り上げにも大ダメージです」
なぜこんなにまで値上がりしているのでしょうか?
卸売業者を訪ねました。
國崎青果 関東営業所 小園智之所長
「全国的に今年は天候不良によって、ブロッコリーが順調に成長しなかった」
特に九州と四国では、出荷量が去年のおよそ5分の1に落ち込んでいる地域もあるといいます。
ブロッコリーがいつもの価格に戻るのは、いつになるのでしょうか?
小園所長
「今週から徐々に下がってくるとは思うんですけど。福島、新潟、鳥取(の出荷)が出てきて、今後落ち着いてくると思います」
ブロッコリーの他にも、リンゴやミカンも値上がりしているという状況です。
食卓に当たり前にある食材が軒並み高騰していて、家計への圧迫はしばらく続きそうです。
先日新聞に載っていましたが、我が香川県(うどん県)はブロッコリーの出荷額で全国2位になっています。
需要と供給により価格が決まる世界ですから、個人的には、当然ではないかと思います。
農家の方も、価格が高騰するときは野菜などを作れていないわけですから。
基本的に、野菜などは高くなったときにニュースなどで取り上げられますが、基本的に農家の方が値付けをできない市場出荷やJA出荷を根本的に見直す時期に来ているのではないかと思います。
肥料や苗などの価格が上がっても、価格転嫁ができない状況なのですから。
和牛の子牛価格は暴落しブロッコリーは高騰していることについて、あなたはどう思われましたか?
“家族の代わり”担う「身元保証」サービスの指針案の課題は?
「介護施設に入るには保証人が必要と言われましたが私は1人なので…」。
夫に先立たれ、その後、重度のやけどをして1人での生活が難しくなった80歳の女性に頼める家族はなく、途方に暮れる中、助けとなったのは高齢者の「身元保証」を行う事業者でした。
単身高齢者の増加を背景にいま、こうした事業のニーズが高まっています。
しかしながら、NHKによると、ルールがないことから契約上のトラブルも相次いでいて、国は初めて指針の案を示すなど対策に乗り出しています。
入院や施設への入所などの際に、緊急時の対応などのために求められることがある「身元保証」は、法律などで規定されたものではなく、病院や介護施設などが慣習的に求めているものですが、身寄りのない人や頼れる親族などがいない人がサービスを受けられないケースが問題となっています。
静岡県静岡市の介護施設で暮らす80歳の女性は夫に先立たれて市内の自宅で暮らしてきましたが料理中に大やけどをして手術をしたあと、1人での生活は難しくなり、ことし1月、介護施設への入所を希望しました。
ところが、入所の際に求められた「身元保証人」を頼める人がなく、希望した施設には入所できませんでした。
当時の状況について、女性は「介護施設は今の世の中、どこに入るにも保証人などが必要ですが、私は1人なのでしかたがないと思いました」と振り返ります。
その後、女性は市内で身元保証事業を行う社会福祉法人に相談し、事業者に保証人になってもらい、別の介護施設への入所が実現しました。
事業者は入所時の「保証人」になるだけでなく、施設での暮らしに必要なものを買って届けるなど、日常生活の支援もしていて、この日は女性と一緒に振り込みの手続きのため、郵便局の窓口まで付き添っていました。
女性は「病院の付き添いなどもいつも助けていただいて非常に助かっています。お互いに信頼がなければ、そうしたことを頼むこともできないので、家族のような存在です」と話していました。
事業者が保証人になることを条件に、女性を受け入れた介護施設の施設長は「利用者の体調に変化があったときの相談や病院の受診、容体急変時の救急搬送、入院手続きなどはこれまでは親族に頼らざるをえなかったので、事業者のこうしたサービスはとても助かります」と話していました。
身寄りのない高齢者に入院時の「身元保証」などを行う民間のサポート事業をめぐっては、単身の高齢者の増加などで需要が高まる一方、監督する省庁や法律はなく、契約をめぐるトラブルも相次いでいます。
国民生活センターによると、全国の消費生活センターなどに寄せられた相談件数は2018年は100件でしたが去年は302件と5年で3倍以上に増えていることがわかりました。
契約や解約に関する相談が最も多く、「希望していないサービスを追加され高額になった」や「解約を申し出たが返金されない」といった相談があったということです。
こうした状況を受け、厚生労働省などはサービスの健全性を確保し、高齢者などが安心して利用できるよう事業者が守るべき指針の案を初めてとりまとめました。
指針案ではサービスの内容や費用をホームページなどで表示することや、解約や返金方法は重要事項として書面で説明することが望ましいとしています。
また、サービスの提供にあたっては、内容や費用などを記録して定期的に利用者に知らせることや認知症などで利用者が十分に判断できない場合は成年後見制度の活用も求めています。
厚生労働省などは、指針の案についてパブリックコメントを行って意見を募ったうえで最終的な策定を目指すことにしていますが、指針に強制力はなく、監督官庁も決まっていないことから今後、事業が適正に行われているかチェックする体制の整備などが課題となります。
今回の指針の案で、身寄りのない人が入院や施設入所などの際に求められる「身元保証」や、買い物や通院の付き添いなどの「日常生活支援」、亡くなったあとの葬儀や遺品の処分などの「死後事務」を行うサービスは「高齢者等終身サポート事業」と位置づけられました。
こうした事業は、高齢化や単身世帯の増加などを背景に、「介護保険」といった既存の制度では補いきれない部分のニーズを引き受ける形で利用者が増えているとみられます。
事業を利用している殿岡さえ子さん(71)は都内で1人暮らしをしていて、交通事故の影響で高次脳機能障害があるほか、腰椎に痛みもあります。
そのため、月に数回のクリニックへの通院時には、事業者の付き添いサービスを利用していて、この日は男性スタッフが診察に立ち会い、医師の問診を一緒に聞いたり、骨折予防の注射を打つのを見守ったりしたほか、受診料の支払いなどをサポートしていました。
殿岡さんは「今は特に体の具合が悪いので重い荷物を持ってくれたり、一緒にあちこち連れて行ってくれたりするのはとても楽で助かります」と話していました。
こうしたサービスは、事業者との契約に基づいて行われ、支援は亡くなったあとまで続くことから契約が長期にわたるのも特徴です。
そのため、この事業者は利用者の容体が急変したときに備え、受けたい医療や最期に過ごしたい場所などの要望を定期的に確認しているほか、亡くなった後に備え、葬儀や納骨などを行うことをあらかじめ定める契約も結んでいます。
身元保証などを行う事業者の小池安喜さんは「利用者が元気なうちからいざというときの希望や思いを聞いておくことではじめて本人の意思を代弁することができます。高齢で身寄りがなければ、生活に不備が生じる場面が現実にはあり、支援を通じて安心につなげられればと思います」と話していました。
「身元保証」などを行う事業のニーズが高まる中、独自に事業者の質の確保に取り組み始めた自治体も出てきています。
静岡県静岡市ではことし、契約ルールや解約時の返金手続き、利用者からの寄付の扱いなどの基準を新たに定め、条件を満たす場合に限って3年間「優良事業者」として認証する制度を導入しました。
認証の取得を希望した事業者に対しては市がヒアリング調査などを行い、支援や契約の内容、個人情報の取り扱いなど市の定めた基準にのっとった運用をしているか、細かく確認します。
そして基準を満たすと確認できれば「優良事業者」として認証しますが、基準は30項目以上と多岐にわたるため、認証を得たのはまだこの1法人だけです。
今後どれだけ公的な枠組みの中で「身元保証」などの事業の普及が進むかが課題になっています。
認証事業を始めた静岡市地域包括ケア・誰もが活躍推進本部の担当者は「市が一定のルールを作って事業者の質の確保に関わることで、一人暮らしで困っている高齢者が安心して過ごせるよう、終活支援の手伝いができればと考えています」と話していました。
静岡県静岡市内で唯一の認証を受けた事業者で、社会福祉法人「まごころ」の田中努さんは「何もルールがない中での運営は高齢者からすればどの事業者を選んだらいいかわからず戸惑う一方、私たちも手探り状態で支援をするには不安があったので、認証という形でルールを設けてもらえるのはありがたいです。いま多くの高齢者に求められる大事な事業だと思うので、これからは自信を持ってサービスを提供していきたい」と話していました。
事業者向けの指針の案が初めて示されたことについて、「身元保証」などの問題に詳しい日本総合研究所の沢村香苗研究員は「身寄りのない人の増加とともにこれまでは家族が担ってきた役割を代行するサービスへのニーズが高まる中、今回、指針が示されたことで事業者の質をある程度担保して高齢者に不利益がないよう手だてがとられた意義は大きい」と話しています。
その上で、今後の課題については「事業を監督する官庁がない前提は変わっていないので示された指針を事業者がしっかり守れているか、守らなかったらどうなるのかといった実効性や仕組みの検討が必要です。また、支援は有償なので、経済的な事情や判断能力が十分でないなどの理由で利用できない高齢者への対応も考える必要がある。そして、事業者がいるからといって全部を担ってもらおうとすると負荷が高まるため、自治体や地域のほか、親族がいる人はその力も借りて身寄りがない人をより多くの人で高齢者を支えていく体制づくりを目指すべきだ」と話していました。
現代社会においては、『身元保証』は必要なサービスだと思いますが、監督する省庁や法律がないというのは驚きでした。
静岡県静岡市の取り組みはとても素晴らしいことだと思います。し国としても、早く対応して欲しいですね。
そうしないと、きちんとしていない業者がたくさん出てきて、『身元保証』というサービス自体が信頼されない状況になってしまうと思います。
“家族の代わり”担う「身元保証」サービスの指針案の課題について、あなたはどう思われましたか?
Googleが迷惑メール対策を大幅強化しGmailに送れなくなる恐れ!
日本経済新聞によると、アメリカのGoogleが2024年2月以降、迷惑メール(なりすましメール)対策を大幅に強化した「メール送信者のガイドライン(Email sender guidelines)」を適用すると発表し、メールに携わるIT(情報技術)業界関係者に衝撃が走っているようです。
メールの送信者がこのガイドラインの要件を満たしていない場合、世界最大規模のメールサービス「Gmail」にメールを送れなくなる恐れがあるためです。
具体的には、送信したメールが拒否されたり、受信者の迷惑メールフォルダーに配信されたりする可能性があります。
メール配信事業者や企業のメールサーバー管理者などは、2024年2月の適用開始までに対策を施す必要があります。
なお、通信事業者やインターネット接続事業者(ISP)のほとんどは対応済みなので、それらが割り当てたメールアドレスのユーザーは影響を受けません。
Googleが2023年10月3日(米国時間、以下同)に発表したガイドラインによると、対象になる宛先アドレスは、個人向けのGmailアカウントです。
末尾が@gmail.comまたは@googlemail.comのメールアドレスです。
ガイドライン公開当初は、法人向けクラウドサービスGoogle WorkspaceのGmailアカウントも対象になるとしていました。
しかしながら、2023年12月初めに実施したガイドラインアップデートで対象から外しました。
また、その後、メールの送信にTLSを使用するという要件も加えました(要件については後述)。
TLSは通信を暗号化するプロトコル(通信規約)です。
Googleは今後もガイドラインを適宜アップデートする可能性があります。
このため関係する企業は最新の情報を絶えずチェックする必要があるのです(ガイドラインのURLはhttps://support.google.com/mail/answer/81126)。
今回のガイドラインはすべてのメール送信者が影響を受けます。
しかしながら、特に深刻なのは、Gmailアカウント宛てに大量のメールを送信しているメール配信事業者や企業です。
ガイドラインに記された要件は、Gmailアカウントに1日当たり5,000件以上のメールを送っているかどうかで異なるからです。
一番の違いは、対応すべき送信ドメイン認証の種類です。
送信ドメイン認証とは、送信元メールサーバーのIPアドレスや送信元が施した電子署名を利用して、メールがなりすまされていないかどうかを判断する仕組みです。
1日当たり5,000件未満の送信元は、送信ドメイン認証の「SPF」と「DKIM」のどちらか一方に対応する必要があります。
一方、5,000件以上の送信元はSPFとDKIMの両方に対応した上で「DMARC(ディーマーク)」にも対応しなければならないのです。
1日当たり5,000件未満と5,000件以上で共通の要件もあります。
具体的には「送信元のドメインまたはIPアドレスに有効な正引き及び逆引きDNSレコードを設定する」「メールの送信にTLSを使用する」「受信者から報告される迷惑メールの割合を0.1%未満に保ち、0.3%を超えないようにする」「Internet Message Format標準に準拠する」などです。
国内最大のメールセキュリティー団体「JPAAWG」の会長を務める、インターネットイニシアティブ(IIJ)技術研究所技術連携室の櫻庭秀次シニアリサーチエンジニアによると、これら共通の要件については「配信事業者や企業の多くは既に対応済み」だそうです。
1日当たり5,000件以上の送信元だけの要件もいくつかあります。
その1つがDMARCをパスすることです。
これはメールソフトやウェブブラウザーなどに表示される送信者アドレス(ヘッダーFrom)がなりすまされていないことを意味します。
マーケティング目的のメールや配信登録されたメールの場合には、ワンクリックで登録を解除できるようにするとともに、そのリンクをメールの本文中に分かりやすく表示する必要があります。
前述のように、Gmailアカウントにメールを送信するには送信ドメイン認証に対応する必要があります。
送信ドメイン認証にはSPF、DKIM、DMARCがあります。
SPFとDKIMは、それぞれIPアドレス及び電子署名を利用して、メールの送信元ドメインがなりすまされていないかを確認する仕組みです。
SPFあるいはDKIMを利用すれば送信元ドメインの詐称は見抜けます。
しかしながら、メールソフトやウェブブラウザーなどに表示される送信者アドレスは偽装できてしまいます。
近年の迷惑メールの多くは送信者アドレスを偽装します。
そこで開発されたのがDMARCです。
DMARCは送信ドメイン認証の1つとされるが、厳密には送信元のドメインは検証しません。
SPFやDKIMとの併用を前提としています。
DMARCは、SPFやDKIMの検証をパスした送信元ドメインとメールの送信者アドレスのドメインを照合し、これらが一致したメールのみパス(合格)とするのです。
つまり、DMARCを導入すれば、送信者アドレスのなりすましを見抜けます。
Googleの新しいガイドラインの主な目的は、大量のメールを送信する事業者/企業にDMARCを導入させることだといえるでしょう。
3種類の送信ドメイン認証のうち、国内普及率が最も高いのはSPFです。
総務省の情報通信白書(2023年版)によれば、2022年12月時点でのJPドメインにおけるSPFの普及率は77.2%だそうです。
導入が容易な上に「NTTドコモによる対応が普及を後押しした」(櫻庭シニアリサーチエンジニア)。
NTTドコモは2007年11月、携帯電話の迷惑メール対策の一環として、SPFによる検証機能を用意しました。
ユーザーがなりすましメールを拒否する設定にした場合、SPFに対応していないドメインからのメールは届かなくなりました。
このため企業やISPなどはSPFに対応し、普及率が向上したのです。
前出の情報通信白書によれば、2022年12月時点でDMARCの普及率はわずか2.7%です。
ところが、2023年以降、導入の機運は高まっています。
総務省と警察庁および経済産業省は2023年2月、「クレジットカード会社等に対するフィッシング対策強化の要請」を発表しました。
その中でクレジット会社に対してDMARCの導入を要請しています。
また、内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)が2023年7月に公開した「政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン(2023年度版)」でも、基本対策事項の1つとしてDMARCの導入を挙げています。
今回のGoogleのガイドラインが、さらに導入を後押しする可能性は高いでしょう。
「SPFのときと同じような普及率の向上が期待できる」(櫻庭シニアリサーチエンジニア)。
ただし、ガイドラインの要件を満たす最低限のハードルは、DMARCよりもDKIMのほうが高いです。
SPFとDMARCについては、DNSサーバーに特定の設定情報(TXTレコード)を追加すればガイドラインをクリアできます。
一方、DKIMはそれだけでは済みません。
送信するメールに電子署名を付与する仕組みが必要です。
自社でメールサーバーを運用している場合にはDKIM用のサーバーを用意します。
オープンソースソフトウエア(OSS)のサーバーソフトとしてはOpenDKIMが有名です。
クラウドメールサービスを利用している場合には、設定変更などが必要になります。
今回のガイドラインでは送信ドメイン認証が注目されますが、メールマガジンなどを配信している事業者や企業は、ワンクリック登録解除への対応も必須です。
メール中の目立つ場所にリンクを用意し、それをクリックするだけでメール配信の登録を解除できるようにする必要があります。
登録解除の申請ページに誘導するリンクや、登録解除のメールを送るようなリンクでは不十分です。
櫻庭シニアリサーチエンジニアによると、ワンクリック登録解除を用意していないメールマガジンは「とても多い」。
2024年2月1日以降、そういったメールマガジンはGmailユーザーに届かなくなる可能性が高いです。
ガイドラインにはワンクリック登録解除の実装方法が記されているため、該当する事業者や企業は参考にしましょう。
メールマガジンなどの送信をメール配信事業者に委託している企業は、その事業者の対応状況を確認する必要があります。
さもないと2024年2月1日以降、Gmailユーザーから「メールマガジンが届かない」といった苦情が押し寄せることになります。
世界中のメールユーザーに大きな影響を与えるであろう今回のガイドラインですが、特にメール配信事業者からの反発は必至です。
Googleとしても当然予想していたでしょう。
迷惑メール撲滅に注力するGoogleの覚悟のほどがうかがえます。
今回のガイドラインを機に、メールを利用している企業は送信量にかかわらず迷惑メールの対策状況、特に送信ドメイン認証の対応状況を確認すべきです。
今後、Googleに続けとばかりに、迷惑メール対策を強化するメールサービスが増える可能性が高いでしょう。
実際、アメリカのYahooはGoogleと同様の対策をすると公表しています。
送信ドメイン認証、特にDMARCに対応していないとメールを受け取ってもらえなくなる時代がすぐそこまで来ているのです。
僕もメルマガを配信したり、受信したりしていますが、対応しないといけないですね。
確かに、毎日、数え切れないほどの迷惑メールが送信されてきますので、Googleの対応を機に、迷惑メールが減れば良いなぁと思います。
Googleが迷惑メール対策を大幅強化しGmailに送れなくなる恐れがあることについて、あなたはどう思われましたか?
「若者集まる」高松中央商店街に大手チェーンが続々出店!
日本経済新聞によると、高松市の中心商店街に外食大手のサイゼリヤやディスカウント店「ドン・キホーテ」など、大手チェーンの新規出店が相次いでいるようです。
これまで香川県内の郊外の大型店舗やロードサイドへの出店が中心だでした。
アーケードの総延長の長さが日本一で、活性化の成功例とされてきた高松中央商店街ですが、新型コロナウイルス禍が落ち着いて若者の往来が戻りつつある機会をとらえ、大手チェーンが進出したかっこうです。
2023年11月下旬、高松中央商店街の中でも注目度が高い丸亀町商店街に、その複合型商業施設「丸亀町グリーン」でサイゼリヤの新店舗がオープンしました。
開業から1か月以上たった現在も、ランチの時間帯をはじめ多くの人でにぎわっています。
サイゼリヤは四国では香川県にしか店舗が無く、新店舗が香川県内4店舗目です。
高松市内では2店舗目となります。
丸亀町グリーンでは、2022年にマクドナルドの新店舗も開業しています。
丸亀町商店街では2023年8月、ディスカウント店「ドン・キホーテ」の新店舗がオープンしました。
ドン・キホーテも高松市郊外に店舗を構えていましたが、商店街を「再開発が進み注目が高まっている地域」(運営するパン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの担当者)と位置づけ、出店を決めたようです。
各社は商店街に若者が集まっていることに注目しています。
サイゼリヤは「多くの人が往来していることに加え、若い世代の方の比率が高い」と出店の背景を説明しています。
パン・パシフィックHDも「若い単身世帯の人や学生が楽しめる店舗づくりをしている」そうです。
2012年に開業した丸亀町グリーンは出店誘致の方針の一つとして「飲食メジャーブランドのエリア初出店による集客の強化」を掲げており、マクドナルドやサイゼリヤの誘致に成功しました。
2022年のマクドナルド出店により若者の客足が増えたといい、さらなる出店につながる好循環が生まれているようです。
高松丸亀町商店街振興組合の古川康造理事長は「大手チェーンばかりになるのはよくないが、来てくれるのは歓迎だ」と語っています。
実際にドン・キホーテの集客力が商店街の客足を押し上げている面もあるそうです。
高松市中心部に位置する中央商店街は「日本一長いアーケード商店街」として知られています。
丸亀町商店街など各商店街を合わせた全長は2.7キロメートルで、近隣にはオフィスに加え学校も多く、若者の往来が盛んです。
地方都市の商店街は郊外店舗に押されて活気が失われる地域が多い中で、中央商店街は空き店舗ができても新陳代謝が速く進んでいます。
高松市に見学に訪れる商店街関係者も多いです。
さらにアーケード商店街内ではマンションの建設が相次いでおり、にぎわいの場を持続させる要因になりそうです。
個人的には、チェーン店ばっかりできてと思っていましたが、やはり、集客力はあるんですね。
昔のトキワ街などのにぎわいを知っている人間からすると、現状、商店街を見るとさみしい気持ちになりますし、現在の丸亀町商店街も決して成功しているわけではないと思っていますが、少しでもにぎわいが戻るといいですね。
郊外のショッピングモールに人が集まっても、儲かるのは運営会社だけであまり地域活性化につながらないと思いますので、通勤している人、観光客、出張に来ている人、大学生、専門学生、高校生、何かの会合などで街中に来ている人などが、商店街を訪れてお金を使ってくれて、商店街が活性化すれば、高松市の活性化につながると思いますので、期待したいですね。
「若者集まる」高松中央商店街に大手チェーンが続々出店していることについて、あなたはどう思われましたか?
脱毛サロン大手「銀座カラー」の営業停止で「返金は?」などと戸惑い!
「返金はされるのか」。
毎日新聞によると、美容脱毛サロン大手「銀座カラー」の運営会社「エム・シーネットワークスジャパン」(東京都港区)が、2023年12月15日に破産手続き開始を公表したことを受け、利用者とみられる人たちはX(ツイッター)への投稿で不満と戸惑いをにじませています。
「会員の皆さまへ」と、毎日新聞の記者が12月16日昼過ぎに銀座本店(東京都中央区)が入るビルの階段を上ると、店舗に通じる扉にこう題した紙が張ってありました。
「16日以降、全店で営業を停止させていただきますので、会員の皆さまへの施術を行うことはできません」とあり、今後の会員への対応については、登録されているメールアドレスに送信し、破産管財人のホームページに掲載しているとしています。
銀座カラーのウェブサイトによると、過去には約40万円で全身脱毛の施術を何度も受けられる「通い放題プラン」や、約30万円で2年間有効な「脱毛し放題プラン」もあったが、最近は全身脱毛6回コース5万9,400円などがあったようです。
こうしたサービスなどに関し、Xには利用客とみられる人たちからの投稿が相次いだ。
<8年くらい前に永久会員? みたいなのになって、育児落ち着いたらまた通おうと思ってたのに! まだ期限も毛も残ってますけど!!>
<さっき急に倒産の連絡来た…最近、店舗の閉鎖が相次いでたからヤバいのかなって思ってたけど…ショックがでかすぎる>
<急に部分だけの施術になるし、おかしいなとは思ってた。次どこ通えばいいん? また新しく契約?>
<銀座カラー倒産? 40万のプランまだ途中ですけど…>
<脱毛行く準備しよと思って起きたら倒産!?今日まさに予約入れてるけど?? 脱毛し放題コースはどうなるん??>
「会員の皆さまへ」と題された紙には、上野保弁護士(東京第二弁護士会)が破産管財人となり、コールセンターが存在することが示されていました。
また、管財人ホームページを紹介しており、このページには、回数プランの未消化分のサービスは「一切受けられません」と記され、サービスを継承する会社も「現時点ではありません」としています。
また、未消化分のサービスに関する返金は「できません」と説明しており、クレジット会社や信販会社を通じたローン契約などは「クレジット会社などに直接お問い合わせください」としています。
過去にも結構あると思いますが、前払いのところとか、極端に安いところは危険ですね。
利用者も、きちんとお店を選ばないといけないですね。
お店の数が多いから安心とはいかないのが、なかなか難しいところですが。
美容とかダイエットはいつの時代も、ニーズがあるということでしょうから、引っかかる方も多くはなりますね。
脱毛サロン大手「銀座カラー」の営業停止で「返金は?」などと戸惑っていることについて、あなたはどう思われましたか?
世相を表す2023年の漢字は「税」!
NHKによると、ことし1年の世相を漢字ひと文字で表す「今年の漢字」が京都の清水寺で発表され、「税」の文字が選ばれました。
「今年の漢字」は京都市に本部がある「日本漢字能力検定協会」が、その年の世相を表す漢字ひと文字を一般から募集し、最も多かった字が選ばれています。
ことしは11月1日から12月6日までの14万7,878票の応募の中から、最も多い5,976票を集めた「税」の文字が選ばれました。
京都市東山区にある清水寺では午後2時すぎ、森清範貫主が大きな和紙に「税」の字を一気に書き上げました。
「税」が選ばれたのは、消費税率が引き上げられた2014年以来、2です。
「税」の字が選ばれた理由について協会は、1年を通して増税の議論が行われたことに加えて、所得税などの定額減税が話題にのぼったことのほか、インボイス制度の導入やふるさと納税のルールの厳格化など、「税」にまつわるさまざまな改正や検討が行われたことなどをあげています。
筆を執った清水寺の森清範 貫主は「税」が選ばれたことについて「国民がシビアに税の行方を見ている。税に対する意識が非常に強いことを改めて感じた」と話しました。
その上で「世の中は不穏な空気ばかりだが、来年こそは世界の人々が和むような『和』という字が選ばれることを願っている」と話していました。
「今年の漢字」に寄せられた文字は去年に続いて戦争を意識したものが目立った一方、野球に関連した明るいイメージのものも多く並んでいます。
「日本漢字能力検定協会」によりますと2番目は「暑」で、夏の平均気温が気象庁が統計を取り始めてから最も高くなったことを理由にあげています。
1番目の「税」との差は405票でした。
3番目は去年最も多かった「戦」でした。
12番目の「争」とともに2年連続でトップ20に入っていて、ロシアによるウクライナ侵攻や、イスラエル軍とイスラム組織ハマスの軍事衝突などの不安が続いていることを物語っています。
一方、野球のWBC=ワールド・ベースボール・クラシックで日本が優勝したことや、阪神タイガースがプロ野球で38年ぶりの日本一に輝いたこと、それに大リーグの大谷翔平選手の活躍を受けて、野球に関連した「虎」「勝」「球」「翔」「侍」が、トップ20に相次いでランクインしました。
「今年の漢字」は、京都市に本部がある「日本漢字能力検定協会」が1995年に始めました。
これまでの漢字を振り返ると、最も多く選ばれたのは「金」が4回です。
いずれもオリンピックが開催された年に選ばれています。
2番目に多かったのは、「災」と「戦」で2回でした。
気象や災害に関する漢字も多く、東日本大震災が発生した2011年には「絆」が、阪神・淡路大震災が発生した1995年には「震」が選ばれています。
このほか、暮らしや生活に関わる漢字では消費税が8%に引き上げられた2014年には「税」が、新型コロナウイルスの感染が拡大した2020年には「密」が選ばれています。
先日、長男から『ことしの漢字は「熱」だと思うけどどう思う?』と聞かれて、『同じことを思ったけど「暑」かな?』という会話をしましたが、『税』でしたね。
やはり2023年は10月1日から導入された消費税の『インボイス制度』に翻弄されましたし、税務調査とかで今までで圧倒的に『税務署』の方と会うことが多かったですね。
最近話題の『パーティー券』の問題も『脱税』ではないかと思っていますし、『税』で妙に納得もしました。
世相を表す2023年の漢字は「税」であったことについて、あなたはどう思われましたか?
事業再構築補助金の新規採択の停止を有識者が提言!
東京新聞によると、中央省庁の予算執行の無駄を有識者がチェックする「秋の行政事業レビュー」で、先日、新型コロナウイルス禍で打撃を受けた中小企業の事業転換を支援する「事業再構築補助金」の新規採択をいったん停止するべきだと有識者が提言したそうです。
所管する経済産業省が補助金の効果を検証していないことを問題視し、給付後の企業の状況を調べる仕組みの構築や給付審査の厳格化を求めました。
事業再構築補助金は中小企業の設備投資の費用などを補助する仕組みで、これまでに計7万6,224社が採択されました。
財務省によると、2023年9月末時点で、累計約2兆4千億円の予算を確保しました。
有識者の一人は、「いったん新規採択を停止すべきだ」と指摘しました。
この事業再構築補助金は、基本的に今までにやっていないことに新たにチャレンジする際の設備投資などを補助するというものなので、成功の確率は低いのでしょうが、詐欺的なものもおそらくあると推測されますので、効果を検証することは必要でしょうね。
金額も、中小企業が使える補助金の中ではずば抜けて多額ですから。
僕自身も、事業再構築補助金のお手伝いをさせていただいておりますが、(規模の小さな)中小企業の実態を分かっていない方々が制度設計をされていると思いますし、誰が補助金の恩恵をこうむっているのだろうかと疑問を感じたりもします。
事業再構築補助金の新規採択の停止を有識者が提言したことについて、あなたはどう思われましたか?
2022年の出生数は想定より11年早く初の80万人割れ!
日本経済新聞によると、厚生労働省は、先日、2022年の出生数が外国人を含む速報値で前年比5.1%減の79万9,728人だったと発表しました。
80万人割れは比較可能な1899年以降で初めてです。
国の推計より11年早くなっています。
出産期にあたる世代の減少に加え、新型コロナウイルスの感染拡大で結婚や妊娠・出産をためらう人が増えました。
若い世代の経済不安を和らげ、出産に前向きになれる社会に変える必要があります。
出生数は7年連続で過去最少を更新しました。
2022年の出生数は2019年の89.9万人より10万人少なくなっています。
出生数が最も多かった1949年の269.6万人に比べると、2022年は3割に満たないのです。
急速な出生減の主因はコロナ禍での結婚の減少です。
2019年に60万組を超えていた婚姻数が2020年に53.7万組、2021年に51.4万組に減り、2022年も51万9823組にとどまりました。
日本では結婚数がその後の出生数に直結する傾向があり、影響が色濃く出ました。
コロナ下の経済の混乱も妊娠・出産をためらう要因となりました。
行動制限などは和らいだものの出生数が反転する兆しは見えないようです。
2022年の出生数を月ごとに見ると12月は前年同月に比べて6.8%減っています。
減少率は4か月続けて拡大しています。
年間の減少率も2022年は5.1%で、2021年の3.4%減より大きくなっています。
人口の動きは日本経済の成長力や社会保障の持続性を左右します。
国立社会保障・人口問題研究所が2017年に公表した最新の推計では、基本的なシナリオとされる出生中位の場合に出生数が80万人を下回るのは2033年でした。
実際には11年も前倒しとなりました。
低位では2021年に77万人となって80万人を割る想定で、現状は最も悪いシナリオに近くなっています。
人口減も加速しています。
死亡数は8.9%増の158万2,033人で過去最多を更新しました。
新型コロナによる死亡が影響した可能性があります。
出生から死亡を引いた自然減も78万2,305人と過去最大です。
減少幅は2021年より17万人ほど広がりました。
今回の速報値は外国人による出産や死亡などを含んでいます。
日本人のみの出生数や合計特殊出生率は6月に公表予定です。
減少ペースをもとに、加藤勝信厚労相は2月に「77万人前後になるのではないか」との見方を示しています。
日本の社会保障制度は持続可能性を問われます。
高齢者自身の負担に加えて、現役世代が果たす役割が大きいためです。
年金や医療、介護など約130兆円の給付費の財源のうち、現役が多くを拠出する保険料は全体の半分以上を占めています。
出生が減れば、高齢者を支える将来世代が減ります。
保険料の引き上げなど一段の負担増が避けられなくなるでしょう。
欧米の多くの国はコロナ禍による出生減からすでに回復しています。
ドイツやフランス、ベルギーなど少子化対策が手厚い国は回復が早い傾向があります。
ドイツは2021年の出生数が二十数年ぶりの高水準になりました。
男性の育児参加など子育てしやすい環境作りに取り組んでいます。
フランスは多子世帯の税優遇や育児休業中の賃金保障などで支援しています。
岸田文雄首相は政権の最重要課題として次元の異なる少子化対策を掲げ、3月末をメドに具体策をまとます。
短期的には出産・育児への支援充実が欠かせません。
厚労省の調査によると、妻が35歳未満で理想の数の子どもを持たない夫婦の77.8%が「お金がかかりすぎる」ことを理由に挙げています。
京都大の柴田悠准教授は2023年2月20日の政府会議で児童手当の増額や学費の軽減、保育の定員拡大などが必要と訴えました。
即時に必要な政策に2025年ごろまでに年間6.1兆円規模を投じる必要があるそうです。
コロナの影響で、出会いや結婚が減っているのはあるのでしょうが、その辺を差し引いても、政府の少子化対策の失敗でしょう。
中国の人口が減少したというのも驚きましたが、11年も早いというのは日本の将来がすごく心配になりますね。
うちも子どもが2人いますが、お金は結構かかるなぁと普段から感じますし、一方で、昔はこども手当てや医療費の無償化はなかったでしょうから、自分の両親とかは結構大変だっただろうなぁとよく思います。
将来の日本を支える人達ですから、みんなで知恵を出し合って、安心して結婚や出産や子育てができる日本にしないといけないと本当に思いますね。
2022年の出生数は想定より11年早く初の80万人割れだったことについて、どう思われましたか?
金融庁が「エヌエヌ生命保険」に立ち入り検査へ!
エヌエヌ生命の関係者によると、8月19日までに検査予告があったそうです。
中小企業オーナーなどを対象にした「節税保険」の販売や商品開発の実態について、今後検査を進めるとみられます。
節税保険の不適切販売を巡っては、金融庁が2022年7月にマニュライフ生命保険に対して初の行政処分を下したばかりです。
販売行為の組織性や悪質性が生保各社の中でも際立っていたことでやり玉に挙がった格好でしたが、同じく節税保険販売における組織性などが強く疑われていたのがエヌエヌ生命でした。
そもそも同社は2022年2月、金融庁から保険業法に基づく報告徴求命令を受けており、逓増定期保険などを活用し、「租税回避行為」を指南する私製の資料が多数見つかったことをすでに報告しています。
今後の立ち入り検査の動向次第では、マニュライフ生命の事例と同様に、他社に転じたエヌエヌ生命の旧経営陣に対する責任追及に発展する可能性もあります。
保険の本質を忘れているような生命保険会社は処分されて当然かと思います。
僕自身も代理店をやっていますが、こういったことで色々なことが厳しくなっていきますので、勘弁して欲しいですね。
他社に転じた旧経営陣の責任もきちんと追求して欲しいと思います。
やってはいけないことをやって、多額の報酬を得たり、多額の報酬で他社に転じているのでしょうから。
金融庁が「エヌエヌ生命保険」に立ち入り検査することについて、どう思われましたか?
国税庁をかたる不審なメールにご注意!
TabisLandによると、国税庁をかたる不審なショートメッセージやメールから、国税庁ホームページになりすました偽のホームページに誘導する事例が見つかっているとして、国税庁が注意を呼びかけています。
情報によると、国税庁の名称や国税庁と類似した名称を使用した団体から、携帯電話等に「還付金を振り込む。」、「受取口座情報を返信してください。」などの内容のメールが届く事例が発生しているようです。
一例としては、「National Tax Agency(国税庁)」を名乗る者から、「You are eligible to receive a tax return of JPY~(~円の税金の払い戻しを受ける権利がある)」という旨のフィッシングメールが届き、メールに記載されたアドレス(https://www.nta.go.jp/~)をクリックすると、国税庁の偽サイト画面が表示され、本人確認と称して「Name(氏名)」「Date of birth(生年月日)」「16 digit debit card number(16桁のデビットカード番号)」等の個人情報を取得しようとする事例が発生しています。
国税庁(国税局、税務署を含む)からショートメッセージによる案内を送信することはなく、国税の納付を求める旨や、差押えの執行を予告する旨のショートメッセージやメールも送信していません。
国税庁からのメールによる案内は、国税庁ホームページ新着情報の配信サービスの登録をしている場合、国税庁メールマガジン配信サービスの登録をしている場合、e-Taxの利用にあたりメールアドレスを登録している場合に限って送信しています。
国税庁では、不審なショートメッセージやメールを受信した場合や、国税庁ホームページをかたるサイトを発見した場合には、アクセスすると被害を受けるおそれがあるためアクセスしないこと、また、国税庁ホームページを利用する際にはブラウザのアドレス欄(国税庁ホームページアドレスは、https://www.nta.go.jp/)を必ず確認するよう呼びかけています。
最近は、色々な不審メールがたくさん送られてきますね。
国税庁からメールが送られてくると、焦る方もおられると思いますので、そのあたりの心理状況もついているんでしょうね。
安易に、クリックとかしないようにしましょう。
国税庁をかたる不審なメールにご注意!について、どう思われましたか?
持続化給付金の不正受給が続々発覚し自主返還は166億円に!
朝日新聞によると、家族ぐるみで計約9億6千万円もの持続化給付金の不正受給にかかわったとして、住居不詳の男性(47)が詐欺容疑で指名手配され(インドネシアで逮捕)、男性の元妻と長男、次男が逮捕されました。
新型コロナウイルスの経済対策として導入された持続化給付金は、迅速な支給のため手続きが簡素化された半面、後に数多くの不正受給が発覚しています。
中小企業庁によると、要件を満たさなかったとして給付金の受給者が自主返還を申し出た件数は、2022年5月26日時点で約2万2千件です。
このうち約1万5千件についてはすでに返還があり、その総額は約166億円に上っています。
中小企業庁は、自主返還があった場合には警察への通報や被害相談はしていないそうです。
一方で、全国の警察による摘発も相次いでいます。
2021年3月、衆院議員事務所元スタッフの男ら4人が給付金100万円を詐取した疑いで愛知県警に逮捕されました。
セミナーを開いて「私ども自民党としましては、みなさんが持っていない情報を持っている」などと話し、不正受給を持ちかけていたとされます。
大阪国税局OBで元税理士の男も、身分を個人事業主と偽るなどして同じく4,500万円を詐取したとして2022年1月に有罪判決を受けました。
キャリア官僚の関与が明るみに出たこともありました。
経済産業省の元官僚2人はペーパーカンパニー2社の売り上げを偽造し、持続化給付金など計約1,550万円を詐取したとして2021年12月に東京地裁で有罪判決を受けました。
早く給付する必要はあったと思いますが、明るみに出ているところでこれだけの不正受給があったということは、制度がザルだったと言わざるを得ませんね。
このような給付金があったからこそ、犯罪者がたくさん生まれたわけですから。
中小企業庁にも反省してもらい、今後に活かしてほしいですね。
今回の事業復活支援金を見ると、改善されたところはありますが、支給されないケースもあり、ビジネスのことが分からない人たちが作っているんだろうなぁと感じる点がありますが。
持続化給付金の不正受給が続々発覚し自主返還は166億円にのぼったことについて、どう思われましたか?
国税職員ら20代男女7人が給付金詐欺で逮捕!
読売新聞によると、新型コロナウイルス対策の国の給付金をだまし取ったとして、警視庁が東京国税局職員(24)(神奈川県横浜市)ら20歳代の男女7人を詐欺容疑で逮捕しました。
7人は投資仲間で、名義人に不正受給させた約2億円の大半を暗号資産に投資していたといい、警視庁が金の行方を調べています。
ほかに逮捕されたのは、東京国税局職員と同期入庁だった東京国税局元職員の男(24)(詐欺罪で起訴)らです。
警視庁は2022年2月頃にアラブ首長国連邦(UAE)のドバイに出国した30歳代の男が中心メンバーだったとみて行方を追っています。
捜査関係者によると、7人は2020年8月頃、埼玉県に住む当時17歳の少年(詐欺容疑で書類送検)がコロナ禍で収入を減らした個人投資家だと偽り、中小企業庁から持続化給付金100万円をだまし取った疑いです。
東京国税局職員は黙秘していますが、一部のメンバーは容疑を認めています。
7人のうち東京国税局職員ら複数のメンバーがオンライン上の投資サロンに所属しています。
「給付金をビットコインに投資して2倍にする」などと言って知人らを勧誘し、約200件の不正受給を行わせたようです。
東京国税局職員と元国税職員は申請に必要な確定申告書の作成を担当し、1件当たり5万円の報酬を得たとみられます。
申請名義人は高校生や大学生など若者が多かったようです。
グループは給付金を全額回収し、メンバーの報酬を差し引いた残りの大半を暗号資産に投資しましたが、その後、元金などは名義人に返還されていないそうです。
名義人の一人が2020年8月頃、警視庁に不正受給を申告し、警視庁が捜査していました。
持続化給付金の不正受給を巡っては、2020年12月にも東京国税局の甲府税務署員が逮捕され、詐欺罪などで有罪判決を受けています。
最近は国税庁職員の不祥事も目につきますね。
こういう人たちがいる組織に税務調査などはできるのでしょうか?
報酬を申告しているのかも気になりますが、国税局もご多分に漏れず人がなかなか採用できないのかもしれませんが、採用時にきちんと適性を確かめ、採用後も全職員を対象にモラルなど研修が必要なのでないかと思います。
本当に、持続化給付金は、期限内に申告している人のみを対象にして、過去何年間かの納税額を給付額のMAXにした方が良かったのではないかと改めて思います。
簡単に申請できたことが、逮捕者がたくさん出る状況を生み出しているわけですので。
国税職員ら20代男女7人が給付金詐欺で逮捕されたことについて、どう思われましたか?
事業復活支援金の申請期限及び事前確認期限が延長!
2022年5月31日火曜日までとされていた事業復活支援金の申請期限が、6月17日金曜日まで延長されました。
なお、申請前に必要な「登録確認機関による事前確認」の実施は6月14日火曜日までとなります。
ただし、申請や事前確認のために必要な「申請IDの発行」は5月31日火曜日までとなりますので、ご注意ください。
申請をお考えの事業者の方は、お早めに申請IDを発行していただき、必要書類を準備し、登録確認機関での事前確認を受けたうえで、申請をしてくださいね。
事業復活支援金では、申請を行う前に事務局が募集・登録した「登録確認機関」において、①事業を実施しているか、②給付対象等を正しく理解しているか等の事前確認を受けていただく必要があります。
事前確認を受ける際には「申請ID」を登録確認機関に掲示する必要があります。
事前確認を受ける前に本ホームページにて仮登録(申請ID発番)を行ってください。
なお、コールセンターでも仮登録(申請ID発番)を受け付けておりますので、ホームページのご利用が難しい方は、コールセンターまでお問い合わせください。
いったん期限を決めたのであれば、きちんと守って欲しいですね。
弊事務所も登録確認機関となっていますが、何かと時間はかかりますし、確定申告や3月決算で忙しい時期に大変ですので。
ちなみに、弊事務所は顧問先の事前確認しかやっていませんので、これ以上やりませんが。
事業復活支援金の申請期限及び事前確認期限が延長になったことについて、どう思われましたか?
高校で「金融教育」が始動したことで金融各社が教材開発に注力!
日本経済新聞によると、学習指導要領の改訂で2022年4月1日から高校で本格的な金融教育が始まったのを受け、金融各社が教材開発や教員育成に本腰を入れているようです。
若い時から日々の家計の管理や金融商品の知識をつけることで金融リテラシーの向上を狙う施策です。
証券会社などが培ってきたノウハウを提供し、国全体で「豊かさ」を追求する動きが手探りで始まっているようです。
新学習指導要領では、家庭科の中で預貯金や株式・債券などの基本的な金融商品の特徴、資産形成の視点も教えることとされました。
新たに必修科目となった「公共」の授業でも、金融の役割を学びます。
こちらは企業の資金調達のしくみなどお金がどのように社会の中で動いているかという観点が中心になります。
20年以上金融教育に注力してきた野村ホールディングスの出張講座は、小学生から大学生、学校の教員まで延べ約91万人が受講しました。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、学校支援の「教育と探求社」(東京都千代田区)と組み、人生とお金について考える教材を中高生向けに開発し、2023年度から提供します。
さいたま市教育委員会と金融経済教育に関する連携協定を結んでおり、2022年度は小学生向けに同市に加えて東京都や京都府など複数地域で授業を提供する予定です。
三井住友フィナンシャルグループ(FG)でも傘下のSMBC日興証券やSMBCコンシューマーファイナンスが協力してグループ共通で使える教材を開発しています。
投機と投資の違いや長期投資のポイントなどを解説する出張授業のプログラムを、この春から始めます。
金融教育の流れは資産運用会社にも広がります。
ニッセイアセットマネジメントはタカラトミーと金沢工業大学と組み、SDGs(持続可能な開発目標)に特化した教育用の「人生ゲーム」を制作しています。
8月以降、全国の小学校で展開する計画です。
ニッセイアセットはESG(環境・社会・企業統治)運用の実績を生かして、ESGをテーマにした盤面の開発を担いました。
教員にとっては慣れないテーマで、授業の方法も確立されていないため授業時間を割くハードルは高くなっています。
みずほ証券は、早稲田大学と共同で投資教育を担える教員養成の研究を実施しています。
大学院との研究の一環で、中高生向けの教材作成を取り入れています。
証券会社などにとっては教育活動は大きな収益源にはなりませんが、国民の資産形成への意識を高める活動として注力し始めているようです。
投資ではなく貯蓄が好きな日本人が多いため、貯蓄から投資へのシフトを図るためには、金融教育も必要なことだと思います。
投資をすることで、潜在的な先を含め投資先の企業にも興味を持つと思いますし、企業の活動にも興味を持つでしょうから。
しかしながら、個人的には、物価が上がる中で給与が上がらない日本の現状を考えると、稼ぐ(経営)ということも学んだ方が良いのではないかと思います。
稼がないと運用に回す資金もないわけですから、まずは稼がないと始まらないわけですから。
また、日本の将来に不安があって、投資ではなく貯蓄に回してしまう方も多いでしょうから、みんなが稼げる日本を作っていけば、当然、投資をするようになるのではないかと思います。
この『稼ぐ』ということを学ぶためには、『戦略マネジメント・ゲーム』がふさわしいのではないかと改めて感じた記事でした。
高校で「金融教育」が始動したことで金融各社が教材開発に注力していることについて、どう思われましたか?
給付金搾取で逮捕された経済産業省のキャリア官僚は慶應義塾高校の同級生!
朝日新聞によると、経済産業省のキャリア官僚2人がコロナ禍の影響を受けた中小企業を支援する家賃支援給付金を詐取したとして逮捕された事件で、2人が「相談して2人でやった」などと容疑を認める供述をしていることが、先日、捜査関係者への取材でわかったようです。
1人は「警察の捜査を免れるために職場で証拠隠滅の相談をした」といった趣旨の話もしているそうです。
警視庁は関係者に事情を聴くなどして裏付けをする方針です。
逮捕されたのは、経済産業省産業資金課係長(28)と産業組織課職員(28)の両容疑者です。
2人は慶應義塾高校の同級生だそうです。
警視庁捜査2課によると、2人は共謀して2020年12月、コロナ禍で収入が減った中小企業を装い、給付金を専用サイトから申請しました。
2021年1月に約550万円を詐取した疑いがあります。
申請には、職員が入省前の2019年に設立し、社長を親族に引き継いだとみられるペーパーカンパニーを使い、売り上げ台帳などを偽造した可能性が高いそうです。
捜査関係者によると、2人はいずれも容疑を認め、「2人でやった」「2人で相談した」などと供述しているようです。
また、2人のうち1人は「警察の捜査を察知した」といった趣旨の説明もし、「職場で申請に使ったデータの消去方法などについて話し合った」などと話しているそうです。
警視庁捜査2課は、経済産業省の防犯カメラの映像を分析するなどして、裏付け捜査をする考えです。
一方、係長は世界有数の高級時計メーカーの腕時計や複数のブランド品をクレジットカードで買っていたことが、捜査関係者への取材でわかっています。
警視庁は、給付金の大半を係長が受け取っていたとみており、支払いに充てた可能性があるとみています。
また、自宅マンションの1か月の賃料は国家公務員としての給与額を超えていたほか、複数の外車にも乗っていたといい、収入源や生活実態を調べているようです。
他の報道などによると、2人は暗号資産(仮想通貨)の世界で有名とか、株取引で稼いでいたとか、持続化給付金200万円なども受け取っていたようですが、1人はメガバンク出身、もう一人は司法試験合格者とのことであり、慶應義塾高校を出ているくらいですからそれなりの裕福な家庭に育った方だと思われますので、なぜ給付金を管轄する経済産業省に属する優秀な方が、このようなことをするのだろうか理解できません。
こういう給付金などの詐欺事件を目にするたびに、何度もこのBLOGでも書いていますが、コロナ前の期限内申告を要件とすべきだったと思ってしまいますね。
給付金搾取で逮捕された経済産業省のキャリア官僚は慶應義塾高校の同級生だったことについて、どう思われましたか?
東北新社の総務省接待問題で総務省の調査漏れの会食が複数あった!
讀賣新聞によると、総務省幹部への接待問題を巡り、放送関連会社「東北新社」が設置した特別調査委員会が、総務省の調査で公表されていない複数の接待を確認したことが、先日、東北新社関係者への取材でわかったようです。
総務省側も報告を受けており、接待が放送行政に影響を与えていないか調査しているようです。
東北新社は、問題の経緯をまとめた特別調査委員会の報告書を2021年5月24日に公表する予定です。
関係者によると、東北新社が2017年、認可を担当する衛星・地域放送課長(当時)を接待していたことが新たに判明しました。
東北新社が衛星放送事業に関する外資規制違反を認識した時期です。
会食と近い時期に、この課長に野球観戦チケットも渡していたそうです。
当時の課長は、先日、読売新聞の取材に「(会食の有無は)答えられない」と述べました。
東北新社は2017年1月、「BS4K放送」事業の認定を受けました。
その後、外資比率が20%以上と放送法違反の状態であると認識し、違反を解消するため、総務省の認定を受けたうえで2017年10月に子会社に事業承継しました。
この過程で総務省と東北新社でどのようなやり取りがあったかが焦点となっています。
総務省は2021年2月、東北新社側と延べ38回会食したとの内部調査を公表しました。
当時の総務審議官ら11人を処分しています。
総務省の調査がいい加減ということでしょうね。
きちんと、説明責任を果たしてもらいたいと思います。
そもそも、放送法違反の状況を、子会社に事業譲渡することで解消が認められるのであれば、放送法の存在意義はあるのだろうかと思ってしまいます。
おそらく、この会社に限らず、接待をしている会社はたくさんあるでしょうから、総務省を解体して、不正が起こらないような許認可の仕組みを作ってほしいと思います。
そして、接待を受けた側も、懲戒解雇(退職金なし)くらいにして欲しいですね。
東北新社の総務省接待問題で総務省の調査漏れの会食が複数あったことについて、どう思われましたか?
離婚発表のビル・ゲイツ氏がメリンダさんに1,980億円相当の株式を譲渡!
日刊スポーツによると、先日、離婚を発表したアメリカのマイクロソフトの共同創設者で慈善活動家のビル・ゲイツ氏(65)が、27年間連れ添った妻のメリンダさん(56)にすでに18億ドル(1,980億円)相当の株式を譲渡していたことが明らかになったようです。
芸能情報サイトのE!ニュースやアメリカの経済誌フォーブスが報じました。
フォーブスは推定1,304億ドルと言われるビル・ゲイツ氏の保有資産は、わずかに減少して1,286億ドルになったと伝えています。
アメリカ証券取引委員会(SEC)に提出した書類によると、ビル・ゲイツ氏の投資会社カスケード・インベストメント社が離婚を発表した日にカナダ国内最大の鉄道会社カナディアン・ナショナル鉄道の株式約1,400万株と自動車ディーラーのオートネーション社の株式290万株をメリンダさんに譲渡していたそうです。
一方、ウォールストリート・ジャーナル紙は、他にもコカ・コーラなども含め24億ドル相当の株式を譲渡したと伝えています。
1994年に結婚した2人は、「人生の次の段階において夫婦としては共に成長できるとは考えられなくなった」と理由を明かして離婚することをツイッターで発表しました。
共同で2000年に創設したビル・アンド・メリンダ財団については今後も共に活動を続けていくことを表明していますが、財産分与に関しては婚前契約を結んでいなかったことが明らかになっています。
メリンダさんが裁判所に提出した離婚申請の書類によると、離婚前に巨額の資産の分割方法について別離契約書を作成しており、それに基づいて資産を分割することが記されていたことから、今回の株式譲渡は離婚による資産分与の一環であることは間違いないとみられています。
別離契約の内容は明らかにされていないことから、今回明らかにされた株式譲渡以外にも非公開の取引で資産の一部をメリンダさんに譲渡している可能性もあるとフォーブス誌は伝えています。
税理士の中には節税目的では?という方もいるようですが、それはさておき、保有資産が1,286億ドルというのは想像もつかない数値ですね。
マイクロソフトの功績の表れでしょうが、使いきれないでしょうし、税金対策も大変だろうなぁと思います。
どういう方が顧問税理士なのかにすごく興味があります。
離婚発表のビル・ゲイツ氏がメリンダさんに1,980億円相当の株式を譲渡したことについて、どう思われましたか?
「あなたと同姓の富豪が死んだ」との周到な「ドバイ詐欺」相次ぐ!
毎日新聞によると、オイルマネーの流れ込む中東屈指の金融センターや林立する超高層ビルなど、アラブ首長国連邦(UAE)のドバイが持つ華やかなイメージを利用した「ドバイ詐欺」が全国で相次いでいるようです。
在ドバイ総領事館によると、2019年~2020年と21年3月までの邦人被害額は、少なくとも計約7,800万円に上ります。
未遂に終わったものの約50億円を要求されたケースもあり、1件当たりの最高被害額は2,500万円です。
奈良県では、60代の男性が約830万円をだまし取られる被害が発生しています。
在ドバイ総領事館が国内外の邦人に向けて、ホームページで注意を呼びかける事態となっています。
「私はドバイに住んでいます」。
2018年冬ごろ、60代男性のSNS「インスタグラム」アカウントに1通のメッセージが届いたそうです。
差出人は、国際的に有名な銀行の取締役だという男で、この男性は外国の友人を増やしたいとの思いもあり、SNS上の友人になりました。
「ドバイの富豪が大いなる遺産を残して死んだ。偶然にもあなたと同じ姓だ」。
メッセージのやり取りを始めてから約2か月後、突然こう告げられました。
詳しい話を聞くと、共に事業を進めていた親しいドバイの富豪が亡くなり、遺産相続人を探していると言いました。
「同じ姓のあなたは関係があるのではないか?」
男性には心当たりがあったそうです。
以前、親戚から外国人の身内がいると聞かされたことがあったからです。
「ひょっとすると……」。
どうすればよいか尋ねると、「銀行の顧問弁護士」を紹介されました。
「遺産相続の法的手続きを取るための着手金が必要です」。
その弁護士にメールで連絡を取ると、初めて金銭を要求されました。
高額だったこともあり一度は断ったそうですが、しばらくして男から「着手金は私が払う。遺産を相続してほしい」とのメッセージが届きました。
弁護士からもメッセージが届きました。
「裁判所に書類を提出し、遺産相続が認められた。金額は1億500万ドルだ」
「相続人」となった男性の元には、弁護士から次々と関係書類がメールで送られてきました。
富豪の死亡届に国際通貨基金(IMF)の資金証明書など精巧に作り込まれた十数通の書類をメールで受け取るうち、男性は完全に男たちを信用するようになっていました。
着手金を肩代わりしてもらった「恩義」もあり、泥沼にはまり込むようでした。
証明書取得のための手数料や巨額送金をするための銀行員への賄賂など、男性は、弁護士から次々と出される指示を受け、日本やトルコの銀行口座に計約830万円を送金しました。
「遺産を相続したら、一緒に事業をやろう」という話も持ちかけられましたが、いつまでたっても男性の口座には肝心の遺産が振り込まれないため、「だまされたのではないか?」と思い始めた時には、男とも弁護士とも連絡が取れなくなっていました。
奈良県警郡山署などは、2021年2月、送金先とされた銀行口座を管理していた外国籍の50代男性を詐欺容疑などで逮捕しましたが、容疑不十分で不起訴となりました。
奈良県警は引き続き、男の周辺捜査を進めています。
在ドバイ総領事館によると、ドバイで見られる詐欺は、①金融機関をかたる詐欺、②王族、政府機関をかたる詐欺、③高利商取引を持ちかける詐欺、④王族や紛争地域に在住する軍人や医師らとのロマンス詐欺の4類型が多いようです。
2021年1月からは、総領事館に寄せられた相談事案などをまとめた注意喚起文書をホームページに掲載し、類型ごとの特徴を詳しく紹介し、詐欺被害に遭わないためのポイントを解説しています。
総領事館の関口昇総領事(54)は「王族の存在や日本の生活にはないきらびやかさなどドバイのイメージが詐欺に使われ、被害が生じていることは非常に残念だ」と話し、「ドバイ政府自身が観光や経済のイメージを積極的に発信していることもあって、荒唐無稽な話を信じ込んでしまうのだろう。おいしい話が入ってきたら、一度相手と接触を絶ち、周りの人に相談して」と注意を呼びかけています。
ドバイというイメージを使うのは巧みだとは思いますが、やはり、目の前にお金がちらつくと、簡単に騙されてしまう方がいらっしゃるんですね。
少し冷静になって、周りの方や弁護士さんに早めに相談しましょう。
「あなたと同姓の富豪が死んだ」との周到な「ドバイ詐欺」相次いでいることについて、どう思われましたか?
詐欺と大麻で逮捕の「甲府税務署職員」の父親は東京国税局の「エース」職員!
新型コロナウイルス禍を受けて、2019年2月半ばから9月末まで原則として税務調査を見合わせていた国税当局ですが、調査は10月から再開されたものの、相手側にウイルス感染させる可能性を排除できないとして、強制権限を持つ査察部(マルサ)を除けば、必ず相手側の同意を事前に得るよう、例年以上に徹底されているそうです。
このため調査の対象も自ずと限定されることになり、現場はストレスのたまる毎日が続いているようです。
また、確定申告期限の延長により、確定申告期限の終了までは、新規の案件に着手できないことになっており、事実上、当事務年度(6月末まで)の新規の案件の着手は事実上できないと言えるでしょう。
その国税当局を震撼させる一大不祥事が、2020年12月2日に山梨県で起きました。
東京国税局甲府税務署に勤務する26歳の男性職員が、新型コロナ禍対策として国から支給される持続化給付金100万円をだまし取った疑いで愛知県警に逮捕され、自宅から乾燥大麻が押収されたのです。
ただでさえ思い通りに調査できない日々の中で起きた前代未聞の事件に、東京・築地の東京国税局は重苦しい空気に包まれたようです。
ただ、デイリー新潮によると、この事件が国税当局に衝撃を与えた本当の理由は、実は別のところにあるそうです。
国税関係者が「東京国税局の今後の人事構想や調査方針に悪影響が出かねない」と表情を曇らせる、その理由とは何なのでしょうか?
まず、今回の事件の内容を振り返っておきます。
甲府税務署の資産課税第2部門に所属する調査官(26)は、愛知大学生の男性2人(起訴済み)と共謀して2020年5月下旬、愛知県内に住む20代の男子学生を個人事業主(美容業)と偽り、2020年4月の事業収入が前年同月比で大幅に減少したとする虚偽の内容を中小企業庁に申請しました。
2020年6月2日に申請者の口座に給付金100万円を振り込ませた詐欺の疑いで、愛知県警に逮捕されました。
国税職員だった調査官は、給付金申請の際に添付する確定申告書の偽造を担当し、2020年9月に愛知大学生2人が逮捕・起訴された後の捜査で関与が浮上しました。
2020年12月24日には、この愛知大学生1人の不正請求にも関わった疑いで再逮捕されました。
自宅から押収された資料からは虚偽の確定申告書を約250件作成していたことが判明したそうです。
また、愛知県警が2020年12月2日朝に調査官の自宅を詐欺容疑で家宅捜索した際、乾燥大麻や吸引用具が発見され、同容疑者はその場にいた埼玉県川越市の無職男(25)と自称フィリピン国籍の男(24)とともに大麻取締法違反容疑で緊急逮捕されました。
起訴済みの愛知大学生のうち1人は、大麻取締法違反罪でも起訴されています。
調査官は都内の私立大学を卒業後、2016年に国税専門官として東京国税局に採用され、杉並署など東京都内の複数の税務署を経て、2019年7月に甲府署に異動となり、相続税などの調査を担当する資産課税第2部門に勤務していました。
東京国税局元幹部は「杉並署から甲府署への異動は、将来有望と目される若手職員が歩むルートとされています。その有望株がよりによって持続化給付金の詐欺に加えて、薬物絡みの事件まで起こすなど前代未聞。セクハラやパワハラなど比較にならない、言語道断の行いです」と憤っているようです。
調査官の逮捕を受けて、東京国税局は西川健士総務部長名で「職務外の行為とはいえ、職員が逮捕される事態は公務に対する信頼を著しく損なうもので遺憾。事実関係を確認し、厳正に対処する」とコメントしましたが、公式の謝罪会見は調査官の起訴を待って行われるようです。
国税職員としてどころか、社会人として当たり前のモラルさえ持ち合わせていなかった調査官ですが、大学卒業後5年目の社会人とはいいながら、いったいどんな家庭教育を受けてきたのか、それこそ親の顔が見てみたいものです。
前出の国税関係者が声を潜めて話したようです。
「実は両親とも国税局の現役職員なんです。特に50代半ばの父親は、甲府署で息子も配属された資産課税畑の専門家。東京国税局の中枢を担うノンキャリのエースの一人としてここ数年、局内の重要ポストを次々と歴任しました。その点からも、今回の事件はまさに痛恨事。エースの一人である父親の将来に禍根を残したと断罪されています」
ここ数年間の父親のキャリアを遡ると、資産課税課筆頭課長補佐→浜松西税務副署長(名古屋国税局への出向)→東京派遣国税庁監察官→調査第1部特別国税調査官(特官)→査察部査察第10部門統括査察官と1、2年で異動を繰り返し、現在は今事務年度に新設された課税第1部統括国税実査官(富裕層担当)を務めています。
これがどれほどピカピカの経歴なのか、国税OB税理士が解説しています。
「他局の大規模署の副署長、東京局職員の不正を捜査する監察官、超大法人を調査する特官、マルサの情報部門(通称ナサケ)の統括官と、重要ポストを短期間に幅広く経験させてもらっています。ナサケ第10部門は、マルサ未経験の幹部候補が希望して着任する、いわば“お客様ポスト”。画に描いたような出世コースで、課長以上の幹部就任に向けた階段を、猛スピードで駆け上っている感じです。その中でも期待度の高さを示すのが、初代として就任した富裕層統轄実査官(統実官)のポストでしょう」
統実官とは、縦割りの組織の弊害を打破して調査の精度や効率を上げる狙いから、東京局では所得税と資産税を担当する課税第1部に7つ、資本金1億円未満の法人税と消費税、酒税を担当する課税第2部に1つ設置されている重要ポストです。
中でも今事務年度から新設された東京局課税第1部の富裕層統実官は、新型コロナ禍で任意の税務調査を思うように進められない国税当局の“打ち出の小槌”として、期待度大なのです。
「税務調査の“米櫃”的な存在の飲食店やパチンコ店などの現金商売業者に対しては例年、無予告調査が多用されますが、新型コロナ禍の今事務年度はその手がおいそれとは使えません。一方で海外の税務当局との情報交換制度であるCRS(共通報告基準)が軌道に乗り、日本人富裕層が海外に所有する資産の監視体制は急速に整備されています。
2019事務年度の富裕層に対する追徴税額は前年度に比べて約28%増の259億円と過去最多を記録しており、今事務年度もCRSの効果は大いに期待できます。それに知的レベルの高い納税者が大半の富裕層は、こちらが不正蓄財の証拠さえ明示すれば調査に協力的で、効率も上がります」(国税庁幹部)
その富裕層を専門的に調査する新たなポストを与えられたのが、他ならぬ調査の父親だったのです。
結果を残せて当然のお誂え向きのポストが、資産課税畑のエースに用意されたというわけです。
前出の国税OB税理士が話しています。
「自身が起こした不祥事ではないものの、国税職員になった息子への教育の責任を問われる事態は避けられないでしょう。少なくとも、これまでのような出世街道を歩むことはもう難しいのでは。今後の東京局内の人事構想や調査方針に及ぼす悪影響は必至です」
今回の息子の不祥事を受けて、国税関係者の間では、父親が重責の富裕層統実官を適切に遂行できるのか危ぶむ声が出るなど、動揺が広がっているそうです。
事の重大性は、世間が考える以上に深刻のようです。
税務当局は、パートの方も職員のご家族を採用していると聞きますし、閉ざされた世界だと思いますが、親の力で採用され、エリートコースを歩んでいるのではないかと推測されますが、別人格とはゆえ、親にも責任はあるのではないかと思われる1件ですよね。
国民の脱税とかを防ぐ立場にある人が、国からお金だまし取っているわけですから。
銀行の職員の横領などもそうですが、やはり、『資質』というものが大事であり、『資質』は親の教育などにも影響を受けるのではないかと思います。
この事件に限ることではありませんが、最近、その職業や資格を目指した時の夢や希望をすっかり忘れて事件を起こしているケースが多いのではないかと感じています。
自分への戒めもありますが、時には、初心を思い出すことがとても重要ですね。
そこは、会社員の方も、クレドを見て経営企業などの理念に立ち返るということと同じかと思います。
詐欺と大麻で逮捕の「甲府税務署職員」の父親は東京国税局の「エース」職員であることについて、どう思われましたか?
クラウド会計のfreeeの顧客情報2,800件が漏えいの恐れ!
日本経済新聞によると、クラウド会計ソフト大手のフリーで、クレジットカード番号を含む約2,800件の顧客情報が漏えいした恐れがあることが、先日わかったようです。
フリーが使う外部のクラウドシステムのセキュリティー設定に不備があり、第三者がアクセスできる状態でした。
実際に情報が閲覧されたり、悪用されたりした被害は確認していないそうです。
情報漏洩の恐れがあるのは、顧客からのアカウント設定や支払い方法に関する問い合わせフォームの内容です。
外部からアクセス可能だった約2,800件の大半は顧客のメールアドレスでしたが、問い合わせの際に記載されていた氏名、住所、電話番号に加え、銀行口座やクレジットカードの番号、会計ソフトにログインするためのIDとパスワードも含まれていました。
フリーが展開する会計ソフトなどの自社サービスから顧客情報は流出していません。
フリーが情報管理に使っていたのは、企業向けソフトウエア大手であるアメリカのセールスフォース・ドットコムのクラウドシステムとみられます。
フリーが、先日、外部のセキュリティー関係者から情報提供を受け社内調査したところ、同日までの約1年間、第三者が情報にアクセスできる状態が続いていました。
すでに外部からアクセスできないように閲覧権限の設定を変更したそうです。
セールスフォースのクラウドシステムを巡っては、導入企業である楽天のほか、ソフトバンク傘下のスマートフォン決済大手PayPay(ペイペイ)などでも、設定ミスによって加盟店や個人の顧客情報が漏洩した疑いが明らかになっています。
これを受け、セールスフォースは導入企業に対し、アクセス権限の設定を確認するよう注意を呼びかけています。
フリーは2013年にクラウド会計ソフトのサービスを始めた国内の先駆けです。
登録した銀行口座やクレジットカードなどの明細を自動取得し、帳簿を作成できるソフトを手がけています。
経理業務の専門知識がなくても手軽に使える利便性を売りに、個人事業主や中小企業を中心に直近の有料会員は23万件に上ります。
2019年12月、東証マザーズに上場しました。
最近、情報漏えいのニュースを見ると、セールスフォースのクラウドシステムを使っているところばかりですね。
きちんと説明などがされているのかわかりませんが、これだけの大手が設定をみすしているわけですから、セールスフォース側にも原因はあるんでしょうね。
おそらく、信頼も失っているでしょう。
いずれにしても、丸投げではなく、きちんと管理していかないと痛い目にあいますね。
クラウド会計のfreeeの顧客情報2,800件が漏えいの恐れがあることについて、どう思われましたか?
持続化給付金詐欺事件で元税理士の親族ら9人も書類送検!
毎日新聞によると、大阪国税局OBの元税理士が新型コロナウイルスに伴う国の持続化給付金をだまし取った詐欺事件で、大阪府警東淀川署は、先日、逮捕された元税理士(43)=詐欺罪で公判中=の親族や事務所スタッフら20~70代の男女9人を詐欺の疑いで書類送検したと発表しました。
名義貸しや虚偽申請を手伝っていたとみられ、東淀川署は事務所ぐるみで不正に手を染めていたとみて全容解明を進めています。
書類送検されたのは、元税理士が代表を務める税理士事務所(閉鎖)のスタッフ5人と元税理士の親族4人の合わせて9人です。
容疑は、2020年5月から6月に、元税理士と共謀して個人事業主と偽ったり、うその売り上げを提出したりして給付金計1,500万円をだまし取ったとされます。
東淀川署などによると、元税理士は2020年4月に中小企業庁から給付金の申請手続きが公表された時に、開業届の提出が必ずしも求められていないことに着目しました。
申請が殺到して調査が追いつかない上に、規模の小さい零細事業者を装えば、営業実態の把握が困難になるだろうと考えて虚偽申請を計画したようです。
申請が始まった5月からスタッフや親族、顧問先に名義貸しを持ち掛け、成功報酬を受け取っていました。
スタッフは役割分担して申請業務を進めていました。
元税理士の事務所が申請した給付金の総額は計4億3,700万円で、このうち約1億円分を不正受給したとみられます。
元税理士は論外でしょうが、税理士事務所のスタッフもおかしいと思う人がいなかったのでしょうか?
おそらく、法人ではなく個人事業主でしょうが、1億円分は不正受給だとしても、4億3,700万円分申請するというのはスゴイですね。
それだけクライアントがあれば、そんなにせこいことをしなくても、他に稼ぐ方法はあるように推測されますが、なぜ、こんなことに手を染めたんでしょうね。
気のせいかもしれませんが、問題を起こす税理士は国税局OBが多いように思いますが、モラルが低いんでしょうか?
国税局OBが税理士登録できるという制度もそろそろ見直す時期に来ているのではないでしょうか?
給付金詐欺容疑の慶応大学生は「起業の金欲しかった」!
サンケイスポーツによると、新型コロナウイルス対策の持続化給付金をだまし取ったとして、島根県警に詐欺容疑で逮捕された慶応大学4年生(22)が「起業のためにお金が欲しかった」と動機を供述していることが、先日、捜査関係者への取材で分かったようです。
関係者によると、慶応大学生はプロ野球の監督を務めた方の孫で、慶応大学野球部で捕手として活動していました。
慶応大学生は、受給対象でない松江市の男子大学生に給付金を申請するよう指南し、2020年7月に中小企業庁から100万円を大学生の口座に振り込ませて詐取した疑いで、島根県警松江署に2020年1月26日に逮捕されました。
島根県警松江署によると容疑を認めているようです。
捜査関係者によると、慶応大学生は知人らに会員制交流サイト(SNS)で不正申請を促し、関与した給付金の不正受給額は計1,000万円以上とみられます。
受給者はそれぞれ数十万円を慶応大学生に「アドバイス料」として渡した疑いがあります。
お金に困っている企業や個人事業主に早めにお金を渡すということを優先したのでしょうが、これだけ、大学生や税務署職員や税理士やそれ以外の方が逮捕されているところを見ると、制度の設計がザルだったということでしょうね。
個人的には、当初から、過年度の期限内の確定申告や2019年の開業の開業届の募集要項公表までの提出は条件に入れるべきだったと考えています。
そうすれば、不正受給はかなり防げたと思いますし、開業届の提出や確定申告をきちんとしておかないといけないという国民の意識の向上、正直者が得をするということにつながったのではないかと思います。
給付金詐欺容疑の慶応大学生は「起業の金欲しかった」とコメントしていることについて、どう思われましたか?
Clubhouseの利用規約が早くも有名無実化!
Business Journalによると、音声SNS「Clubhouse(クラブハウス)」が大流行中です。
まだiOS版のみでAndroid版が出ていないものの、連日メディアを賑わせる人気ぶりとなっています。
現状は芸能人などが大量に参入しており、ここだけの話が聞けることでも人気となっています。
ある40代男性は、入浴中もトイレ中も使い続け、「クラブハウスに住んでいる状態」だそうです。
「憧れの漫画家さんと直接話せて夢のよう。すべてClubhouseのおかげ」。
一方、眠っている間に貴重な話を聞き逃すのが怖くて、ほとんど眠れなくなってしまったのだそうです。
あまりの人気から、Facebookでも対抗となる音声SNSを開発中と報道されています。
Twitterでも2020年末より「Spaces」という音声チャットルームのβテストを開始しており、音声SNSへの注目は当分続きそうです。
一方、Clubhouseにはさまざまな問題点が指摘されています。
改めて3つの大きな問題について紹介されています。
<データの取扱いは不透明、セキュリティリスクは高い>
Clubhouseではじめから指摘されていたのは、セキュリティ上の問題です。
「セキュリティ的に考えると怖くてできない」という人も少なくなく、利用していても「セキュリティは心配だけれど利用したいから仕方がない」という人もいるようです。
2021年2月、ドイツのハンブルクのデータ保護当局は、同アプリの個人情報の扱いを問題視する文書を公表しています。
「運営会社がルーム内の全ての会話を録音・保存している」と指摘すると同時に、個人情報の収集方法にも問題があるとしています。
ユーザーが誰かを招待する際はスマホの連絡先データを全てアプリ側に渡す必要があり、運営会社はサービスの利用者以外の個人情報も得ますが、データ管理や削除方法については不透明のままです。
このようなデータは、知らぬ間に第三者に利用される可能性もあります。
さらに、アメリカのスタンフォード大学の調査によると、同アプリのデータの一部に中国企業がアクセスできる可能性があるそうです。
同アプリにAPIを提供している上海のソフトウェアプロバイダーAgora社に、ユーザーのIDとチャットルームのIDを送信しているというのです。
つまり、Agora社を経由すれば、誰がどのチャットルームにいたかがわかってしまうというわけです。
さらに、アカウントも一度つくったら簡単には削除できない点も問題です。
削除ボタンがあるわけではなく、アカウント削除や無効を希望する場合にはメールアドレスを登録の上、support@joinclubhouse.comに削除申請を送る必要があります。
しかも、申請が受理されるまでに時間がかかるという声もあがっています。
<出会い系利用や情報ビジネスの温床にも>
Clubhouseで興味があるテーマのルームに参加すると新しい出会いにつながることがあるようです。
これは楽しい経験だそうですが、一方で諸刃の剣にもなりえます。
あるルームで初めて会った同士が、「明日会おう」と言っていたそうです。
つまり、すでに出会い系に使われているということです。
以下で述べるとおり、未成年も多く参加しており、音声でのやり取りが残らない以上、出会い系被害につながっても証拠も残らない可能性があるのです。
すでに誹謗中傷や差別発言などが見られるだけでなく、情報ビジネスや宗教関係とも相性が良いといわれています。
海外ではすでに情報ビジネスの温床となっているようです。
他のSNSではフォロワーがそれほど多くないのに同アプリ内ではフォロワーを多く集め、「一般人が○日でフォロワー☓☓人になったコツ」などとルームを立てて語っているのを見かけることもあるようです。
話が上手い人が活躍できるSNSですが、逆に話術によって騙されるリスクも出てくるので注意が必要です。
<18歳以下も多く、録音録画される例も>
Clubhouseには利用規約があるが、規約はまったく守られていないようです。
たとえば18歳以上対象とされていますが、年齢確認などの仕組みはなく誰でも利用可能です。
「高校生(17)」「高校生、17歳です」「15歳の中学生です」「中学生、13歳です」などというユーザーが多数見つかる状態です。
なんと「8歳の小学生がいた」という声もあがっています。
大人が18歳以下のユーザーをフォローしたり、話しかけることもできます。
実際、「高校生と話せた」と喜んでいる40代男性もいるようです。
前述のように出会い系にも使われていることを考えると、リスクが高いことは言うまでもありません。
同アプリは、規約で会話の録音や記録を禁じています。
ところが、藤田ニコルさんが話していた内容が週刊誌の記事となってしまい、規約が守られていないことが明らかになりました。
また、YouTubeなどで検索すると、同アプリでの芸能人などの会話が録音・録画された例が多数見つかる状態です。
「規約で禁止されていても、アカウント停止になる程度。スクープがとれるなら自分でもやると思う」とある記者は言っているようです。
フォロワーを増やすために相互フォローを目的としたいわゆる「フォロー部屋」も禁止されています。
ところが、フォロー部屋を名乗るルームは頻繁に立ち上がっており、こちらも特に罰則などもないようです。
規約が有名無実化しているのが現実です。
この他にも、電話番号を使った招待制のため、思わぬ問題も起きているようです。
SNSでつながる今の時代、電話帳に登録されているのは友だちとは限らず、最新の人間関係を反映させたものではなくなっています。
「友だちの多い本名も知らないキャバクラ嬢に招待されてしまった」とか、「縁を切ったはずの元カレや絶交した元友人が表示されて気分が悪い」という話も聞きます。
その他、アーカイブが残らないリアルタイムで聞かねばならないサービスのため、時間を食ってしまい睡眠不足になっている人もいます。
問題を中心に述べてきたが、Clubhouseが楽しいものであることは確かなようです。
このサービスが向いている人にとっては、コロナ禍でもリアルコミュニケーションできる貴重な場であり、新しい出会いにつながる場でもあるのでしょう。
すでにビジネスに活用している人も出てきています。
なかには、ルームでのトークで数十万円の物販につながったという人もいるようです。
ただし、「特に承諾のないまま商業目的で商品またはサービスの売買を広告しまたは販売すること」は規約で禁止されており、注意が必要でしょう。
新しいサービスが、はじめから問題がないということはまずありません。
リスクもありますが、可能性も秘めていることは間違いありません。
リスクに気をつけながら使ってみるのはいいかもしれません。
当初からFacebookなどで招待してとか書かれている方がたくさんいたので、知ってはいたのですが、Androidユーザーなので、僕自身はやっていません(できません)。
自分にはあまり向かないだろうなぁと思っています。
セキュリティについては、昨年、セキュリティに問題があると言われたZoomがセキュリティの改善などをしてあれほど流行った(定着した?)わけですから、Clubhouseも徐々に改善はしていくことでしょう。
Clubhouseの利用規約が早くも有名無実化であることについて、どう思われましたか?
国税局OBの元税理士が約100人に持続化給付金の不正受給を指南か?
新型コロナウイルスの影響で収入が減った個人事業主らを支援する国の持続化給付金をだまし取ったとして、大阪府警東淀川署は、先日、大阪国税局OBの元税理士(43)と、税理士事務所の事務員だった30歳代の男を詐欺容疑で逮捕したことが、捜査関係者への取材でわかったようです。
大阪府警東淀川署は、大阪国税局OBの元税理士が顧問先企業の従業員ら約100人に不正受給を指南したとみており、被害総額は約1億円に上る可能性があるそうです。
捜査関係者によると、大阪国税局OBの元税理士は2020年6月、代表を務める大阪市内の税理士事務所(2020年11月に閉鎖)で、当時事務員の男と共謀し、顧問先の会社に勤める男性(20歳代)を個人事業主と偽った2019年分の確定申告書などの書類を準備し、新型コロナウイルスの影響で収入が減ったように装って、中小企業庁の専用サイトから持続化給付金を申請し、男性の口座に100万円を振り込ませ、詐取した疑いです。
大阪国税局OBの元税理士は手数料名目で数十万円を受け取ったといい、大阪府警東淀川署は男性からも任意で事情を聞くようです。
大阪国税局OBの元税理士らは、手数料を稼ぐ目的で顧問先企業の社員やその家族らに次々と不正受給を持ちかけ、応じた人に対して給付金の申請手続きに必要な身分証の写真や通帳のコピーをメールなどで送信するよう指示し、事務所内で、うその収入などを記した確定申告を電子申請し、虚偽の書類を入手していたとみられます。
大阪国税局OBの元税理士は、2015年に大阪国税局を退職し、税理士事務所を開業しました。
不動産オーナー向けに節税方法を指南する書籍を出版し、税務調査への対応方法を解説するセミナーなどで講師も務めていましたが、2020年9月に入ってから日本税理士会連合会に登録抹消届を提出し、9月29日付で受理されています。
ちなみに、持続化給付金は、コロナ禍で、月の売上高が前年同月比50%以上減った事業者などを対象に、中小企業は200万円、個人事業主やフリーランスは100万円を上限に支給するものです。
2020年11月23日時点で約380万件、約5兆円を給付しているそうです。
申請は2021年1月15日までです。
なぜ、この大阪国税局OBの元税理士が、このようなことをするのか、同業者として理解できません。
よほどお金に困っていたのでしょうか?
国税局OBはモラルがないのでしょうか?
こういう人が、業界の信用を失墜させるので、本当に勘弁してほしいですね。
国税局OBの元税理士が約100人に持続化給付金の不正受給を指南していたことについて、どう思われましたか?
持続化給付金詐欺の疑いの税務署職員は100件以上のうその確定申告書を作成か?
東京国税局甲府税務署の職員が、新型コロナウイルスで影響を受けた事業者に支給される、国の持続化給付金をだまし取ったとして逮捕された事件で、職員がこれまでに100件以上のうその確定申告書を作成していたとみられることが分かったようです。
警察は職員がうその申告書を作成した見返りに、報酬を得ていたとみて調べを進めています。
東京国税局甲府税務署の職員(26)は、2020年6月、国の持続化給付金をめぐり、受給対象ではない大学生を申請者にして、事業収入が大幅に減ったという、うその確定申告書を作成し、100万円をだまし取ったとして詐欺の疑いで逮捕され、先日、検察庁に送られました。
警察が東京国税局甲府税務署の職員の携帯電話に残された、やり取りなどを解析したところ、これまでに100件以上のうその確定申告書を作成していたとみられることが分かりました。
すでに逮捕・起訴されている愛知大学の学生2人の捜査の過程で、東京国税局甲府税務署の職員が確定申告書の作成に関わっていたことが分かりましたが、学生2人との面識はなく、間をとりもった人物がいるとみられるということです。
警察はうその申告書を作成した見返りに、報酬を得ていたとみて調べを進めています。
こういう人が税務署の職員というのは驚きです。
報道によると、資産税の担当だったようですが、こういう人に税務調査とかでとやかく言ってほしくないですよね。
資質の問題かとは思われますが、税務署も、教育とかがきちんとできていないということなのでしょうね。この件だけではないのですが、これ以外にも税務署の職員の不祥事は起こっていますので、税務調査がやりにくくなるでしょうね。
持続化給付金詐欺の疑いの税務署職員が100件以上のうその確定申告書を作成していたことについて、どう思われましたか?
持続化給付金の詐取容疑で国立印刷局職員2人を逮捕!
新型コロナウイルスの影響で経営に打撃を受けた個人事業主などに国が支給する持続化給付金をだまし取ったとして、警視庁捜査2課は、先日、詐欺容疑でいずれも国立印刷局職員の21歳の容疑者と20歳の容疑者を逮捕しました。
警視庁捜査2課によると、2人は容疑を認めているようです。
持続化給付金詐取事件で国家公務員が逮捕されるのは初だそうです。
警視庁捜査2課によると、21歳の容疑者が指南役だったとみられ、「身分証を出せばお金がもらえる」などと20歳の容疑者に不正受給を持ちかけたそうです。
職場の同世代の同僚や、会員制交流サイト(SNS)で計数十人を勧誘し不正受給を指南したそうで、実際に受給したケースもあるとみられます。
逮捕容疑は2020年6月ごろ、それぞれ個人事業主と偽り、虚偽の確定申告書の写しや売り上げ台帳を中小企業庁所管の事務局に提出し、同給付金計200万円を詐取したとしています。
事件をめぐっては、SNSを通じて21歳の容疑者に不正受給を指南した人物がいた可能性もあり、警視庁捜査2課は全容解明を進める方針だそうです。
すぐに支給できるよう制度設計が簡単すぎたのが原因だとは感じますが、とある税理士の方が言っているように、税務調査ができなかったので、持続化給付金の事務局を税務署の職員が手伝ったら良かったのではないかと思います。
また、持続化給付金のために今まで申告をしていなかったのに過去の申告をした人をどんどん税務調査してほしいと思います。
何度かこのBLOGでも書いていますが、本当に、過去から事業をしている人は2018年度などの期限内申告、2019年に開業した人は持続化給付金の公表までの開業届の提出などを要件にしておけば良かったのにと感じます。
持続化給付金の詐取容疑で国立印刷局職員2人が逮捕されたことについて、どう思われましたか?
摘発を恐れる持続化給付金の不正受給者の返金希望が殺到し返金手続きが一部停止!
共同通信によると、新型コロナ対策で個人事業主らに支給される持続化給付金を巡り、警察の摘発などを恐れる不正受給者から返還希望が殺到していることを受け、国が返金手続きの一部を7月から停止していることが、先日、中小企業庁への取材で分かったようです。
希望自体は受け付けていますが、誰からの返金かを明確にするため個別に受付口座を準備中で、振り込みを待たせている状態が続いているようです。
2020年10月下旬ごろをめどに返金の方法を郵送で案内する方針だそうです。
当初はいずれの受給者に対しても同じ口座に振り込ませていたようですが、名義の入力を誤るケースが続出し、7月はさらに希望者が増え、返金方法を見直したそうです。
返金すれば良いのだろうかという気はしますね。
確か当初の想定だと、1件当たりの事務費が4、5万円くらい想定されていたと思いますので、その分も返してもらわないといけないように思いますね。
最初に申請要項を見たときにこれで大丈夫なのだろうか?(抜け穴がいくつでもあるのでは?)と思うくらい要件等を簡単にしすぎたので、不正も横行したという感じですね。
その当たりは、制度設計の段階である程度は分かっていたのではないのかと思いますが。
摘発を恐れる持続化給付金の不正受給者の返金希望が殺到し返金手続きが一部停止していることについて、どう思われましたか?
加速する三井物産の印鑑レスだがそれでも残る「岩盤」!
日本経済新聞によると、新型コロナウイルスの感染拡大の結果、在宅勤務によるテレワークが当たり前になり、様々な局面で接触を減らす努力がなされるようになりました。
変化を余儀なくされる中で浮かび上がってきたのは、デジタルを使いこなせていない日本の姿です。
押印のための出勤など、デジタル化を真剣に進めていれば、容易に解決できた問題もたくさんあります。
多くの日本企業も、コロナ禍を契機にデジタル化をもう一歩進めようとしています。
新本社の本格稼働を機に「印鑑レス」を加速している三井物産の事例が紹介されています。
コロナ禍は、机に置かれた決裁箱から印鑑待ちのりん議書の山を取り出し、次々とはんこを押していくという日本のオフィスのこのような日常を変えられるのでしょうか?
2020年6月に東京都千代田区大手町の新本社を本格移動させた三井物産が「印鑑レス」を加速させています。
電子署名サービス大手のアメリカのドキュサインのサービスを全社に導入しました。
新型コロナウイルスの脅威がまだ広がっていなかった2月と比較すると、6月の利用数は10倍以上になっています。
新本社は、社員一人ひとりに割り当てられた席がありません。
執務席は本社で働く4,500人に対し7割しか用意されておらず、社員には高さ約50センチのロッカーが割り当てられただけです。
その日、仕事をする席は、その日ごとに選ぶフリーアドレス制なのです。
新オフィスは社内外の活発な交流を期待しての仕掛けなのですが、大量の書類を持ち歩いて座席を探していては、かえって効率が落ちます。
新本社の移転前にペーパーレスをなじませる必要があると、2019年11月にドキュサインを使い始めました。
世界で50万社以上が利用し、最大手とされます。
クラウドに契約書やりん議書などの書類データをアップし、関係者はクラウド上で承認(署名)します。
社員が書いたりん議を上長が承認すると、さらに役員へ通知が行くといった具合にワークフローが可視化されています。
自分が提出した書類の決裁がどこまで進んでいるか不安になることもありません。
三井物産には、はんこ待ちの紙は「インボックス」、はんこを押した後は「アウトボックス」という箱に入れる慣習があるそうですが、新本社移転によりかなり廃れたようです。
はんこレスの習慣をさらに加速させたのが、新型コロナです。
ドキュサインの利用数は2019年11月が66、12月は306と、そろりと滑り出しましたが、2020年3月は2,364と、2月の651の3倍超に急伸しています。
4月は5,940、5月が6,491と増え続け、6月以降は7,000を超えています。
赤石理・企画法務室室長補佐は、「1~2月は取引先にドキュサインに移行したいと申し出るのを面倒がる雰囲気があったが、コロナで一気に変わった」と話しています。
ある社員は「ドキュサイン導入後、りん議の文章直しに伴う再提出が減った。紙で回ってくると上司は、『てにをは』を直したくなるが、デジタルだと突き返すのをためらうようだ」と笑っています。
導入前に多かった疑問は「法務的に通用するかどうか」でした。
総合商社は、取引先が世界にまたがるため、「この国も使えるか」「紙を使わなければならない分野はあるか」など実用面での不安を解消する必要がありました。
このため国際的な法律事務所や現地法人の法務担当の協力を得て、主要取引国上位約30か国を調査しました。
10数か国でドキュサインが利用できると判断し、紙の契約を前提にした内規を変更しました。
グループ会社も含めて10回以上の説明会を開き、日本の法律に必要なカスタマイズを行い、準備に1年かけました。
安永竜夫社長は就任直後に取締役会資料を電子化するなど率先してペーパーレス化を進めていたため、社内への浸透も速かったようです。
現場からの意見で、韓国やカナダなどに対象国を広げたり、通関用の書類に適用したりと改善を進めました。
デジタル総合戦略部の下田幸大氏は、「デジタル、法務、財務部門が三位一体になって進められた」と語っています。
三井物産で急速に浸透するペーパーレスですが、「岩盤」が残っているようです。
ドキュサインは、対外的な契約書だけでなく、りん議書や月報、報告書など社内の書類にも使われています。
社外と交わしている紙の売買契約書は年5万件程度で、ドキュサインの利用数月7,000のうち8割が社内、2割が社外となっており、社外文書の電子化率は3割程度となっているようです。
取引先にドキュサインの利用を依頼すると、「ITの会社でも、『契約に関するルール変更を取締役会にかけなければならない』と返答がくる」(下田氏)そうです。
ドキュサインを利用する際は、三井物産がライセンスを持っていれば取引先は不要だが、契約書にまつわる内規という壁は高いようです。
同じ反応はグループ会社からも出たそうです。
もっと硬い岩盤は、「行政」です。
ドキュサインの利用が加速した4月以降も、法務部の社員は「社印」を押すために交代で出勤したようです。
例えば、農薬や劇物などの化学品関係で農林水産省などに提出する報告書は、「営業担当から『どうしてもはんこが必要です』と要望があった」(赤石氏)ようです。
外国政府に提出する書類の作成や商業登記の変更、トラックや乗用車の所有名義の変更など、総合商社の業務は多岐にわたるので仕方がない面はあるにしても、多くが行政向けです。
緊急事態宣言時は、曜日や時間を限定して社印が必要な書類を受け付けたそうです。
財務担当も頭を悩ませています。
税務調査では、電子帳簿保存法が求める「検索機能の確保」に対応が必要ですが、ハードルが高く十分に進められていないようです。
同法は、「取引年月日、勘定科目、取引金額その他のその帳簿の種類に応じた主要な記録項目を検索条件として設定」でき、「日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定」できることなどを求めているほか、訂正や削除履歴が確認できることも必要とされています。
契約書だけでなく、領収書、請求書、業務委託に関する書類、委任状など文書の種類ごとに要件を備えるコストが高く、三井物産はさしあたり契約書だけ対応しました。
紙からデジタルになるなら、「より便利に使えるべきだ」という「ディマンディング(過剰要求)現象」がデジタル化を阻んでいる一例です。
2019年10月、三井住友フィナンシャルグループ(FG)は、電子契約サービスを手掛ける弁護士ドットコムと合弁会社、SMBCクラウドサイン(東京都港区)を設立しました。
契約書をクラウドにアップし、「いつ」「誰」が契約を承認したかを、電子署名と暗号技術を用いて改ざんできないように記録する「立会人型」と呼ばれるサービスで、ドキュサインと同じタイプです。
銀行の取引網を通じて、売り込んでいます。
4月の緊急事態宣言を受けて、外資系とIT系企業がこぞって導入しています。
導入期間は約2か月から、2週間から3週間に縮まりました。
利用者数は1.5倍に増え、契約送信数は10倍になりました。
大手企業も6月頃から動き出しました。
緊急事態宣言で業務がストップし、電子契約の必要性を体感して「本腰を上げ始めた」(SMBCクラウドサインの三嶋英城社長)ようです。
コロナ以降、「電子契約はNO」と安易に断ってはいけない雰囲気が高まっているそうです。
三井住友FGが、電子契約サービスに参入したのは、銀行の信用力が生かせるリーガルテックに狙いを定めたと同時に、銀行こそが印鑑に縛られている業種だからです。
銀行に届け出た印鑑と異なる印鑑を書類に押してしまった「印鑑相違」は、利用者、銀行の双方にとって大きなストレスです。
三嶋社長は、「『レガシー企業』の代表格である銀行が取り組むことに意義がある」と話しています。
メガバンクや総合商社という日本を代表する企業が日本をデジタル先進国へと導こうとしています。
僕も数年前に、印紙税を削減できるということで電子契約について調べた時期があり、少し前から、取引先から電子契約や電子サインを求められるケースが出てきています。
うちの事務所もそろそろ電子契約にしようかなぁと思っていたところなので、コロナがきっかけで進めやすい環境にはなってきたなぁとは思っているところです。
大企業がどんどん進めてくれれば、中小企業もせざるをえなくなり、世間一般的に行われるようになることを期待したいと思います。
あとは、普段は政治に期待はしていませんが(笑)、行政のはんこをなくそうとしている河野太郎行政改革大臣には期待しています。
加速する三井物産の印鑑レスだがそれでも残る「岩盤」について、どう思われましたか?
持続化給付金を大学生グループが不正受給か?
東京新聞によると、新型コロナウイルスで収入が半減した個人事業主や中小企業への持続化給付金を、関東地方の大学生のグループが不正受給していた疑いがあることが、関係者への取材で分かったようです。
迅速な支給のため手続きが簡素化されている点につけ込んだとみられます。
友人の誘いで不正受給に加担した大学生は警察の摘発を恐れ、被害弁済の手続きを始めたそうです。
関係者によると、「持続化給付金が簡単に手に入る。君たちも申請すればもらえるからやってくれないか」と4月下旬に、関東地方に住む20代の大学生に、友人の他大学の男子学生から会員制交流サイト(SNS)でそんなメッセージが届いたそうです。
友人は他にも首都圏の学生を十数人集め、インターネットのビデオ会議システムを使って受け取り方法を指南しました。
「確定申告の書類を作れるやつがいるから、大丈夫」「あとは(その書類を)近くの税務署に出すだけ」などと説明しました。
大学生が住所や銀行口座などの個人情報を指南役の友人に知らせると、税務署に申請する書類がPDFファイルで送られてきたようです。
大学生は前年度、収入がありませんでしたが、個人事業主として確定申告するよう言われ、収入があったと偽って最寄りの税務署で確定申告を済ませ、ネットで持続化給付金の受給を申請しました。
5月中旬、口座に100万円近い給付金が振り込まれ、当初の約束通り、大半を友人に渡しました。
後日、犯罪行為に当たると知り、国民生活センターや弁護士に相談したようです。
大学生は現在、持続化給付金事務局のコールセンターを通じて被害弁済の手続きを進め、警察への自首も検討しているそうです。
周囲には「友人を信じ切っていた。申し訳ない」と話しています。
事務局のコールセンターには、こうした弁済に関する相談が相次いで寄せられているようです。
不正受給が発覚すると、詐欺罪に問われる可能性があるほか、支給額に年3%の延滞金を加えた額に20%の加算金を上乗せして返金する必要があります。
制度を所管する中小企業庁の担当者は、「不正が疑われる事案は警察と情報を共有している。逃げ得は許さない、というスタンスでやっていく。給付金の原資は税金。不正受給をしてしまったなら、まずは返金し、警察の捜査に協力してほしい」と話しています。
<持続化給付金>
新型コロナウイルスの影響を受けた個人、中小企業が対象で、今年1月以降に前年同月比で事業収入が50%以上減った月があることなどが条件です。
支給額は個人事業主が最大100万円、中小企業は同200万円です。
迅速な支給のため手続きは簡素化され、申請はインターネットで今年の収入を自己申告で記載し、確定申告書などの写しを添付します。
申請期間は2021年1月15日までで、経済産業省によると、8月5日現在で、293万件、3兆8,150億円が支給済みだそうです。
持続化給付金の不正受給を巡っては、実際に若者の逮捕者も出ています。
山梨県警は、7月22日、100万円を詐取したとして、詐欺の疑いで埼玉県内の男子大学生(19)を逮捕しました。
捜査関係者は「容疑者は普通の大学生」と話しています。
ツイッターなどのSNS上には不正受給を誘う書き込みが相次いでいます。
多くは「給付金案件」「申請代行」といった投稿で不特定多数を勧誘し、これまで犯罪に手を染めたことのない若者らが、軽い気持ちで応じていることがうかがえます。
各地の消費生活センターには5月下旬以降、20~30代からの不審な勧誘に関する相談が増加しています。
中小企業庁の担当者も「不正受給が疑われる情報はたくさん入ってきている」と明かしています。
山梨県警の事件が報道された後、詐欺の発覚を恐れたのか、返金の申し出が増えたそうです。
警察当局も今回の大学生グループとは別に、組織的な不正受給に関する情報を把握しており、詐欺容疑で捜査する方針だそうです。
警察庁幹部は「被害弁済が済んでいれば、それを加味して対応する」と話す一方、「組織的詐欺の指南役には厳しく対処したい」と強調しています。
制度設計に不備があったと言われればそれまでかもしれませんが、迅速に対応するためにはある程度はシンプルな設計で仕方なかったとは思います。
もちろん、不正受給は言うまでもなくアウトですが、個人的には、2018年と2019年の確定申告をしているとか、2018年は期限内申告をしているとか、マイナンバーを使うなどのやり方はあったのではないかと今でも思っています。
あまり深く考えずに応じている大学生が多いのかもしれませんが、自分できちんと判断するようにしないといけないですね。
持続化給付金を大学生グループが不正受給していた疑いがあることについて、どう思われましたか?
国家公務員に昨年の夏より多いボーナスの支給!
管理職を除く一般行政職(平均35歳)の支給額は平均680,100円です。
昨年までの民間企業の賃金アップを踏まえ、昨夏より1,000円多く、8年連続プラスとなりました。安倍晋三首相は404万円、閣僚は337万円でした。
一般行政職は支給平均年齢が0.5歳若くなり減額要因となった一方、昨年の人事院勧告に基づき、支給月数が0.025か月引き上げられ、月給の2.22か月分に増加し、結果として支給額は増加しました。支給額トップは最高裁長官の577万円(前年同期比8万円増)です。
衆参両院の議長は535万円(同8万円増)で、国会議員319万円(同5万円増)、中央省庁の事務次官328万円(同5万円増)となりました。首相ら特別職は平成24年から、行財政改革に取り組む姿勢を示すため、首相が支給額の30%、閣僚が20%を自主返納しています。
内閣人事局の試算によると、返納後の金額は首相404万円(昨年同期比6万円増)、閣僚337万円(同5万円増)となりました。新型コロナウイルス感染拡大による経済への影響から、今年度の通常国会では「内閣、国会議員は特権的待遇と国民は見ている」(4月27日の参院本会議、鈴木宗男参院議員)などとボーナス返上を求める声も上がっていました。
これに対し首相は「国会での議論を踏まえつつ、適切に判断する」(同)と答えていました。
時効を教えず町が勝訴し14年間分の水道料金を請求!
朝日新聞によると、長野県富士見町が、住民の男性(82)に水道料金徴収の時効を大きく超える14年前からの滞納分と延滞金計約607万円の支払いを求めて提訴し、その主張を認める長野地裁諏訪支部(手塚隆成裁判官)の判決が確定したことが分かったようです。
提訴時の水道料金の時効は2年でしたが、時効の成立には債務者側がそれを主張する必要がありました。
行政絡みの訴訟に詳しい弁護士は「住民に有利になることは行政側が教えるべきだ。地方自治体は一般企業とは違う」と、町の対応を疑問視しています。
町が男性を提訴したのは2018年夏でした。
町は弁護士を代理人にし、男性は「お金がなかったので」と弁護士を雇いませんでした。
提訴を知るとほぼ同時に自宅隣で営む製造会社が倒産状態になっていました。
県地方税滞納整理機構から同社への発注元に、支払代金の差し押さえが通告されたのです。
半月後に税金は支払ったものの、発注は消えました。
男性は「町県民税は分割で払い続けていたのに」と話しています。
その後は生活するだけでやっとの状態が続いているようです。
判決が言い渡されたのは翌2019年11月21日です。
支払いを命じられた606万8,892円の内訳は、2004年3月~2018年4月の水道料金約335万円と延滞金約271万円でした。
町は2020年3月13日に男性への給水を停止しました。
4月7日、長野地裁諏訪支部が自宅とその敷地一帯の強制競売開始を決定しました。
公債権の税金と違い、水道料は私債権として民法が適用されます。
時効は公債権の原則5年に対し、2年(2020年4月の新民法施行からは5年)です。
ただし、債務者側が主張(「時効の援用」と呼ぶ)しなければ時効が有効とはならないのです。
提訴を前に、町は「債権がある限り請求しない理由はない」(上下水道課)として、滞納が始まった14年前からの水道料金と延滞金を請求しました。
時効は男性に知らせないことにしたようです。
同課は「裁判で時効の援用をされると想定したが、それがなかった」と明かしています。
男性の方は「時効なんて全く知らなかった」と説明しています。
控訴をしなかったため、判決が確定しました。
直後、町は提訴後(2018年5月以降)の水道料金も請求しました。
2019年12月までの約28万円を、男性側は2020年1月末までに支払っています。
行政関係の訴訟を数多く手がけた岡谷市の松村文夫弁護士は、富士見町のやり方に「違和感を感じる」と話しています。
「地方自治の目的は住民福祉の増進」としたうえで、町が時効を教えなかったことを「配慮が足りなかった」と指摘しています。
「特に、(弁護士を付けない)本人訴訟ですから。時効を教えなかったのはよくないと思う」と、延滞金の利率が14・6%と高いことにも疑問を呈しています。
裁判では町が男性に支払いを促す面談をしていないことも明らかになりましたが、判決は「面接をして任意の納付を促す義務があるとはいえない」としたのです。
強制競売に先立ち、同支部の執行官が男性宅を訪れ、家屋や自宅敷地、会社敷地の現況調査をしています。
時効だけでなく延滞金にも疑問の声が出ています。
町は延滞金徴収条例に基づいて利率14・6%の延滞金(民法では遅延損害金)を請求し、認められました。
これに関し、行政実例に詳しい全国町村会法務支援室は「14・6%は高い。普通は旧民法にある法定利率の5%だ」と話しています。
半面、一般論として「市町村が条例で(延滞金の利率を)定めていればそちらが適用される」とも指摘しています。
ただし、それは私債権を対象とした条例がある場合のようです。
又坂常人・信州大名誉教授(行政法)は富士見町の延滞金徴収条例を読み込んだ上で、「この条例は(税金などの)公債権を対象としている」と結論づけています。
又坂氏によると、同条例は地方自治法第231条の3が規定する延滞料について定めている▽同条は公債権について定めたもので私債権には適用されないという解釈が一般的であり、多くの自治体でもそのように運用されている▽私債権について条例に規定がない以上、(提訴当時の)民法を適用して法定利率の5%で再計算しなければいけない―と指摘しています。
又坂氏は「間違った債権額で強制執行が行われると、国家賠償請求を起こされる可能性もある」と話しています。
長野県諏訪市役所3階にある諏訪湖記者クラブですが、室内の掲示板に男性が数枚の紙を貼ったのは3月半ばでした。
手書きの文面には「焼身自殺」の文字があったようです。
自宅を訪ねると、男性は「先祖の墓の前で焼身自殺するつもりだった」と話し始めたそうです。
「家族に迷惑をかけたらだめだから、女房とは離婚した。子どもとも縁を切った」
自宅には仏壇があり、壁には家族の写真や標語などがたくさん掲げてあります。
幼少期に一家で満蒙開拓団に加わったため、それにかかわる記念の品もあるようです。
男性は、53年前から自宅の隣でアルミ鋳造の会社を営んできました。
取引先を失った後も細々と仕事を続けていましたが、給水停止で不可能になりました。
「溶かしたアルミを入れる金型と鋳造機械を冷やすために水がいるんです」
町とは約20年前、自宅隣のマンホールポンプ場をめぐって裁判になりました。
水道料金を滞納し始めたのはそのさなかです。
「東京の弁護士を雇ったので弁護士代がかさんでしまって……」
税金や電気代の支払いを優先し、水道料金は後回しにしてきたと話しています。
「町はいろんなトラブルを棚に上げて水道料金だけ『これでもか』ってやってくる。先祖代々の土地と汗水垂らして建てた家をこんなことで取られるなんて」と悔しさをにじませました。
こういう間違ったやり方が原因で、もし自殺などで尊い命が失われると、どうするんでしょうね。
固定資産税の計算を間違っていた場合は、時効を主張して、過去の分を市町村は支払わないのに、逆の立場になると、黙っておくんですね。
やはり税金もそうですが、知らないと損をすることが世の中にはたくさんありますので、国民も色々と勉強しないといけないですね。
時効を教えず町が勝訴し14年間分の水道料金を請求したことについて、どう思われましたか?
指南役暗躍し「カラ研修」で助成金を詐取する不正が審査追いつかず横行!
日本経済新聞によると、非正規労働者の待遇改善を支援する「キャリアアップ助成金」の不正受給が全国で横行しているようです。
大阪府警は4月までに指南役ら30人を詐欺容疑で摘発しています。
急増する申請に対して、十分な審査を行う体制が整っていないことが不正受給の背景にあるようです。
「労せずしてもうかる国の支援制度がある」と、コンサルタント会社顧問だった30代の男らは接骨院の事業主らを集めたセミナーで、こんな誘いの言葉をかけていたようです。
関心を示した事業主に男らが指南したのはキャリアアップ助成金の不正受給の手口でした。
受給の要件を満たすために、実際には行っていない従業員の研修を実施したと申請書類に記入するよう指示し、受け取る助成金の額を水増しするため、架空の人物や知人を従業員として申請させていたようです。
コンサルタント会社顧問だった男らは、報酬として助成金の2~3割を受け取っていたそうです。
2019年に大阪労働局の調査で不正が発覚し、大阪府警は2019年10月、詐欺容疑で男を逮捕(詐欺罪で起訴)しました。
事業主側の捜査も進め、2020年4月までに計30人を摘発しました。
だまし取られた助成金は、2013~2016年で計1億2千万円に上るそうです。
キャリアアップ助成金は、厚生労働省が2013年度に創設しました。
研修や賃金増など、雇用する非正規労働者の処遇を改善した事業主に支給します。
処遇改善の対象は7種類あり、事業主が各地の労働局に申請します。
最大1千万円超の助成が受けられます。
厚生労働省によると、キャリアアップ助成金の不正受給が発覚した件数は2014年度は2件でしたが、2016年度は26件、2018年度は70件と急増傾向にあるようです。
刑事事件に発展するケースも相次いでいます。
奈良県警は2019年2月までに約1,700万円をだまし取ったとして、指南役とされる50代の男ら31人を詐欺容疑などで摘発しました。
複数の申請書で、同じマンションの一室が事業所の住所として記載されていることに奈良労働局の職員が気付き、発覚したそうです。
キャリアアップ助成金の申請件数は、2018年度は約9万3千件で2015年度(約4万7千件)からほぼ倍増しました。
審査を担う現場である労働局の体制が追いついておらず、不正受給が横行する要因になっているようです。
会計検査院の調査報告書では、2015~2018年度に大阪や神奈川など8労働局で計約5,400万円の支給が不当だったと認定しています。
「申請書の記載内容が事実と違っていたにもかかわらず、労働局の確認が不十分だった」と指摘しています。
大阪労働局の担当者は「人手不足で不正の発見が遅れたことは否定できない。再発防止の体制を整えたい」と話しています。
厚生労働省は2019年4月、不正受給した事業主が助成金を申請できない期間を3年から5年に延長するなどペナルティーを強化しました。
指南役が不正を主導するケースがあることなどから、同省の担当者は「『100%助成金を受け取れる』『無料で受給額を査定する』といった勧誘には注意してほしい」と呼びかけています。
助成金制度に詳しい社会保険労務士の藤原郁子さんは、「不正を一目で見抜くのは難しく、審査は性善説に頼っているところが大きい」と説明しています。
「本当に必要としている人への迅速な支給と、支給後の抜き打ち検査など不正抑止策を両立させていくことが必要だ」と話しています。
もう明らかなことだと思いますが、補助金や助成金や給付金などは、一定数、不正受給が出てくることを想定したうえで制度を設計しないといけないのではないかと思います。
設計する側は、要件等をこうすれば、抜け道としてこういったことを考えて来る人もいるだろうなと想定し、できる限り不正受給の芽をつぶしていかないといけないのではないかと思います。
その辺は、公務員一筋の方にはなかなか難しいかもしれませんね。
あとは、国がやっているものは、ペナルティが管轄の省庁を問わず及ぶようにしないといけないと思います。
根本的には、本当に必要な方ができるだけ早く使える制度にしてほしいですね。
指南役暗躍し「カラ研修」で助成金を詐取する不正が審査追いつかず横行していることについて、どう思われましたか?
持続化給付金の業務の受託団体が設立時から一度も決算公告せず!
国から持続化給付金の業務を受注した一般社団法人サービスデザイン推進協議会が、2016年の設立以降、法律で定められている決算公告を一度も出していなかったことが、先日、わかったようです。
一般社団法人サービスデザイン推進協議会をめぐっては、電話番号が明示されていないなど、運営の実態がはっきりしないとの指摘が相次いでいました。
新たに財務情報を公開していなかったこともわかり、不透明な民間団体に巨額の公的事業を発注した経済産業省の対応が問われます。
一般社団法人は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づき、定時社員総会などの終了後、遅滞なく貸借対照表を公告しなければなりません。
法人の財務情報をきちんと知ってもらうためです。
しなかった場合は、「百万円以下の過料」という罰則もあります。
衆院経産委員会で、経済産業省は野党の質問に対し、「協議会に確認したところ、設立年度である16年度以来、3カ年分の決算は適切に行われているものの、決算公告は行われていない」と答えました。
過去3年度分の決算については、直近の2019年度分に合わせて、6月の社員総会終了後に公告する予定だそうです。
実は、決算公告は、一般社団法人だけでなく株式会社にも会社法で義務づけられています。
中小企業などでは公告をしていないケースも目立ちますが、国から巨額の公的事業を多数受注してきた一般社団法人がしていないというのは異例です。
一般社団法人サービスデザイン推進協議会は今回の給付金事業を含め、過去に経済産業省の事業計14件(総額約1,600億円)を受注していました。
経済産業省は一般社団法人サービスデザイン推進協議会について、事業実施を通じて「つきあいの深い団体」であることを認めています。
また、一般社団法人サービスデザイン推進協議会は持続化給付金の業務を769億円で受注し、その97%にあたる749億円で広告大手電通に再委託していたこともわかっています。
経産省中小企業庁の前田泰宏長官は経産委で、一般社団法人サービスデザイン推進協議会との契約にあたり、電通に再委託することは知っていたが、協議会の提案書には金額が明記されていなかったと説明しています。
「97%(分の金額で再委託する)という認識はなかった」と述べました。
経済産業省はこれまで、契約は適切だったと繰り返し主張してきました。
業務の大部分を電通に再委託することの是非が、改めて問題になりそうです。
さらに野党側は、契約の手続きについても追及しています。
経済産業省は給付金事業の実施事業者について、競争入札で公募することを4月8日に公示しました。
経済産業省によると公示前の4月2日に、経済産業省担当者が一般社団法人サービスデザイン推進協議会関係者と接触し、意見を聞いていました。
過去の受注実績などを考慮して、経済産業省側から声をかけたそうです。
一般社団法人サービスデザイン推進協議会は4月7日の理事会で、入札に参加することを決めていたとされます。
野党議員は「事前に声をかけている。競争入札のあり方として変じゃないか」などと問いただしました。
経済産業省は、入札の公示前に協議会のほかにも2団体から意見を聞いており、一般社団法人サービスデザイン推進協議会だけ特別扱いしたわけではないとの立場のようです。
これほどの規模のものを短期間にということになると、受けられる企業も限られてくると思いますので、事前に声をかけるのは致し方ないところもあるのではないかと思います。
ただし、社会保険庁などが再委託で問題を起こしていますので、再委託を制限しないといけないのではないかと思いますし、税金を使っているわけですから、黒塗りではなく内容を明らかにしてほしいと思いますね。
あとは、今後は入札時に、決算公告とか(これについては大臣もおっしゃっていましたが)、納税とか、財務状態や損益状況などをきちんと確認しないといけないのではないかと思います。
持続化給付金の業務の受託団体が設立時から一度も決算公告をしていないことについて、どう思われましたか?
「持続化給付金」の受託団体の入札の経緯に野党が注目!
「持続化給付金」をめぐり、国から業務委託を受けた民間団体の実態が不透明とされる問題ですが、野党側は、入札の経緯について詳細な数字を開示するよう政府に求めました。
「つまり事実上、全部委託しているんです。中身何もないから。だから幽霊会社だって務まるんですよ」(「立国社」会派 田嶋要衆院議員)
野党が“幽霊会社”と指摘するのは、「持続化給付金」の業務を受託した「サービスデザイン推進協議会」です。
この団体は業務を769億円で受託しましたが、そこから電通におよそ749億円で再委託されていて、差額について野党は「中抜きではないか」と批判しています。
先日、野党側が追及したのは、この団体の入札の経緯です。
経済産業省が提出した資料によると、入札では、この団体と外資系のコンサルタント会社が競いました。
会社のランクを示す等級では、コンサルタント会社がAなのに対し、団体がCと劣勢でしたが、最終的に団体が落札しています。
「等級Aの『デロイトトーマツ』よりもCの『協議会』が落札をしたと先ほども議論がありました。ランクの低いCランクの『協議会』法人の方が、結局なぜ総合評価で高かったかと」(共産党 笠井亮衆院議員)
「一般競争入札の評価方法は総合評価でございますので、提案内容の技術点であるとか、あるいは価格、こういったものを総合的に勘案して決定するもの」(中小企業庁担当者)
しかしながら、資料では価格や技術点、総合評価点などの部分は全て黒塗りとなっていて、全体像が把握できません。
「疑念が持たれないように、価格についても開示するからねと、デロイトトーマツさんにお話していただいて開示してください」(立憲民主党 川内博史衆院議員)
「今のところ2度確認をしましたけれども、公表していただきたくないということでありました」(梶山弘志経済産業相)
梶山大臣は、開示は難しいという考えを繰り返しました。
野党側は、実態解明のため、改めて安倍総理が出席する予算委員会の集中審議の開催を求めることにしています。
川内博史衆院議員がデロイトトーマツに確認したところ、開示に関しては聞かれていないと答えているようですが、この大臣は大丈夫なのでしょうか?
このサービスデザイン推進協議会の共同代表理事と電通グループの執行社員などが記者会見を開いていましたが、イマイチ納得はできない感じでしたね。
税金を使っているわけですから、入札の結果は、きちんと開示して欲しいですね。
応札の前提として、入札の内容が開示されることもあるということにしておけば、いいのではないかと思います。
それが、色々な面で抑止力になるのではないかと思いますから。
「持続化給付金」の受託団体の入札の経緯に野党が注目していることについて、どう思われましたか?
持続化給付金の事業費の97%が電通へ!
東京新聞によると、新型コロナウイルスで売り上げが減少した中小企業などに最大200万円を給付する持続化給付金で、国の委託先であるか『一般社団法人サービスデザイン推進協議会』が広告大手の電通に対して、事業の大半を再委託していることが分かったようです。
国の委託費の97%は法人経由で電通に流れるようです。
実質的な給付事業は電通が行っているといえ、法人の実体の乏しさが鮮明となりました。
経済産業省が、立憲民主党の川内博史衆院議員に回答しました。
経済産業省は、法人に769億円の委託費を支払うことを公表しています。
今回、法人が電通に支払う再委託費が749億円に上ることが判明しました。
法人は、電通、パソナ、トランスコスモスが2016年に設立しています。
約150万件を想定している膨大な給付件数を処理するには多くの人手が必要で、電通から他の企業に事業の外注が行われている可能性もあります。
電通が設立した法人から電通へ「事業が丸投げされているのではないか」というこれまでの本紙の取材に対し、中小企業庁は「迅速に体制をつくり、誰がどんな業務に当たるかを考える上で法人は大事だ」と回答しているようです。
一方、法人や電通は「経産省の事業なので回答は控える」などとして、給付金事業の運営体制を明らかにしていません。
法人から電通への再委託について、財政が専門の法政大学の小黒一正教授は、「経産省は再委託を含めた業務の流れを承認している。法人が(電通への再委託額との差額にあたる)20億円に見合った役割を果たしているのかどうかを説明する責任がある」と指摘しています。
それでは、『一般社団法人サービスデザイン推進協議会』とはどんな団体なのでしょうか?
ホームページに情報はほとんどなく、電話番号も公表されていません。
先日、登記簿上の所在地を訪ねると、東京・築地の9階建ての小さなビルの9階に入居していたようです。
インターホンに応答はなく、「お問い合わせは(給付金の)コールセンターまで」の張り紙があるだけだそうです。
登記簿情報から代表理事の男性に電話すると、「私はアドバイザーで、詳しいことは不明。実態は電通の人たちがやっているので聞いてほしい」と述べたそうです。
電通は「回答を控える」とコメントしています。
立憲民主党の川内博史衆院議員が中小企業庁に問い合わせると、作業は「少なくとも5千人以上で対応している」と回答したようです。
国が当初想定した申請は約150万件で、マンパワーが必要なため、電通以外にも再委託されている可能性があります。
しかしながら、中小企業庁は取材に対し、「国が契約しているのは協議会。その先の再委託は公表しない」と回答しています。
コールセンターの場所すら明かさなかったようです。
設立以降の経緯からは経済産業省との距離の近さが浮かびます。
法人の設立日は経済産業省が主導した優良ホテルなどの認定事業の委託者公募が始まったのと同日で、法人はこの事業を受託しています。
以来、持続化給付金も含め、4年間で計14件の事業を経済産業省から受託しています。
持続化給付金事業の入札には、もう1社が応札しましたが、法人は公募開始の2日前に持続化給付金のウェブサイト用アドレスをすでに取得していたようです。
事業受託を見越したような対応ですが、同法人は「受託できた場合に備えた」としています。
国税庁出身で中央大法科大学院の酒井克彦教授は、「多額の税を使いながら持続化給付金の交付が滞っており、経産省には再委託を含めた委託先の業務の実態について国民に説明する責任がある。ブラックボックスのまま検証ができなければ問題だ」と話しています。
税金を使っている以上、国民にきちんと説明してほしいですね。
1件当たり50,000円くらい入ってくる計算ですから、電通はおいしい商売をしていますよね。
公募開始前にウェブサイト用アドレスを取得していたということは、裏ですでに決まっていたんでしょうね。
公募の意味はあるのでしょうか?
持続化給付金の事業費の97%が電通へ入いることについて、どう思われましたか?
福島県天栄村が特別定額給付金10万円を1,162人に二重払い!
時事ドットコムによると、福島県天栄村は、先日、政府が国民に1人10万円を配る特別定額給付金について、375世帯の1,162人に誤って二重払いしていたと発表しました。
福島県天栄村が振込先のデータを金融機関に2度渡すミスがあったそうです。
福岡県天栄村総務課によると、給付事務では出納室の職員が金融機関の担当者に振込先のデータをDVDで渡しているようです。
2020年5月19日に振り込む分のデータを5月15日に渡したつもりでしたが、実際は5月14日に渡し済みの5月18日分のデータだったそうです。
金融機関や住民の問い合わせで二重払いが分かったようです。
人口5,300人くらいのところで、2割発生して、1億円強ですから、人口が数十万規模の市とかになると、間違うと、かなりの額になりますし、返してもらう手続きも大変でしょうね。
色々と市町村の方も大変だとは思いますが、きちんとチェックして、間違いのないようにして欲しいですね。
そうしないと、余計な負担がかかって、他でもミスが生じる可能性が高まり、悪循環に陥ると思いますから。
福島県天栄村が特別定額給付金10万円を1,162人に二重払いしていたことについて、どう思われましたか?
売れ筋は「テイクアウト用弁当箱」だが隠れ営業やダミー休業の横行も!
飲食店や喫茶店などに食材を卸す会社の担当者が、世相を囁いています。
「今の売れ筋は、食材ではなくテイクアウト用の弁当箱や小分けしたケチャップ、ドレッシングだ」。
そう話した後、東京商工リサーチ(TSR)の取材に、一斉休業の裏話を話し始めたそうです。
担当者によると、多くの飲食店は当面の店舗営業が期待できず、穴埋めでテイクアウトにシフトしています。
それを裏付けるように、今まで発注がなかった「テイクアウト用弁当箱」や「小分けされた調味料」、「弁当用の総菜」が急増しています。
なかでも、「弁当箱」の在庫が一気に捌けたそうです。
「発注しても全部は入ってこない」ため、このままでは数週間で在庫が無くなる可能性すらあるそうです。
とはいえ、特需があっても「全体の売上は、通常から7割減少している。おかげで週2~3日は自宅待機だ」とこぼしています。
いま、「新型コロナウイルス」感染拡大の防止で政府や自治体は事業者に休業を要請し、要請に応じた事業者には協力金の支給に向けた準備が進んでいます。
ところが、この担当者が声を潜めて驚くようなことを話し出しました。
「表に休業中の紙を張り出し、消灯しているお店が常連客にこっそり営業時間を伝え、暗闇の中で営業している」というのです。
「休業中」なのに発注があり、「隠れ営業」がわかるそうです。
別の飲食店は、毎年ゴールデンウィーク中は定休日にしています。
しかしながら、今年はあえて「ゴールデンウィーク中は休業」と告知しました。
営業マンは、「休業補償の協力金を狙っているのだろう」と憶測しています。
あの手この手で難局を乗り切る知恵なのでしょうか、それとも姑息な手段なのでしょうか?
この担当者は、これまで苦労している経営者を見てきました。
それだけに新型コロナの感染拡大の中で、「休業や時短が続けば生き残りは難しい。グレーとわかっていても事業継続したいと思うのだろう」と、やるせない心情を漏らしています。
要件を厳しくしないとこういうケースが一定数出てくるということは、当初から分かっていますよね。
できるだけシンプルな制度が良いと思いますが、極力、不正が起こらないようにしてほしいですね。
売れ筋は「テイクアウト用弁当箱」だが隠れ営業やダミー休業が横行していることについて、どう思われましたか?
税務大学校和光校舎における専門官基礎研修がオンライン研修等に!
税務大学校においては、令和2年4月6日より国税専門官採用試験により新規に採用された約1,100名を対象とする専門官基礎研修を実施することとしていました。
この研修は、国税庁使命である適正・公平な課徴収の実現ため、税務職員として必要となる税法や会計学などの高度な知識を習得させ、全国統一的な納税者対応を確保するためのものです。
大勢の人が一堂に会するということで、批判がたくさんあったようですが、ようやく、専門官基礎研修の実施に当たっては、専門家等の意見を踏まえ、感染防止対策を徹底することとしていましたが、今般、新型コロナウイルスの感染拡大の状況等を踏まえ、当分の間、和光校舎での専門官基礎研修を、在宅でのオンライン等研修により実施することとしました。
高知県など税務署職員が新型コロナウイルスに何名か感染していますので、もう少し危機感があっても良いように思いますが、決めるのが遅すぎたという感じですね。
期間は約3か月で9割が寮に入る見通しだったようですが、新型コロナウイルスの拡大を不安視する市民から和光市に苦情が相次ぎ、市長もツイッターで「クラスター(感染集団)が発生したら責任を取れるのか」と批判していましたが、クラスター感染が発生する可能性があるような行為は、参加する方やそのご家族の方々も不安でしょうし、国関係のところが率先して避けて欲しかったと思います。
税務大学校和光校舎における専門官基礎研修がオンライン研修等になったことについて、どう思われましたか?
過払い金をめぐる紹介料で東京弁護士会が弁護士法人を業務停止に!
時事ドットコムによると、大手司法書士法人から過払い金返還請求事件を引き継いだ際、弁護士職務基本規程で禁じられた紹介料を支払ったとして、東京弁護士会は、先日、「弁護士法人ベリーベスト法律事務所」(東京都港区)を業務停止6か月の懲戒処分としたようです。
代表社員の両弁護士(ともに43歳)も業務停止6か月としました。
同事務所は2010年設立の新興大手です。
ホームページや東京弁護士会によると、約220人の弁護士を抱え、国内外に38の支店を構えています。
懲戒請求を受けた後、別の弁護士会に新法人を立ち上げ、国内支店の登録も移しました。
新法人や支店に処分は及ばず、東京弁護士会は「懲戒逃れ」と指摘しています。
別の弁護士法人を立ち上げ、支店の登録も移すと、処分は及ばず、やっていけるんですね。
弁護士ゆえ、法律に詳しいのでしょうが、そういったケースを想定しないものになっているのでしょうか?
時代に即していないのであれば、早めに変えた方がいいんでしょうね。
過払い金をめぐる紹介料で東京弁護士会が弁護士法人を業務停止にしたことについて、どう思われましたか?
介護施設が競合激化などで年100件超倒産し戸惑う家族!
日本経済新聞によると、自宅で暮らせない高齢者の受け皿となる介護施設の倒産が高止まりしているようです。
競合激化や人手不足などから福祉・介護事業の倒産は2016年以降、毎年100件を超え、入居時に払った前払い金が戻らないトラブルもあるようです。
倒産に備えた業界団体の保証制度はあるものの要件が厳しく、国は緩和を検討しているそうです。
「ようやく母が穏やかに暮らすことができる」と、2019年12月、神奈川県平塚市の男性(54)は母(83)が乗る車椅子を押しながら、胸をなでおろしました。
母が入居していた東京都内の有料老人ホームの倒産に巻き込まれ、対応に追われてきましたが、2019年末に同市の別の施設に無事、転居できたそうです。
母は脳梗塞の後遺症で会話や体を動かすことが難しく、2017年10月に、都内の施設に入居しました。
立地も気に入り、迷いなく前払い金570万円を支払ったそうです。
しかしながら、最初から気がかりなことが続いたようです。
部屋に運んだはずの荷物が一時行方不明になるなど、ずさんな管理が目に付いたほか、母の着替えが行われずにパジャマ姿のままだったこともあるようです。
職員に問いただしても「すみません」と言うばかりでした。
2018年秋、体調を崩した母が入退院を繰り返すようになり我慢も限界に達しました。
退去して「戻ってくる前払い金で転居しよう」と考えていた2019年1月、運営会社が倒産し、前払い金が戻ってこないことを知らされたのです。
契約時に支払う前払い金は高額ですが、月々の利用料が安くなり、入居者が退去・死亡した場合は返金されます。
しかしながら、経営が破綻し、運営を引き継いだ別会社に返済債務が引き継がれない場合、返金されることはなくなるのです。
こうした場合に備えて、全国有料老人ホーム協会(東京都)は最大500万円の保証制度を設けています。
男性もこの制度を頼りにしましたが、運営は入居者ごと別会社が引き継いだため、保証要件の「入居者全員が退去する場合」に該当せず、前払い金は返ってきませんでした。
男性は弁護士の助言に従い、毎月の利用料を前払い金で相殺することを施設側に提案しましたが、施設側は受け入れず、「利用料の滞納」を理由に2019年中の退去を要請され、2019年12月末にようやく転居のめどがついたのです。
男性は「引っ越し後は心なしか母の体調も良く、ひとまず安心している」としつつも、前の施設での未納分については今後、弁護士と話し合う予定です。
東京商工リサーチによると、福祉・介護事業の倒産は2012年ごろから増加傾向となり、2016年以降は100件を超えて高止まりが続いています。
担当者は「介護や福祉の市場が大きくなり、ノウハウがないまま参入した業者の倒産が増加している」と分析しています。
「利用者側に前払い金が戻らなかったりヘルパーが定着しなかったりするなど様々な問題が起きている。新規参入はまだ多く、倒産は今後も増えるだろう」とみているようです。
一般社団法人「有料老人ホーム入居支援センター」(東京都)の上岡栄信代表理事は、「施設の質は運営者で大きく変わる。利用者側は入居前に施設をしっかり確認することが重要だ」と強調しています。
施設を見極めるポイントとして、(1)職員数が入居者数の8割以上、(2)職員の勤続年数が長い、(3)広告なしでも満室状態が継続などを挙げています。
マイホーム建設やリフォームなどでも同じだと思いますが、やはり、多額のお金を支払うのであれば、運営会社のことを調べるのは当然のことではないかと思います。
性善説ではなく、性悪説で考えないといけない時代になっているわけですから。
自分の目で現場を確かめたり、運営会社の状況を調べたりして、入居するかどうかを決めて欲しいですね。
介護施設が競合激化などで年100件超倒産し戸惑う家族が増えていることについて、どう思われましたか?
総務次官を日本郵政への情報漏えいで更迭!
読売新聞によると、監督官庁の事務方トップが、大物OBに行政処分の情報を事前に漏らしていました。
癒着を疑われても仕方ないでしょう。
前代未聞の不祥事です。
高市総務大臣は、鈴木茂樹総務次官が日本郵政の鈴木康雄上級副社長に対して情報を漏えいしたとして、停職3か月の懲戒処分を科したと発表しました。
鈴木次官は漏えいを認め、辞職しました。
事実上の更迭です。
鈴木前次官は、かんぽ生命保険と日本郵便による保険商品の不適切契約問題を巡り、日本郵政グループへの行政処分の検討状況を電話などで複数回伝えていたそうです。
行政の公正性をゆがめる行為であり、厳正な処分は当然でしょう。
高市総務大臣は、大臣室で開かれた少数の幹部による会議内容が日本郵政側に漏れているとの疑念が浮かんだことから、内部監察を命じ、問題が発覚したとしています。
鈴木康雄氏は総務次官を退任した後、2013年に日本郵政副社長に就任し、現在は上級副社長を務めています。
かんぽ問題をいち早く報道したNHKに対して強硬に抗議し、批判を浴びた方です。
監督官庁が民間企業と必要な情報交換をすること自体は悪いことではありません。
しかしながら、行政処分の情報を事前に企業に伝えることは通常あり得ません。
先輩後輩の関係があるからと言って、機密を漏らすことは到底許されません。
かんぽ問題では、法令違反や社内規定違反が疑われる事案が約1万3,000件に上ります。
日本郵政と日本郵便を所管する総務省は、監督が不十分だったとして業務改善命令の発動を検討していました。
高市総務大臣は記者会見で、「次官が公務に対する信頼性を著しく失墜させる行為を行ってしまったことは誠に残念だ」と語りました。
「逐一情報が漏れていくことによって、先方の対応の仕方などが変わってくる可能性がある」と指摘したのは、もっともです。
総務省は情報管理の適正化を図り、信頼回復に努めねばならないでしょう。
持ち株会社である日本郵政だけでなく、日本郵便、かんぽ生命、ゆうちょ銀行でも総務省OBが役員になっているそうです。
高市総務大臣は「OBが日本郵政グループの取締役などに就任することは好ましくない」と述べ、今後、役員人事を認可する際に厳正な態度で臨む考えを示しました。
グループのガバナンス(企業統治)のあり方を問題視しているのでしょう。
日本郵政と総務省はまず、なれ合いと見られるような両者の関係を改めることが必要ですね。
あってはならない事件ですね。
事務次官ともあろう方が、善悪が分からないのでしょうか?
将来的に、後を引き継ぐことが想定されていたのでしょうか?
停職3か月というのも、甘過ぎますよね。
個人的には、懲戒解雇でもいいのではないかと思います。
高市総務大臣には、天下りに対して、厳しい姿勢で取り組んでほしいですね。
総務次官が日本郵政への情報漏えいで更迭されたことについて、どう思われましたか?
徳島県からデパートがなくなる!
セブン&アイ・ホールディングス(HD)は、先日、徳島市寺島本町西のそごう徳島店の営業を2020年8月末で終了すると発表しました。
人口減が進む地方を中心とした経営合理化の一環で、徳島県内唯一の百貨店が姿を消します。
徳島県都のにぎわいに影を落としそうです。
そごう徳島店は1983年10月、徳島駅前市街地再開発事業で再開発ビルの核テナントに誘致され、「徳島そごう」として開業しました。
2000年7月に民事再生法の適用を申請し、その後、そごう徳島店となりました。
営業面積は22,512㎡です。
徳島県都の玄関口の顔として高い集客力を誇り、売上高はピークの1993年2月期で444億円あったようですが、明石海峡大橋の開通などによる買い物客の県外流出などもあり、2019年2月期には3割以下の128億2,500万円に落ちていたようです。
社員数は社員72人と契約社員104人の計176人です。
セブン&アイHDは2020年8月末で、そごう徳島店のほか、西神店(神戸市)、西武大津店(大津市)、西武岡崎店(愛知県岡崎市)の4店舗を閉店します。
また、2021年2月末に、川口店(埼玉県川口市)を閉めます。
西武の福井店(福井市)と秋田店(秋田市)も2021年2月末に店舗面積を縮小します。
年に数回はこの辺りを車で通りますが、あまり人が入っている感じではなかったので、いつまでもつのかなぁと思っていましたが、とうとうこの時が来たかという感じですね。
若い方は、神戸とか大阪に気軽に高速バスで行くんでしょうね。
年配の方にとっては、デパートに行くことがステータスだったかもしれませんので、なくなってしまうことで行くという楽しみところがなくなってしまうのが残念ですね。
香川県にとっても他人事とは思えないニュースでした。
徳島県からデパートがなくなることについて、どう思われましたか?
暗号資産は政治家個人への寄付禁止規制の対象外!
時事ドットコムによると、高市早苗総務大臣は、先日の閣議後記者会見で、政治資金規正法が原則禁じている政治家個人への寄付について、暗号資産(仮想通貨)による寄付は違反の対象にならないとの見解を示しました。
「金銭などと同様に規制の対象とするためには法的な手当てが必要。新たに政治家の政治活動に制限を加えることになるので、各党、各会派でまず議論してもらう問題だ」と述べました。
政治資金規正法が政治家個人への寄付を禁じている「金銭等」は、金銭・有価証券と規定されています。
高市総務大臣は「暗号資産は、いずれにも該当しないため、寄付の制限の対象にならないものと解されている」と説明しました。
こんなんでいいんですかね?
この辺の感覚がよく分からないですね。
政治資金規正法を早く改正して欲しいと思います。
暗号資産は政治家個人への寄付禁止規制の対象外であることについて、どう思われましたか?
「タピオカ屋さん」の動向調査!
「タピオカ屋さん」が増えています。
東京商工リサーチ(TSR)が保有する日本最大級の企業データベース(約379万社)から、「タピオカ」専業及び関連事業を営む企業を抽出したところ、2019年8月末現在で60社あることがわかったようです。
2019年3月末時点では32社でしたが、夏場の半年間でほぼ2倍に急増しました。
60社のうち、49社(構成比81.6%)は2018年以前の設立で、空前の「タピオカブーム」に乗り、新規に会社を興すより、既存企業が業態や扱い品を変更して参入しているのが特徴です。
貿易統計(財務省)によると、2019年1~7月の「タピオカ」と「タピオカ代用物」の輸入は約6,300トンで、2018年(1~12月)の約3,000トンをすでに大幅に上回っています。
大手飲食チェーンでもタピオカ関連メニューの提供を始めており、街はタピオカブームで溢れています。
なお、本調査は、東京商工リサーチの企業データベース(対象約379万社)から、営業種目や業績変動要因(主要分)に「タピオカ」の記載があるものを抽出、分析したものです。
街を席巻する勢いの「タピオカ屋さん」60社のうち、2019年設立は8社(構成比13.3%)に過ぎません。
ただし、設立年別では、2017年が3社(同5.0%) 、2018年が6社(同10.0%)と年々増え、「インスタ映え」を狙い、多様なタピオカドリンクを生み出しています。
「タピオカ屋さん」 60社の本業は、「パンケーキカフェ」、「肉バル」、「助成金コンサルティング」や「売電事業」など、飲食業から電力事業まで様々です。
本業とは別にタピオカブームにあやかる副業的な店舗展開が特徴になっています。
60社の本社所在地は、東京都が25社(構成比41.6%)で最も多く、次いで、神奈川県と大阪府、福岡県が各5社(同8.3%)、千葉県4社(同6.6%)、沖縄県3社(同5.0%)と続きます。
大都市圏やインバウンドで活気づく地方都市を中心にタピオカが広がっていることがわかります。
中国地方で数年前から「タピオカ屋さん」を運営する企業は、「昨年から来店客数が以前の倍になった」と語っていますが、「毎年、冬場は売上が落ちるが、今年は夏過ぎから来店客数が落ちている」とブーム終焉の兆しも感じ始めているようです。
関東地方で「タピオカ屋さん」を営む企業は、「ライバルが増え、味やインスタ映えなど戦略が重要」と語っています。
ブームが終焉を迎えるのか、落ち着くのか、まだ盛り上がるのか。分岐点に差し掛かっているようです。
タピオカブームは景気と微妙に関連があります。
第1次ブームは、バブル崩壊の1992年頃、第2次ブームは、リーマン・ショックの2008年頃です。
いずれも不況に前後してブームが起きています。
今回の第3次ブームは、米中の貿易摩擦、英国のEU離脱、国内では消費税増税と重なります。
果たして景気を占うブームとなるのか、今後の動きが注目されます。
ちなみに、タピオカミルクティーは“バブル”ティーとも呼ばれています。
我が高松市でも商店街にここ1か月以内で数店舗が出店しています。
個人的には、既にブームは終わっていると思っていますが、どうなるのでしょうか?
あと、最近数多く出てきている相続税対策の商品である東京の区分所有不動産も、1階のテナントがタピオカ屋さんだったりして、この商品はどうなのかなぁと思ってしまいます。
「タピオカ屋さん」の動向調査について、どう思われましたか?
農業票が勝敗を左右する!
日本経済新聞によると、55年体制下で自民党の最大の票田といわれた農業票ですが、農業人口の激減でかつての神通力は失われたといわれてきました。
しかしながら、過去の参院選で自民・非自民勢力が激突した1人区を分析すると、揺れ動く農業票が勝敗を左右してきたことが浮き彫りとなるようです。
21日投開票の参院選で、日本の「スイングボート(勝敗を決する票)」はどう動くのでしょうか?
参院選の主戦場は全国に32ある改選定数1の1人区です。
野党5党派は全区で候補者を一本化し自民党は16区を「激戦区」に指定しました。
1人区には農村部が多くなっています。
かつては自民・非自民の勝敗は固定的でしたが、1990年代以降は振り子のように動いているようです。
「都市部」と「農村部」で自民党の比例代表の得票率を見ると、変化はわかりやすいです。
農業者比率3%未満の14都府県を「都市部」、3%以上の33道県を「農村部」と定義すると、2013年参院選から2017年衆院選の4回の選挙で都市部の得票率はほぼ動いていませんが、農村部の得票率は乱高下しながら下がっています。
背景にあるのは農産品の輸入自由化と、その対策としての「ばらまき」の歴史です。
自民党の安定が崩れたきっかけは1989年参院選です。
竹下政権が前年の日米交渉で牛肉とオレンジの輸入自由化を決め、惨敗しました。
1993年の多角的貿易交渉「ウルグアイ・ラウンド」合意時は6兆円の対策費が配られました。
一方、民主党は2009年衆院選でコメなどの生産・販売価格の差額を交付する戸別所得補償制度を掲げ、農家の支持を取り付けました。
2016年参院選は直前に環太平洋経済連携協定(TPP)に署名し、自民圧勝のなか東北6県中5県で野党が勝利しました。
安倍晋三首相は参院選をにらみ、農業票奪回に力を注いできました。
1月の施政方針演説で「政権交代前の3倍の6,000億円を上回る土地改良予算」を強調し、5,000億円超の巨額の補正予算もつけました。
存在感と比べ、農家の数は激減しています。
1960年に1,175万人いた人口は1980年には約3分の1の412万人に減少しました。
2018年は145万人です。
もはや日本の多数派ではありませんが、激戦区のスイングボートであるがゆえに予算の優先権を握り続けているのです。
参院選を前に農家はなお揺れています。
5月に来日したアメリカのトランプ大統領は日米貿易交渉について、「多くは7月の選挙後。大きな数字を期待している!」とツイッターでつぶやきました。
2020年に大統領選を控えたトランプ氏にとっても農業票は重いのです。
2016年大統領選と2018年下院選を比べると、農家が多い23州では共和党候補の得票率が下がっているためです。
農村では疑心暗鬼が広がっています。
秋田県の農政連は自民現職の推薦を決めましたが、秋田県内13支部のうち3支部は「自主投票」としました。
組合長は「農家をまとめきれない」と語っています。
与野党は30年間、攻守を変えながらスイングボートの争奪戦に明け暮れてきました。
その間、農村にばらまかれた税金は100兆円規模にも迫ります。
その結果、小規模農家が温存され農業の刷新も遅れてきました。
農家の平均年齢は66.6歳で、65歳以上が68%を占めています。
このままでは農業は消滅していくでしょう。
今、必要なのは「消える農村」に税金を注ぎ続けることではないでしょう。
農業を若者やベンチャー企業が魅力を感じるフロンティアへと立て直し、縮小を続ける地方経済をインバウンドなどで活性化することでしょう。
与野党が参院選で競うべきは、そんな未来像です。
選挙のために必要以上に予算が割り振られてきた典型例ですね。
時代の変化に伴った変革が必要だと思いますので、こういう政治も変えていかないといけないでしょうね。
農業に関わっている優秀な方がたくさんいますので、政治に振り回されることなく、農業の発達を期待しています。
農業票が勝敗を左右することについて、どう思われましたか?
タピオカブームは本当に「株価暴落の前兆」なのか?
MONEY PLUSによると、「タピオカブームは株価暴落の前兆ではないか」と、SNSを中心に、タピオカがブームになると株価が暴落するというウワサが広がっているようです。
2019年は「第3次タピオカブーム」とも呼ばれる、タピオカドリンクの流行が起きています。
これが一部の投資家にとって懸念材料となっているようです。
今回のブームでは、若年層の女性を中心に人気が広がり、「タピる」(タピオカドリンクを飲むこと)や「タピ活」(タピオカドリンクを飲む活動のこと)といった新しい言葉が生まれました。
業務スーパーでは即席のタピオカが品切れ続出となるなど、第3次ブームの勢いはとどまるところを知りません。
日本で初めてタピオカブームが起こったのは、1992年といわれています。
ちょうど平成バブルが崩壊している最中の出来事になります。
2回目のブームは、リーマンショックが発生した2008年です。
このように考えると、2019年のタピオカブームが不況の前兆ではないかというウワサ話にも、妙な説得力があるように思えてしまいます。
タピオブームが不況のシグナルであるという考え方は、株式市場でよく生まれる「アノマリー」の1つといえるでしょう。
アノマリーとは、具体的な根拠や理論をもって説明することはできないものの、経験則上よく当たるといわれる物事のことをいいます。
大安に結婚式を挙げると幸せな生活が送れるという経験則も、典型的なアノマリーです。
株式市場で有名なアノマリーといえば「夏枯れ相場」です。
夏枯れ相場とは、8月ごろになると株式の取引高が減少するというもので、8月はお盆やバカンスによって市場参加者が取引を控えるため、取引高が減少する、と解説されることがあります。
実際のところ、本当に休暇が理由で夏枯れ相場になっているのかは判明していません。
ここ10年の傾向でいえば、夏に取引高が減少し、9月から再び活発に取引される傾向にあるようです。
タピオカブームと不況の時期が今後もピッタリ重なるのであれば、夏枯れ相場と同様に、株式市場における有用なアノマリーとなってくるかもしれません。
夏枯れ相場のようなメジャーなアノマリーと比べて、市場との関連が薄いアノマリーには“賞味期限”がある場合もあります。
市場との関連が薄いアノマリーとして、「芸能人の結婚が日経平均株価の暴落を引き起こす」というものがありました。
このアノマリーがどのような顛末をたどったか、実際の例を挙げながら考えてみたいと思います。
2015年に女優の堀北真希さんが俳優の山本耕史さんと結婚発表した翌営業日、8月24日の日経平均は前日比▲895.15円と大きく下落しました。
同年に俳優・歌手の福山雅治さんと女優の吹石一恵さんが結婚したと報じられた翌日、9月28日の日経平均は同▲715円となりました。
2016年に入ると、女優の北川景子さんと歌手のDAIGOさん、女優の優香さんと俳優の青木崇高さんが結婚したと報じられ、どちらのパターンも日経平均が大きく下落しました。
これらの経験則から、芸能人が結婚発表すると日経平均が一時的に急落するというアノマリーが生まれ、内容の面白さも相まって知名度を向上させていきました。
しかしながら、このアノマリーが広く知られることとなった2017年ごろから、ぱったりと株価の急落は起きなくなってきています。
2017年の女優の佐々木希さんとお笑いタレントの渡部建さんの結婚報道では、むしろプラスになりました。
2018年は、結婚報道ではありませんが、女優の石原さとみさんとSHOWROOM社長の前田裕二さんの熱愛が報じられました。
この時、確かに株価は下落しましたが、暴落というほどの下げ幅ではありませんでした。
先日明らかになった女優の蒼井優さんとお笑いタレントの山里亮太さんの結婚報道でも、その翌日6月5日の日経平均株価は+367円と大幅高となりました。
ここ2年に限っていえば、芸能人の結婚は暴落というよりも、むしろ株価の上昇を引き起こす可能性が高いといえます。
市場の反応としても、蒼井優さんの事例で日経平均の暴落を懸念する書き込みはあまりみられませんでした。
芸能人の結婚で日経平均が暴落するというアノマリーは、賞味期限が切れたといっても差し支えなさそうです。
タピオカブームも芸能人の結婚と同様に市場との関連が薄いと考えられるため、賞味期限が切れている可能性に注意が必要です。
アノマリーが成立する要因としては、アノマリーを信じる投資家たちがその通りに行動することで株価に影響が出てくるという説があります。
つまり、ある出来事と株価の変動に本質的な因果関係がなくても、それを信じる人が多ければ、その通りに株価が動くということです。
本当は因果関係のないものに相関性を見出してしまうことを、心理学では「錯誤相関」といいます。
そのルーツは、古代における雨乞いの儀式にまでさかのぼります。
本来、雨乞いの儀式と降水の間に因果関係はないはずです。
しかしながら、雨乞いをした日に降水があると、人は雨乞いをしたら雨が降ったと考えてしまいます。
特に、雨乞いが連続して成功していけば、雨乞いの有効性が徐々に確信に変わってきます。
こうなってしまうと、雨乞いを行なった日に降水がなくても「祈りが足りない」、ないしは「供物が少ない」などといったやり方の部分に視点が移ってしまい、雨乞いという儀式自体を否定しなくなります。
そのため、多少失敗したとしても、雨乞いの儀式はいろいろな地域で長きにわたり受け継がれていったのではないでしょうか?
私たちも、このような心理は持ち合わせています。
たとえばルーレットで、2回連続で赤が出たら次は黒が出るというパターンを10回繰り返しているような時、次に2回連続で赤が出たら黒に賭けたくなってくるのではないでしょうか?
しかしながら、実際にはそこに法則はなく、たまたまそのようなパターンが連続して出てきただけといえます。
タピオカブームと株価暴落について考えると、たった2回のサンプルしかないうえ、初回のブームはバブル崩壊後、しばらくしてから発生しています。
わずか2回の中でも整合性に微妙な点があることを踏まえると、タピオカブームと株価の暴落はいまだ錯誤相関の域を出ないと考えて差し支えないでしょう。
MONEY PLUSのこの記事を読んで安心しました。
最近、月に1回大阪に行っていますが、タピオカを売っているお店は大行列です。
東京オリンピック前が残された消費税率アップの最後のチャンスと言われているため、ここで株価暴落が起こると、しばらく(景気が回復するまで)、消費税率を上げることはできなくなるでしょう。
個人的には、軽減税率には反対ですが、消費税率アップは仕方ないし、10%の方が分かりやすいと思っています。
特に支持政党があるわけではないのですが、消費税率アップに反対や延期と言っている政党には、代替財源を示して欲しいなぁとは思いますね。
タピオカブームは本当に「株価暴落の前兆」なのか?について、どう思われましたか?
オリンピック選手村マンション用地の「不透明」な格安払い下げ!
東京オリンピック・パラリンピックの選手村宿泊棟(21棟)が建設中ですが、都有地だったこの敷地が格安でマンション開発業者に売却されたことが問題視されているようです。
この選手村宿泊棟は、オリンピック後にリフォームされて分譲マンションなどになりますが、はやくもこのGWからはモデルルームが公開されました。
この土地を巡っては、2016年、東京都都市整備局長に、一般財団法人「日本不動産研究所」(東京都港区)が作成した「調査報告書」が提出されましたが、東京都は主要部分を黒塗りし、開示してこなかったそうです。
今回、黒塗りしていない「調査報告書」(別表含め全119ページ)の全文を、ノンフィクション作家の清武英利氏が入手し、ライターの小野悠史氏と「週刊文春」取材班とともに分析・取材したところ、大幅に値引きする根拠が不透明なことがわかったようです。
13.4ヘクタール、東京ドーム約3個分にあたる東京・晴海の同敷地は、もともと都有地でしたが、払い下げの際に約1,500億円とも試算される破格の値引きが行われた経緯が、これまでも疑問視されてきました。
2017年には、値引き分(または適正価格との差額)を舛添前知事と小池知事に求める住民訴訟が起きています(訴訟は現在も継続中)。
これまで住民団体や報道機関が、度々東京都に情報公開請求を行いましたが、東京都は肝心な部分を黒塗りにした“のり弁”資料しか開示してこなかったようです。
「それに強い疑問を感じた」という選手村事業関係者から、“のり弁”のない原本の写しが清武氏に提供されたようです。
報告書の「原本」には、比較対象となったマンションの実名が記載されており、その用地の売買価格を調査したところ、選手村用地の約19倍だったそうです。
都の払い下げ価格が、異常に安い(時価の約5%)ことを、東京都の鑑定資料自体が物語っていることになります。
東京都は、こうした情報を開示しない理由について、次のように回答しています。
「日本不動産研究所が独自に収集、加工した情報が含まれており、公にすることによって研究所の競争上、または事業運営上の地位、その他社会的な地位が損なわれる」(東京都都市整備局)。
小池百合子知事は、都知事選で〈“のり弁”から“日の丸弁当”へ〉と、情報開示の重要性を訴えていましたが、その情報公開に対する姿勢が問われそうです。
おそらく表に出てきているのは一部だけで、本当はこのようなことが他にもあるんでしょうね。
ここ数年、これだけ色々な問題が表沙汰になっているのに、いまだに行われているということは、美味しい思いをしている人がたくさんしるということなんでしょうね。
東京都民ではありませんが、結局は住民が損しているということになると思いますので、こういったことをどんどん表沙汰にしていって、少しでも減ることを期待したいですね。
まともな方々には、どんどん告発していただきたいですね。
オリンピック選手村マンション用地の「不透明」な格安払い下げについて、どう思われましたか?
日付表示はあなたは和暦派?それとも西暦派?
「平成」の次の元号が「令和」に決まりました。
とはいえ元号が発表されるまでの間、和暦を主とする官公庁などの書類のほか、会計基準等の適用時期に関しても「平成33年」など、すでに平成が使われていない年であっても便宜上は平成として記載が行われてきました。
経営財務によると、このため、有価証券報告書などの提出書類における日付表示を西暦に統一したいと考える企業もあるようです。
有価証券報告書における開示に関する規定を定めた「企業内容等の開示に関する内閣府令」の第三号様式をみると、例えば、【提出日】については「平成 年 月 日」となっており、【事業年度】も同様に当該様式上は和暦で示されています。
そのため、和暦表示をしなければならないように思えますが、実務上は全て西暦表示でも問題はないようです。
特別な手続き等は不要で、西暦表示に統一したい企業は、任意で西暦に変更ができます。
経営財務が2018年中に提出された有報の表紙ページを調査したところ、トヨタ自動車や日立製作所、ファーストリテイリングなど、500社以上が西暦表示だったようです。
その中には、ヤマトホールディングスのように表紙に「(注)第153期有価証券報告書より、日付の表示を和暦から西暦に変更しております。」(2018年3月期有価証券報告書)と注釈を入れている事例もあり、同社は監査報告書も含めて西暦表示に変更していました。
しばらく、ややこしい状況が続きそうですね。
僕自身も公的な仕事をいくつかしていますが、2月と3月は書類の提出が結構多かったのですが、同じところに提出する資料でも、和暦と西暦が混在していましたね。
日本人ゆえ、和暦は大事だと思いますし、今後も残していただきたいと考えていますが、混乱・コスト増加などを防ぐため、書類などは西暦で統一してもいいのではないかと思います。
外国から来ている方も多いでしょうから。
個人的にも、元号が変わると発表されたころから、ホームページやブログなどもできる限り西暦に変更をしていますので、僕は『西暦派』です。
『平成』と印刷している事務所の封筒も今後は西暦にしようと思います。
日付表示について、どう思われましたか?
京王電鉄子会社が『キセル』で2億円詐取の疑い!
ニュースでも結構取り上げられていますが、京王電鉄が株式を100%保有する子会社で、法人・学校向け団体旅行を数多く手掛ける京王観光が、組織ぐるみで“キセル”(不正乗車)を行い、JR各社から少なくとも2億円を詐取していた疑いのあることが「週刊文春」の取材で分かったようです。
「不正が行われていたのは、京王観光の大阪支店と大阪西支店の2支店(2018年秋に統合)です。
団体旅行を実施する際、ツアー参加人数分のJR乗車券を購入せず、差額分の乗車料金を利益に計上していたのです。
京王観光にはJR乗車券の発券端末が各支店に設置されており、京王側の責任で発券・発売が行えるようになっています。
この仕組みはJRとの信頼関係のもと、性善説で成り立っており、団体旅行で改札を通過する際、JR側も発券数と乗車人数が合致するかなど、いちいちカウントしていません。
それを逆手に取った不正乗車ですから極めて悪質です」(京王観光関係者)とのことです。
被害に遭ったうちの一社であるJR東海は、「JRの乗車券類を発売できる立場を悪用した不正乗車であって、極めて遺憾であり、厳正に対処する考えである」と回答しています。
一方、親会社の京王電鉄は、「同じ鉄道業界に身を置く同業であると同時に、重要なお取引先様でもあるJR様への背信行為ですので、極めて重大な不正と考えております。JR様や監督官庁の判断結果が下されるのを待って(公表を)検討します」と回答しています。
ヒドい話ですね。
従業員のモラルが低すぎます。
京王電鉄のはキセルに寛容なところなのでしょうか?
こういう事件によって、今後、ツアー参加者側で諸々の手続きが面倒になったりするのは避けてほしいですね。
JRにも厳粛に対応してほしいです。
京王電鉄子会社が『キセル』で2億円詐取の疑いがあることについて、どう思われましたか?
廃校となった小学校の体育館と敷地をマイナス795万円で売却!
埼玉県深谷市は、先日、廃校となった小学校の体育館と敷地について、入札によりマイナス795万円で売却することになったと発表しました。
落札者側で体育館を解体することが条件でした。
マイナス価格で入札が成立し、自治体が資産を手放すのは全国で初めてだそうです。
対象は深谷市中瀬の旧市立中瀬小学校の体育館と敷地約1,505平方メートルです。
統合で1984年に廃校になりました。
体育館は2010年末まで活用され、2015年6月と2017年7月の2回、1,782万1千円の予定価格で入札にかけられましたが、応札はありませんでした。
深谷市は、今回、体育館を落札者が解体する条件を付け、解体費の負担を考慮して予定価格をマイナス1,340万6千円(市が支払う最高額)として入札を行いました。
民間への「無償譲渡」になるため、正式契約には地方自治法に基づく市議会の議決が必要となるそうです。
解体費は結構高いですし、土地の価格がどんどん下がっていく地方では、こういう案件は今後もどんどん出てくるでしょうね。
10年ほど前に、上場企業などには『資産除去債務に関する会計基準』が適用されることになりましたが、有形固定資産の取得、建設、開発または通常の使用によって生じ、当該有形固定資産の除去に関して法令または契約で要求される法律上の義務及びそれに準ずるものをいう『資産除去債務』を考慮するという考え方は正しかったという感じはしますね。
廃校となった小学校の体育館と敷地をマイナス795万円で売却したことについて、どう思われましたか?
「税を考える週間」ってなに?
国税庁は、日頃から国民各層・納税者の皆様に租税の意義、役割や税務行政の現状について、より深く理解してもらい、自発的かつ適正に納税義務を履行していただくために納税意識の向上に向けた施策を行っています。
特に、毎年11月11日から11月17日までの一週間を「税を考える週間」とし、この期間を中心に様々な広報広聴施策を実施するとともに、税務行政に対するご意見やご要望をお寄せいただく機会としています。
2018年の「税を考える週間」では、「くらしを支える税」をテーマとして、国民各層・納税者の皆様に国民生活と税の関わりを理解してもらうことにより、納税意識の向上を図ることとしています。
<「税を考える週間」の取組み>
「税を考える週間」期間中は、主に次のような広報広聴活動を行います。
①マスメディアを通じた広報
新聞広告やインターネット広告などのマスメディアを通じて広報します。
②国税庁ホームページの活用
国税庁ホームページに国税庁の取組を紹介するページを開設します。
このページでは、インターネット番組「Web-TAX-TV」で国税庁の仕事をドラマ仕立てで紹介した番組に加え、社会保障・税番号制度(マイナンバー)、e-Tax、消費税の軽減税率制度の概要を解説した番組を紹介するほか、講演会資料も掲載します。
「Web-TAX-TV」の番組については、国税庁ホームページのほかYouTubeに開設している国税庁動画チャンネルにおいても配信します。
③講演会及び説明会等
国税局や税務署による主に大学生や社会人を対象とした講演会や説明会を開催し、くらしを支える税をテーマに説明を行います。
④国税モニター座談会
国税局や税務署では、幅広い分野の方にお願いしている国税モニターと座談会を行い、税に関するご意見・ご要望をお聴きし、双方向の情報交換に努めます。
⑤税に関する作文の表彰
全国の中学生・高校生の皆さんから応募のあった税に関する作文の入選作品の表彰が、全国各地で行われます。
なお、優秀作品は、国税庁ホームページ及び各種広報紙等に掲載し広く発表します。
⑥その他
関係民間団体による講演会や税の作品展の開催などが全国各地で行われます。
<「税を考える週間」の歴史>
「税を考える週間」のようなキャンペーン期間を設けて集中的に行う広報活動は、かなり古くから行っています。
その歴史は、昭和22年に申告納税制度が導入され、昭和24年に国税局が発足しておりますが、当時は税務行政に対する納税者の不満が多く聞かれていたという時代でした。
そのような時代背景があり、円滑な税務行政の成否は、納税者の協力いかんにかかっている点に顧み、昭和29年から、「納税者の声を聞く月間」を設けたことから始まります。
当時は、積極的な苦情相談、納税施設の改善及び各税法の趣旨の周知を中心とした納税思想の高揚に関する各施策を中央及び地方を通じて組織的に行うこととしていました。
そして、昭和31年からは、苦情相談を重点項目として期間を「月間」から「旬間」に改め、税務行政に対する納税者の皆様の意見や要望を積極的に聴き、各種の行事を通じて納税者の皆様との信頼を深め、納税者の皆様にとって近づきやすい税務署というイメージを作り、納税意識の高揚を図ることを目的に実施していました。
その後、昭和49年には、「旬間」の全般的な見直しを行い、毎年同じ時期に行うこととして「税を知る週間」に改称しました。
「週間」の実施に当たっては、税を社会全体の役割の中で捉える見地から、納税者の方だけでなく国民各層が、税のよき理解者、協力者であるべきことを改めて認識し、広報広聴の対象とするとともに、各種の施策を通じて、声を聞くという受身の姿勢だけでなく、積極的に税の重要性、執行の公平性等を広報することを目的に実施しました。
そして、平成16年からは、国民一人一人が、わが国をどのようにして支えていくのか、公的サービスと負担をどのように選択するのかを含めて、税のあり方、国のあり様を真剣に考えていただく時期に来ているという観点から、単に税を知るだけでなく、能動的に税の仕組みや目的を考えてもらい、国の基本となる税に対する理解を深めていただくことを明確にするため「税を考える週間」に改称しています。
このように、この取組は大変歴史のあるものなのです。
納税は国民の義務ですので、僕ら税理士のように業務として日々税務のことを考えている人は別にして、一般の方々も使い道なども含めて『税金のことを考える』機会を持つことは重要だと思います。
ただし、古くからやっている割には、一般の方々に『税を考える週間』のことがほとんど知られていないのは、国税庁の努力不足だと思います。
彼らは真っ先にチラシなどを送ったり、ホームページに掲載するということを考えるのでしょうが、どれほどの人が見たり聞いたりしているのでしょうか?
最近では、税理士が高校などに行って、『租税教室』を開催していますが、将来の納税者はもちろんですが、既存の納税者にリーチできるものを考えないといけないと思います。
国税庁が考えるべきことだとは思いますが、税務署などで『税金教室』のようなものを頻繁にして、これを受けた方には何らかの所得控除を設けるといったようなことを考えても良いのではないかと思います。
そうすることによって、サラリーマンの方などの税金に対する知識が高まり、経営にも良い影響が出るのではないかと考えます。
教育の中でも、『税金』の授業を義務化するとか、商業学校などだけではなく、どこの学校でも『簿記』を選択科目にすることが、会計や財務や税務に対する興味はもちろんのこと、将来的に素晴らしい経営者を生み出すことになるのではないかと思います。
「税を考える週間」について、どう思われましたか?
新天皇即位日は祝日で2019年の大型連休は10連休に!
2019年春の天皇陛下の退位と皇太子さまの新天皇即位の準備を進めるため、政府は先日午前の閣議で、安倍晋三首相が委員長を務める「式典委員会」の設置を決めました。
直後に首相官邸で初会合を開き、安倍首相はあいさつで、新天皇の即位日となる2019年5月1日を2019年限りの祝日とし、2019年の大型連休を10連休とする方針を表明しました。
安倍首相は、新天皇の即位を国内外に宣言する「即位礼正殿(せいでん)の儀」の2019年10月22日も、祝日とする方針を明らかにしました。
5月1日と10月22日を、2019年に限って祝日とする政府提出法案を臨時国会に提出する見通しです。
この日設置した委員会の名称は「天皇陛下の退位及び皇太子殿下の即位に伴う式典委員会」です。
菅義偉官房長官が副委員長を務め、杉田和博、西村康稔、野上浩太郎の3官房副長官、横畠裕介内閣法制局長官、山本信一郎宮内庁長官、河内隆内閣府次官で構成します。
1~2か月に1度会合を開き、式次第や参列者の範囲などを検討、皇位継承の各儀式の実施指針となる大綱を取りまとめまるようです。
安倍首相は「天皇陛下の退位と、皇太子殿下の即位が同時に行われるのは約200年ぶり。我が国の歴史にとって極めて重要な節目だ。国民こぞって言祝(ことほ)ぐことができるよう、政府として万全の準備を進めていかなければならない」と述べました。
初会合では、皇位継承順位第1位の皇嗣(こうし)となる秋篠宮さまが、皇太子と同様の立場であることを内外に示す「立皇嗣(りっこうし)の礼」の2儀式を、憲法が定める国事行為として2020年4月19日に行うことも決定しました。
立皇嗣の礼は、天皇の弟が皇太子待遇となるのに伴い初めて実施されるようです。
浩宮さまが皇太子となった際の「立太子(りったいし)の礼」にならい、皇太子待遇となったことを宣言する「立皇嗣宣明(せんめい)の儀」、天皇にお礼を述べる「朝見の儀」を2020年4月19日に行います。
立太子の礼では賓客を招く祝宴「宮中饗宴(きょうえん)の儀」も行われましたが、宮内庁内には見送り論があるようです。
この日の会合では、2019年2月24日に政府主催で行う「天皇陛下在位30年記念式典」の概要も決まりました。
即位20年の式典を基本的に踏襲し、安倍首相が式辞、衆参両院の議長と最高裁長官らが祝辞を述べるようです。
「国民代表の辞」もあり、民間から研究や芸術、スポーツなどで業績をあげた人々も招くそうです。
内閣府には、各府省庁の事務次官らで構成する「式典実施連絡本部」(本部長=菅官房長官)を設置しました。
警備、外国からの賓客、国内の参列者といった分担ごとに班を立ち上げ、事務的な準備を加速させるようです。
ちなみに、政府は2018年4月に、皇位継承に伴う一連の儀式や式典に関する基本方針を閣議決定し、憲政史上初となる退位の礼として2019年4月30日に「退位礼正殿の儀」、5月1日に皇位のしるしとされる神器などを引き継ぐ「剣璽(けんじ)等承継の儀」といった一連の日程を決めていました。
2019年は4月27日土曜日から5月6日月曜日まで(4月30日火曜日と5月2日木曜日は祝日に挟まれ休日、5月6日月曜日は振替休日)10連休となるようで、休日が増えることは喜ばしいことかもしれませんが、公認会計士・税理士という職業柄、財務・会計・税務に関わる仕事をしているため、月末の仕入先などへの支払い、金融機関への借入金の返済、給与計算や支払い、決算業務、申告業務などに多大なる影響を与えるのではないかという点がすごく気になります。
実務のことをよく知らない方々が決めているんでしょうね。
2月決算企業の場合、実質は申告期限が5月7日になるのかもしれませんが、決算・申告後にやっていた業務を前倒してしないといけなくなったり、3月決算企業や4月決算企業は、決算業務や申告業務に使える営業日が少なくなったりしますので、大変でしょうね。
結局のところ、通常より前倒しのルーチン業務が多くなり、決算や申告のために大型連休中も出社して仕事をするということになりそうに思いますね。
あと、月末や月初に返済しているところには、金融機関も返済予定表を出し直さないといけなくなるでしょうね。
新天皇即位日は祝日で2019年の大型連休は10連休になることについて、どう思われましたか?
中央省庁の障害者雇用が実際は半数以下!
2018年09月06日(木)
毎日新聞によると、中央省庁による障害者雇用の水増し問題で、厚生労働省が先日公表した調査結果は、不適切に算入した人数は3,460人に上り、実際の雇用者数は半数以下だったことが明らかになったようです。
意図的な不正もあったとの証言もあり、障害者の支援団体や企業からは「裏切られた」「民間なら誰かのクビが飛ぶ問題」などと怒りの声が上がりました。
「国家公務員になれたかもしれない3,460人の障害者の期待を裏切った」と、障害のある地方議員らでつくる「障害者の自立と政治参加をすすめるネットワーク」代表の伝田ひろみ・さいたま市議は憤っているようです。
伝田市議は幼いころの病気で手足に障害が残り、車いすで生活しています。
今回の調査結果を受け、「障害者と共に暮らす環境整備ができていないというのが根本的な問題だ」と語気を強めました。
NPO法人「障害者の職場参加をすすめる会」(埼玉県越谷市)の山下浩志事務局長も、「率先垂範すべき行政が、水増しをしていたなんてとんでもない」と怒りを隠しません。
法定雇用率を定めた障害者雇用促進法について「数合わせをすればよいという制度の問題が明らかになった」と指摘し、「数字を見るだけでなく、障害者の雇用実態や労働環境を検証すべきだ」と訴えました。
一方、今回の雇用率の問題以外にも、障害者に関する制度で不正が横行しているのではないかと心配する声もあるようです。
知的障害者や家族でつくる「全国手をつなぐ育成会連合会」で統括を務める田中正博さんは、「それぞれの制度が本来の趣旨に沿って運用されているか、行政は確認してほしい」と訴えました。
ある大手銀行の幹部は「障害者雇用の旗を振っている官が、こんなにも水増しをしていたなんて、信じられない」と憤慨しているようです。
民間企業は、厚生労働省から毎年6月1日時点で障害者雇用数の報告を求められ、雇用率が達成できなければ、1人につき月5万円を納めなければなりません。
3年に1度は独立行政法人の調査も受けており、それぞれ雇用率を達成するために試行錯誤しています。
この銀行でも障害者が働きやすい会社を設立して多くを雇用し、グループでの雇用率を高めているようです。
ユニクロを展開するファーストリテイリングは、2018年の国内での障害者雇用率は5.28%と、企業の法定雇用率(2.2%)を大幅に上回ります。
担当者は「一人一人の特性を見極めるため、個人面談を重ねて担当業務を決めている。足が不自由な人には座ってできる作業を、耳が不自由な人には聴覚障害を示す名札をつけてもらい、顧客の理解を得やすいようにして接客業務を任せている」と話しています。
こうした取り組みの結果、民間企業の障害者雇用者数は、2017年まで14年連続で過去最高を更新し、法定雇用率を達成した企業の割合は19年ぶりに5割を超えました。
大手電機メーカーの幹部は「民間企業で今回の省庁と同じことをすれば誰かのクビは飛ぶ。省庁の水増しは意図的な不正であり、しっかり原因究明をしてもらいたい」と注文を付けました。
最近、公務員の存在価値はあるのかと思うような事件が多いですね。
何かを進めるのであれば、自らが規範となるべきであり、民間企業が独立行政法人の調査を受けるのであれば、中央省庁なども受けるべきであり、達成していない場合は、関係者のボーナスを減らして負担すべきではないかと思います。
他の報道によると、国税庁が最も水増しが多いとのことですが、国税庁相手に税務調査で戦ったりしている税理士としては、国税庁に、調査などをする資格はないと思ってしまいますね。
公務員制度を含め、中央省庁の解体・再構築を考えないといけない時期になっているのではないかと切に感じます。
中央省庁の障害者雇用が実際は半数以下であったことについて、どう思われましたか?
日本銀行が投資信託の家計保有額を30兆円以上も誤計上!
金融庁が公開請求者の情報漏出認め野田総務大臣も謝罪!
滋賀県内の税務署職員3人が紛失した書類を作り直し減給処分!
レオパレス21が建築基準法違反疑いで3.7万棟を調査へ!
2018年06月04日(月)
レオパレス21は、先日、計206棟のアパートで施工不良を確認したと発表しました。
「界壁」と呼ばれる防火性などを高める部材が天井裏に未設置だったり、十分な範囲に設けられていなかったりしたようです。
建築基準法違反の疑いがあります。
2019年6月までに全3万7,853棟を調査し、不備のある物件を改修するようです。
田尻和人取締役専務執行役員が、都内で記者会見し、「当社に施工管理責任があった」と謝罪しました。
施工不良が見つかったのは1996~2009年に施工したアパート6シリーズです。
すでに調査を終えた290棟のうち、38棟で界壁がないなどの不備があったようです。
建築基準法は、火災時の延焼防止などの観点から界壁を天井裏に設置するよう定めています。
施工業者に渡したマニュアルには界壁の記載があったのに、個別の下請け業者が参照する図面には記載がないなど整合性に不備があったようです。
施工時の検査でも、図面との照合確認が不十分だったそうです。
これとは別に、1994~1995年に竣工した2シリーズでも、調査した184棟のうち168棟で界壁がありませんでした。
レオパレス21は、2018年4月末に施工の不備がみつかったと発表していました。
一連の調査での不備は200棟を超え、今後も増える見通しです。
2019年6月までに全棟を調査し、2019年10月までに改修工事を終える方針です。
工事費は10室程度の物件の場合、1棟あたり60万円程度としています。
レオパレス21は意図的な手抜き工事の可能性を否定する一方、天井に不燃材が使われており「安全性はある」と強調しています。
これだけあるのに、意図的ではないと言えるのでしょうか?
違う問題でも訴訟を抱えていますし、今回の件で、信用を失い、今後は厳しいでしょうね。
アパート建設に対する銀行の融資も厳しくなっているようですし、数年後にはこの会社はなくなっているかもしれませんね。
オーナーにとっては、建てたら終わりではなく、長い間にわたり所有するものですので、メーカー側もその点を認識しないと未来はないでしょうね。
レオパレス21が建築基準法違反疑いで3.7万棟を調査することについて、どう思われましたか?
シェアハウス投資の不動産会社スマートデイズが民事再生法申請!
2018年04月27日(金)
シェアハウス投資の賃料不払い問題で、女性専用シェアハウス「かぼちゃの馬車」などを運営する不動産会社スマートデイズ(東京都中央区、赤間健太社長)は、先日、東京地裁に民事再生法の適用を申請し、地裁から保全処分と監督命令を受けたと発表しました。
帝国データバンクによると、負債額は2018年3月末時点で約60億円です。
スマートデイズは2012年設立で、一括借り上げによる長期の賃料保証をうたって会社員らをシェアハウスオーナーに勧誘し、会社員らは億単位のお金を借りてスマートデイズから割高な物件を買いました。
スマートデイズは、入居者募集や管理を担いましたが入居率は低迷し、オーナーへの物件売却益で賃料を払う自転車操業状態でした。
2018年1月には資金繰り悪化を理由に賃料支払いを停止し、オーナーの借金返済が難しくなって問題が表面化しました。
物件は2018年1月時点で未完成分を含め約1千棟で、オーナーは約700人にのぼります。
スマートデイズは、先日、「目下の資金繰りに鑑みると、物件の水道、電気などの生活インフラの確保が困難となるおそれがある」とのコメントを公表し、オーナーらに管理会社を変更するよう求めています。
先日、債権者となるオーナー向け説明会を開きました。
スマートデイズでは、経営再建のため2018年1月に社長に就いた菅沢聡氏が今月初めに退き、取締役の赤間氏が社長に就任しています。
そもそも投資家は一括借上げに飛びつきがちですが、相手がどこで稼ぐのかを考えてやったほうがいいですね。
一括借上げは儲からないはずなので、販売時にその分まで回収しているはずです。
本人が投資という商売が成り立つかどうかのけんとうはもちろんのこと、相手の商売も成り立つかどうか考えないといけないですね。
シェアハウス投資の不動産会社スマートデイズが民事再生法を申請したことについて、どう思われましたか?
会計検査院は財務省や官邸に頭が上がらない!
これでは何のための検査だったのでしょうか?
まるで財務省と示し合わせたアリバイ作りのための“出来レース”、「茶番劇ではないか」と批判されても仕方ないでしょう。問題は、会計検査院がなぜそのようなことをしたのかです。
それを考えていくと、会計検査院という組織の置かれた立場、制度的状況から来る、避けがたいジレンマが見えてきます。
そもそも会計検査院とは、憲法第90条にその根拠を持つ機関であり、内閣に対して“独立”の地位を有している、特殊かつ特別な行政機関です。
会計検査院には担当の大臣等は置かれず、その任命に国会の同意を要する検査官3名が置かれ、うち1名が互選により院長となります。
ただし、検査官を任命するのは内閣であり、院長についても互選の上、任命するのは内閣です。
この検査官の人事、かつてこのうち一人が大蔵省(当時)からの天下りポストの事実上の“指定席”になっていたのです。ところが、大蔵省不祥事に端を発する霞が関バッシングの嵐が吹き荒れる中、国会同意を前に大蔵省出身の検査官候補が蹴られて、なぜか総務庁(当時)出身者(元事務次官)に棚からぼたもちのようにお鉢が回ってきたということがあり、その後2代は旧総務庁系(二人目も元事務次官)の指定席になったこともありました。
まさにこの人事に関連して、衆参両院での同意後の平成9年3月25日の第140回国会衆議院決算員会の参考人質疑において、参考人として出席した岸井成格・毎日新聞編集局次長(当時)は、この件について、以下のように述べています。
「 ~(前略)~ 会計検査官の大事(原文ママ・おそらく「人事」の打ち間違い?)については、あの当時、特に大蔵省からOBを起用するというのは、あれだけ大蔵省の問題が騒がれ、まさに監督権限の分離問題という議論の真っ最中にそういう人事任命を発令するということ自体が、ちょっと政治的には不用意だったという点が一つと、やはり基本的には、会計検査院の独立性、信頼性からいえば、官僚OBの起用は慎むべきである ~(後略)~ 」要するに、会計検査院のトップ人事は、霞が関や永田町の事情に大きく左右されてきたということです。また、会計検査院の職員は独自の試験によって採用されるのではなく、国家公務員採用試験によって選抜し、採用者を決定するという、他の府省と同じ方法によっています。
つまり、会計検査院の職員といっても国家公務員法が適用される一般職の国家公務員であり(幹部職への任命等に関する規定については適用除外)、給与体系も同様に給与法が適用されているのです。
予算についても、査定するのは財務省であり、国会及び裁判所と同様に財政法第19条に二重予算制度と呼ばれる“例外的な規定”が設けられてはいるものの、基本的には各府省と変わりありません(財務省の説明よると、同条に基づくこの取り扱いの適用があったのは昭和27年度予算に関する1例のみとのこと)。
第19条 内閣は、国会、裁判所及び会計検査院の歳出見積を減額した場合においては、国会、裁判所又は会計検査院の送付に係る歳出見積について、その詳細を歳入歳出予算に附記するとともに、国会が、国会、裁判所又は会計検査院に係る歳出額を修正する場合における必要な財源についても明記しなければならない。ちなみにこの例外的な取り扱いがある国会及び裁判所については、各府省との人事交流はあるものの職員の身分は別であり、当然採用も国家公務員とは別の試験等によっています。
こうした点を踏まえても、会計検査院については非常に“中途半端な扱い”をされていると言えるでしょう。加えて、かつて会計検査院は、検査、特に地方等での検査に当たって、いわゆる官官接待を受けていたことが大問題となり、会計検査院への風当たりが非常に強くなったことがあるようです。要するに、会計検査院は“独立”の地位を占めているといってもそれは形式的である面が多く、基本的には霞が関の各府省と同じ、「並びの存在」であって、その活動、職権の行使についてもおのずと制約というか、自制がかかってしまう傾向があると考えた方がいいようです。
分かりやすく言えば、会計検査院といえども、対財務省、対官邸ということになると慎重にならざるをえない、単刀直入に言えば、「頭が上がらない」ということでしょう。
それが今回の森友問題に関する検査における不祥事につながったのではないでしょうか?
実際、会計検査院の、まさに森友問題検査を担当した部局は、参院に提出した報告書には相当自信を持っていたようです。
一方で、検査の対象はあくまでも国の収入および支出であること等を盾に、必要十分な行政文書が把握できないために詳細な内容が確認できなかったことを報告書において指摘しながら、「検査をやり直す必要はない」としていたようです。
検査に必要な資料がなければそれの提出を求める、そうしなければ、検査の対象が国の収入および支出だとして、それを全うすることすることすらできないはずです。
しかしながら、実際には文書がないのではなく、改ざん前の文書が存在していることを認識していながら、それを検査の対象としなかったわけですから、なんらかの自制が働かなければそうしたことは起こりえないと考えるのが自然でしょう。
従って、森友問題に関しては、財務省のみならず会計検査院の検査についても国会において追求されるべき点は多々あるはずです。
ただし、その最終的な目的は、一部で主張されているやに聞く“会計検査院解体論”といった極端なものではあるまい(会計検査院解体ということになれば憲法第90条を改正する必要があるから、もしかしたら改憲のとっかかりとすることが解体論の真の目的?)。
その目指すべきところはといえば、すなわち会計検査院を現状の中途半端な位置から解放し、高い倫理観を堅持しつつ、自制も萎縮もすることなくその職責を心置きなく全うできるようにすること、つまり権限の適正化(実質的には強化)であるはずです。
その対象は、会計検査院の組織および権限を規定した会計検査院法にとどまらず、先にも触れた国家公務員法等も含まれるべきでしょう。
もっとも、それは容易な話ではない。霞が関の各府省からの相当強い抵抗や反発が想定されるからです。
会計検査院ともなれば、強い抵抗が予想されるため、政治が一体となって進める必要があるでしょう。
完全に独立の立場から、業務ができる組織であってほしいですし、そのための改革をしてほしいですね。
シェアハウス融資で役員に不正行為の疑いがあり金融庁がスルガ銀行を緊急検査!
2018年04月24日(火)
女性専用シェアハウス「かぼちゃの馬車」をめぐる投資トラブルに絡んで銀行側の対応を調べるようです。
大半の建設費用を融資したスルガ銀行で、審査を通りやすくするために書類の改ざんなど不正行為に役員が関与していた可能性もあるとみています。
かぼちゃの馬車は、先日、東京地裁に民事再生法の適用を申請し、経営破綻したスマートデイズ(東京・中央)が運営するシェアハウスです。
所有者の建物を借り上げ、女子学生らに転貸する「サブリース」と呼ばれる事業を展開していました。
長期の賃料保証をうたい、会社員らの投資を勧誘しました。
空室を埋められず、1月に賃料の支払いを止めました。
スルガ銀行は、1棟で1億円前後する土地・建物の資金を約700人の投資家に融資しました。
融資額は1千億円規模に上るとされます。
複数の関係者によると、スルガ銀行の一部役員が主導する形で、投資家の年収を証明したり、預貯金の残高を示したりする審査書類を改ざんするなどの行為に関与した疑いが持たれています。
金融庁は、スルガ銀行が不正を見抜けなかっただけでなく、スルガ銀行の役員が不正に加担していた例もあるとみています。
金融庁は3月中旬、銀行法に基づく報告命令をスルガ銀行に出し、状況を把握しています。
今回の検査で役員の関与や組織的な不正行為が判明すれば、厳しい行政処分を検討するでしょう。
投資家の相談を受けている弁護士によると、スマート社の販売代理店経由でスルガ銀行に提出された審査書類では、預貯金残高が100倍程度に水増しされているといった例が多数みつかったようです。
販売代理店が融資審査を通りやすくするため改ざんした可能性が高いようです。
弁護士によると、販売代理店は投資家に対して「(改ざんは)スルガ銀行も承知していることだ」と話しているようです。
スルガ銀行の広報担当者は、先日、「指摘のような事実を認識していないため、コメントは差し控える」と話しています。
実際はどうなのか分かりませんが、調査をして全容を明らかにしてほしいですね。
銀行のビジネスのために、個人の方々が損をするのは許せないですね。
シェアハウス融資で役員に不正行為の疑いがあり金融庁がスルガ銀行を緊急検査したことについて、どう思われましたか?
仮想通貨交換業者7社が業務改善計画を提出!
業界は信頼回復を図ろうとしていますが、規制強化の流れは強まり、取り巻く環境は厳しさを増しているようです。 改善命令を受け、計画を提出したのはコインチェックのほか、バイクリメンツ(東京)、GMOコイン(同)、テックビューロ(大阪市)、ミスターエクスチェンジ(福岡市)、ビットステーション(名古屋市)、FSHO(横浜市)の6社です。
ビットステーション、FSHOの2社は、顧客資産の私的流用などが確認され、1か月間の業務停止も命じられています。 コインチェックの改善計画提出は、2月に続き2度目です。
今回は、送金先を追跡できず、匿名性が高い「Monero(モネロ)」など4種類の仮想通貨の取り扱い打ち切りも盛り込まれたとみられます。
コインチェックは提出後、「改善策を着実に実施する。信頼回復に向け、最善の努力をしていく」とのコメントを出しています。 2018年3月22日には、NEM流出後に停止していた「リスク」「ファクトム」の2種類の仮想通貨の引き出しと売却の再開も発表しています。
取引を停止している仮想通貨は残り5種類となります。
先日、流出発覚時のNEM保有者に対して日本円で計約466億円を補償金として支払ったほか、一部通貨の出金や売却を再開していました。 先にルールを作って、それを満たすことのできる企業のみが参入するという流れではなく、既に取引が行われていた中で、あとからルールを作った以上、こういった企業が出てくるのは仕方ないでしょうね。
実務を考慮し、規制する以上、安心して投資ができる環境を作らないと、仮想通貨市場は成り立っていかないでしょうね。
コインチェックのマネックスグループによる買収のように、大手に買収されるところもたくさん出てくるでしょうね。
金融庁には、頑張ってもらいたいですね。 仮想通貨交換業者7社が業務改善計画を提出したことについて、どう思われましたか?
仮想通貨交換業者7社に対して一斉に行政処分!
業務停止命令を含む厳しい対応で臨み、利用者保護最優先の姿勢を鮮明にしました。
一方で、「育成路線」とのバランスに腐心する苦悩もにじんでいます。
2018年2月16日、衆議院財務金融委員会で、「内部管理体制などを検証し、早期に登録の可否を判断したい」と、金融庁で仮想通貨チームのヘッドをつとめる佐々木清隆総括審議官は、正規の登録が済んでいない「みなし業者」のまま営業しているコインチェックへの対応を問われると、こう答えました。
中途半端な「みなし業者」という位置づけが多額の仮想通貨の流出事件を招いたのではないか?という空気が広がるなか、答弁は金融庁がコインチェックを廃業に追い込む「登録拒否」に突き進んでいると受け止められたようです。
“封印”してきた強権路線が頭をもたげた瞬間でした。
このころ、金融庁内にもじわりと温度差が広がり始めました。
「ほかのみなし業者にも検査に入っている以上、実態を比較しながらきちんと手続きを踏む必要がある」(金融庁幹部)と、コインチェックだけ抜き出して処分を急げば、監督方針に整合性が取れないという意見も現場にはあったようです。
2018年2月末に、コインチェックは当初、補償時期などを公表する考えを持っていました。
記者会見の予定まで立てていたようですが、直前になって自主的に取りやめました。
金融庁の検査が続き、追加の処分の中身が見えないなか「事業の継続ありき」で公表するのはかえって金融庁を刺激しかねないという思惑が働いたとみられます。
2018年3月初旬には、「(コインチェックに)かなり厳しい要求を投げかけている。まだ足りない部分はたくさんある」(金融庁)と言ったようですが、それでも1回目の業務改善命令で求めたシステム管理の強化はある程度めどが立ちつつあったようです。
検査に入った一部のみなし業者には違法行為も見つかりました。
実態を比較し、業務停止命令は早計だとの判断に傾きました。
答弁から約3週間たった2018年3月8日、金融庁がコインチェックに出したのは2度目の業務改善命令でした。
「経営体制の抜本的な見直し」など厳しい要求事項が並ぶ半面「取引再開や新規顧客のアカウント開設に先立ち」といった文言もみられ、金融庁の対応への苦慮が垣間見えました。
「けしからん、と登録拒否するのは簡単かもしれないが、まずやるべきは補償と顧客資産の返還だ」と、ある金融庁幹部は冷静にこう話しているようです。
顧客の約580億円相当の仮想通貨を流出させた事実は、きわめて重いでしょう。
かと言って、懲罰的に登録を拒否すれば問題が解決するわけではなく、利用者保護にもつながりません。
また、麻生太郎金融相が掲げる「金融処分庁から金融育成庁へ」という路線の自己否定にもつながりかねません。
片っ端から厳しく処分しては、生まれたての仮想通貨市場が一気にしぼみかねず、それは避けたいというのが金融庁の本音のようです。
フィンテックの「テック」部分の担い手は、金融庁がこれまで監督してきた金融業界の外にいた人たちでもあります。
登録の可否を性急に判断せず「じっくりと丁寧に手順を踏む」(幹部)と、金融庁も模索が続いています。
コインチェックは設立からわずか6年だが、自己資金で460億円もの補償ができてしまうほど「軽視できない顧客基盤を抱えている」(幹部)のが実態です。
ただし、懲罰的な「処分のための処分」では意味がありません。
まだ続くコインチェックへの対応に「育成庁」をめざす金融庁のあり方も試されていますね。
金融庁が関わる以上は、きちんと規制もしないといけないと思いますが、仮想通貨は実態が見えないところも多々あるでしょうから、金融庁も大変でしょうね。
仮想通貨は素晴らしいものだと思いますので、規制をきちんとして、皆さんが安心して取引ができるように早くなってほしいですね。
仮想通貨交換業者7社に対して一斉に行政処分が行われたことについて、どう思われましたか?
「Zaif」のシステム異常で仮想通貨をゼロ円で販売!
2018年03月07日(水)
仮想通貨交換業者のテックビューロ(大阪市)は、先日、運営する交換所「Zaif(ザイフ)」で、仮想通貨をゼロ円で販売するトラブルがあったと発表しました。
顧客の7人がゼロ円で仮想通貨を取得したようです。
価格の計算システムに異常が生じたのが原因で、訂正扱いとして顧客の残高データを修正しました。
テックビューロによると、約18分間、仮想通貨の「ビットコイン」や「モナコイン」を扱う「簡単売買」と呼ばれる取引で、無料で仮想通貨を取得できる状態になったようです。
その後、完全復旧しました。
一部の顧客が、取得した仮想通貨を売り注文に出したため、購入したい人と売却したい人の注文を合わせる取引でも異常な数値が表示されたそうです。
テックビューロはしばらく、事実関係に関する取材に回答していませんでしたが、後日ネット上で「お客さまには多大なご心配とご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ございません」とコメントしました。
取得した人がどうなるか分かりませんが、先日の件もそうですが、こういうことがあると、取引をしてよいのだろうかと不安に思ってしまいますね。
きちんと取引の仕組みなどを確立したうえで、システムの構築をして、こういうことがないようにしてほしいですね。
そうしないと、仮想通貨は素晴らしいとは思いますが、信用をどんどん失って行くと思いますので。
「Zaif」のシステム異常で仮想通貨をゼロ円で販売できたことについて、どう思われましたか?
日本株は予想重視ではなく決算後に買え!
2018年02月20日(火)
決算発表で企業業績の実績を確認してから投資する方がパフォーマンスが上がりやすいという構造変化が日本株市場で起こっているようです。
規制の影響でアナリスト予想の正確性が落ち、世界景気の好調さなどを背景に企業業績の実績値は着実に拡大が続いているからです。
「思惑で買って、事実で売れ」との相場格言は過去のものになるかもしれません。
先日も「実績重視」を感じさせる銘柄がありました。
前週末発表の2017年4~12月期決算で純利益が前年同期比で47%増と大幅に拡大したファナックです。
寄り付きから買い注文を集め、朝方には一時5%高まで上昇しました。
ファナックは四半期受注高を公表し、業績の予想が容易なため、好決算でも「材料出尽くし」として売られやすい銘柄だとされています。
しかし今回は、「業績の好調さが確認でき、まだ弱気になる必要はない」(アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパンの寺尾和之氏)との受け止めが優勢だったようです。
「予想重視」が従来の常識でした。
証券アナリストの予想を織り込む形で業績拡大が期待される銘柄は先んじて買われてきました。
そうなると、決算内容が予想通りでも「驚きはない」として利益確定売りに押されやすくなります。
実際、三菱UFJモルガン・スタンレー証券の分析によると、2008年以降、アナリスト予想をもとに先回りで投資すると高い運用成績を上げてきました。
ところが、2017年は、実績重視で「決算後に買う」方が運用成績がよくなるという変化が生じました。
具体的には、発表された四半期決算で増益率の高さなどがはっきりした好決算銘柄を買い、低調な銘柄を売る戦略だ。特に10月下旬から11月の決算発表シーズンで運用成績のよさが顕著でした。
背景には2つの環境変化があるようです。
まず1つめは、円相場とアメリカ長期金利の安定です。
実績重視の投資法が高成績をあげた2017年3月から年末まで、円相場は7円程度の幅で安定的に推移していました。
将来の為替・金利動向に不透明感があれば、早めに利益を確定したくなるのが投資家心理です。
一方で、安定した環境下であれば、好業績企業が今後も好調を維持するとの見通しが成り立ちやすくなります。
2つめは、上場企業が一部のアナリストなどだけに業績動向を示唆するのを禁じた規制の影響で、事前に業績予想を立てるのが難しくもなりました。
この結果、アナリスト予想の上方修正や下方修正といった短期的な情報の価値が低下し、「実績を見てから買う投資行動になりやすくなった」(三菱UFJモルガン・スタンレー証券の古川真氏)。
2018年に入っても、投資家の間で「為替・金利の安定」という前提条件は崩れていません。
ピクテ投信投資顧問の松元浩氏は、「円相場が108円台をつけたといっても、17年の変動幅の範囲。為替よりも景気拡大の持続性が重要な局面」と指摘しています。
アメリカの税制改革による需要の押し上げなどを理由に、日本株に強気な姿勢を続けています。
実績重視の投資行動が定着したとすれば、決算発表シーズン終了後に買いが優勢になる展開も期待できそうです。
証券アナリストも、AIに取って代わられる代表的な職業だと思いますので、厳しい時代になってきたなぁと改めて感じました。
我々、公認会計士や税理士も、AIに取って代わられる代表的な職業ですので、差別化を図ってずっと生き延びていきたいですね。
日本株は予想重視ではなく決算後に買えという構造変化が起きていることについて、どう思われましたか?
森友学園との交渉の関連文書である「照会票」や「相談記録」などを開示!
2018年02月14日(水)
学校法人「森友学園」(大阪市)が大阪府豊中市の国有地を評価額より大幅に安く取得した問題で、財務省近畿財務局が学園への売却を検討した際に作成した内部文書を保管していたことが、先日、分かったようです。
これまで同省は「交渉記録は廃棄した」と説明していました。
同省担当者は「近畿財務局内での問い合わせと回答内容を記載したもので、学園との交渉記録には当たらない」としています。
国に情報公開請求し、開示を受けた上脇博之神戸学院大教授が明らかにしたものです。
開示されたのは、近畿財務局が2015~2016年度に作成した文書で、財務局の売却担当者から法務担当者への質問を記した「照会票」や回答をまとめた「相談記録」などです。
文書には、学園側が国有地から新たにごみが見つかったとして「土地を安価に買い受けることで問題解決を図りたい」と提案し「無理であれば事業を中止して損害賠償請求をせざるを得ない」などと主張したと記載されています。
売却担当者は法務担当者に「法的にどういう責任を負担することになるのか」と照会し、法務担当者が「速やかに方針を決定し、方策を講じることが望ましい」と回答した経緯も記されていました。
大半の文書で、事案概要などとして学園の主張や交渉経緯が説明され、学園側が「(国有地を)買い受ける場合、損害賠償請求などは一切行わない」と約束したことも記載していました。
これが交渉記録なのか交渉記録ではないのか分かりませんが、あれだけの問題になったわけなのですから、国会の場などで自ら明らかにすべきだったのではないかと思いますね。
そうしないと、今後も『廃棄した』と言えばいいということになりかねないのではないでしょうか?
森友学園との交渉の関連文書である「照会票」や「相談記録」などが開示されたことについて、どう思われましたか?
国土交通省が公用メールを1年で自動廃棄!
2018年02月06日(火)
省庁で利用が急増している公用電子メールについて、国土交通省は2月から、送受信後1年が経過したものをサーバーから自動的に廃棄することを決めたようです。
保存が必要な公文書に該当するメールは職場で保存するよう指示しましたが、廃棄可能なメールとして、国会議員からの説明要求の連絡文書などを挙げています。
専門家は「政策の検証に必要なメールが消去される」と懸念しているようです。
毎日新聞が入手したメール管理指針案や国土交通省の説明によると、国土交通省は昨年、自動廃棄の方針を職員に伝えたうえで、今年1月末までに保存期間が1年以上の公文書に該当するメールをデータファイル化し、共有フォルダーなどに保存・登録するよう指示しました。
登録手続きをしないメールは、サーバーから自動廃棄された時点で見られなくなります。
公文書に該当する場合でも、官僚の裁量で重要性が低いと分類されれば保存期間は1年未満となるようです。
指針案は保存期間1年未満のメールについて、職員間で共有する必要性が高いものを除いて廃棄するよう求めました。
廃棄可能な例として、国会議員からのレクチャー要求の内容を記載した連絡文書、会議や国会議員への説明の日程調整のためのメールなどを挙げています。
指針案には、廃棄可能なメールが「(情報公開の)対象になり得ることに留意する必要がある」と記されているようですが、国土交通省関係者は「職員にまずいメールは捨てろというふうに受け止められかねない」と話しているようです。
森友学園問題や南スーダンPKO日報問題では、政府が「保存期間1年未満」との理由で文書を廃棄したと説明していますが、1年未満の文書の定義があいまいだと批判が出ていました。
国土交通省は、森友学園への国有地売却の事務手続きを担当していました。
国交省はメールを自動廃棄する理由について、政府の公文書管理のガイドラインが改正され適正な管理が求められたことや、サーバーの容量確保の必要があるためなどと説明しています。
廃棄可能なメールは、紙であっても保存期間1年未満のものだとしています。
NPO法人「情報公開クリアリングハウス」の三木由希子理事長は、『メールが自動廃棄されれば、本来なら公文書として保存すべきものまで消えるのは確実だ。メールを選別して保存するには手間もかかるし、どのメールを保存するかの判断は個々の官僚の能力や意識、職場の文化によっても異なる。導入すべきは、重要なメールを確実に保存させるシステムと言える。国交省は森友学園問題に関するような都合の悪いメールを大量に廃棄してしまおうとしていると疑わざるを得ない。』と話しています。
森友問題で、現国税庁長官である佐川氏の発言が、国民の方々に不信感を抱かせたと思っています。
そのような中で、国土交通省のこのような方針は、『都合の悪いメールを大量に廃棄してしまおうとしている』と思われても仕方ないと思いますし、ますます国民の不信感を助長させるのではないでしょうか?
公務員も高い給料をもらって働いているわけですから、責任感を持って仕事をして、問題があれば隠すのではなく、きちんと責任を取って欲しいですね。
国土交通省が公用メールを1年で自動廃棄することについて、どう思われましたか?
月面探査レースに参加しているHAKUTOが3月末までの打ち上げを断念!
2018年01月17日(水)
ショックなニュースがありました。
アメリカのグーグルが支援するXプライズ財団が主催する月面探査レースに参加しているHAKUTO(ハクト)の袴田武史代表が、先日、東京都内で記者会見し、当初レースの期限とされた3月末までの打ち上げを断念すると正式に発表しました。
今後は財団側にレースの期限延期を打診するなどして、3月以降での月面到達を目指すそうです。
「Xプライズ財団に期限の延期を要望している。すでにコミュニケーションは取り始めた」。会見で袴田代表は硬い面持ちでこう話しました。
HAKUTOは、月面探査スタートアップのispace(東京・港)が中心となって結成された月面探査レースのプロジェクトチームで、KDDIやスズキなどが支援しています。
インドの探査チーム「チームインダス」が開発する月面着陸機に相乗りし、インドのロケットPSLVで打ち上げて月を目指す計画でしたが、チームインダス側とロケットを打ち上げるインド宇宙研究機構(ISRO)との交渉が難航し、3月末までの打ち上げが不可能になったそうです。
「資金難と開発の遅れが原因だと推測している」(HAKUTO関係者)ようです。
月面でのレースにはHAKUTOを含め、世界各国の5チームが月を目指していましたが、現時点で各チームとも打ち上げ日程が明確になっていません。
期限が3月末に迫っており、月面での探査機の走行などの期間が必要なだけに、各チームとも瀬戸際のスケジュールです。
財団としても、期限を延期できなければ勝者が決まらない可能性もあります。
HAKUTOは、「延期の可能性はある」(袴田代表)と見て、交渉を続けるようですが、先行きは不透明なままです。
スタートアップによる宇宙への挑戦は、外的な要因で困難になることが多いようです。
2017年11月にも、宇宙ゴミ(デブリ)回収スタートアップのアストロスケール(シンガポール、岡田光信最高経営責任者=CEO)が打ち上げたデブリ観測衛星も、ロシアのロケット打ち上げの失敗の影響で失われました。
「もらい事故」の様相も否めませんが、衛星や探査機の開発は膨大な資金がかかるため「運が悪かった」では片付けられないでしょう。
HAKUTOは今後もチームインダスが打ち上げるロケットに相乗りする方向で進めていくそうです。
HAKUTOの中心を担うispaceは、2020年までに月面着陸ができる探査機の打ち上げを計画しています。
HAKUTOの取り組みとispaceの計画は直接関係しませんが、ispace単独での探査を前に、月面探査の技術的な実証を済ませておきたいという狙いもあったようです。
袴田代表は「チャレンジをあきらめたわけではない。ハクトは7年間やってきていろんな困難があったが一歩ずつ前進することで乗り越えてきた。大きな山だが、必ず解決したい」と話しました。
年明けに、テレビでHAKUTOのことをやっていて、日本にもスゴいことをやっている会社があるんだなぁとか、優勝賞金が2,000万ドル(約22億円)なんてグーグルってやっぱりスゴいなぁとか、元ヤンキーの開発者もいるんだぁなどと思っていただけに、非常にショックです。
他の国にも頑張って欲しいですが、HAKUTOを応援しているので、期限が延期になって欲しい気はしますね。
月面探査レースに参加しているHAKUTOが3月末までの打ち上げを断念したことについて、どう思われましたか?
立憲民主党代表の枝野氏が佐川国税庁長官に「確定申告前にけじめを!」
2018年01月15日(月)
『森友学園問題は(国有地売却額の)値引きが不正・不当であったことの結論は出ていますので、しっかりと「けじめ」をつけてほしい。』と、立憲民主党代表枝野幸男氏が、先日、発言したようです。
『まず国会でおかしな説明をしていた人(佐川宣寿〈のぶひさ〉・前財務省理財局長)がいま国税庁の長官をしている。これから確定申告だが、全国の税務署の職員は気の毒だ。トップがいい加減な説明で、捨てちゃいけない書類を捨てておいて、(納税者側から)「こんな小さなお金の書類がないといって何を言っているんだ」と確定申告の窓口で様々な声が上がってくるのではないか。その前にしっかりとけじめをつけていかないといけない。』と、NHKの番組で発言しています。
特に、枝野氏を支持しているわけではありませんが、おっしゃるとおりかと思います。
税理士向けの新聞に、日税連会長と国税庁長官の対談の記事が載っていましたが、きちんと表に出てきて話をして欲しいものですね。
立憲民主党代表の枝野氏が佐川国税庁長官に「確定申告前にけじめを!」という旨の発言をしたことについて、どう思われましたか?
森友学園の撤去ごみは100分の1!
2018年01月12日(金)
学校法人「森友学園」が大阪府豊中市の国有地を小学校建設用地として格安で取得した問題で、国土交通省大阪航空局は、先日、建設用地から実際に撤去したごみが、算定の100分の1に当たる194トンだったと明らかにしました。
国は、撤去すべきごみの量を1万9,500トンと算定し、土地売却額を約8億円値引きしており、値引きした根拠がより揺らぐことになりました。
森友、加計学園の疑惑を追及する民進党調査チームの会合で、大阪航空局の担当者は、「まだ学園内に積まれたごみもあるが、最終処分場で処理したごみは非常に少ない。」と言っているそうです。
早く、佐川宣寿国税庁長官に、記者会見して説明して欲しいものですね。
あとは、8億円を、当時の国土交通省大阪航空局の方々に弁償してもらいたいですね。
森友学園の撤去ごみは100分の1だったことについて、どう思われましたか?
金融庁職員が天下り斡旋!
2018年01月05日(金)
金融庁の発表によると、金融庁職員が天下り斡旋をしていたようです。
2017年1月、内閣官房内閣人事局が再就職等規制に関する全省庁調査を実施した結果、同局から再就職等監視委員会に対して規制違反の疑いのある27事案の報告が行われた。
この報告を受けて再就職等監視委員会が調査を実施した結果、金融庁職員の再就職等規制に違反する行為が認められた。
本件に係る事案の概要及び当庁の対応は、下記のとおり。
記
1.事案の概要
室長級職員Aは、
①平成28年、法人Bに再就職していた元職員Cの求めに応じ、同人を介して、法人Bに対し、職員Dをその離職後に法人Bの地位に就かせることを目的として、職員Dの退職時期に関する情報を提供した。
②平成28年、元職員Eの求めに応じ、同人を介して、法人Fに対し、職員Gをその離職後に法人Fの地位に就かせることを目的として、職員Gの略歴書の提供及び再就職意思の伝達をして各情報を提供した。
こうした行為は、国家公務員法第106条の2第1項に違反する行為であったと認められた。
2.関係者の処分
職員Aを国家公務員法第82条第1項に基づく懲戒処分として、3月間俸給の月額の10分の1を減額する。なお、職員Aは、処分と同時に総務企画局付へ異動させた。
また、職員Aの上司である課長級職員(当時)については、部下職員に対する管理監督責任があったとして、内規に基づく処分である「訓告」を行った。
3.再発防止策
本件の背景には、職員及び金融庁OBの再就職等規制に関する適切な認識が欠けていたことがあるため、本件のような違反行為が再び行われることのないよう、全職員に対して、改めて再就職等規制の周知・徹底を図る。特に、OBから再就職に係る情報提供等の依頼を受けた場合にはそれに応じてはならない旨を徹底する。また、OBに対しても、改めて再就職等規制の周知・徹底を図る。
4.金融庁による調査
今後、当庁においては、上記2事案以外にも他に違反行為がないか全容を解明するため、外部の法曹資格者を含めるなど適切な人選の調査体制を整備し、徹底した調査を行う。
(注)当庁は、再就職等監視委員会から、金融庁職員に係る上記2事案を調査する過程で当該2事案以外にも再就職等規制違反行為を行った疑いがあるとして国家公務員法第106条の18第1項に基づく調査(任命権者調査)を行うよう求められている。
一般企業でこのような問題が生じた場合、株主等に対する謝罪の言葉などがあると思いますが、金融庁の場合、ないんですね。
この辺りが、悪いことをしているという意識に欠けているという感じがしてなりません。
また、元職員に対する何らかの処分はできないのでしょうか?
当然、優秀な方が民間授業などに行くことを否定するつもりはまったくないですが、天下り問題は、本当にどうにかして欲しいですね。
あとは、金融機関や監査法人などを検査している金融庁がこういうコンプライアンスを無視した行為をしていると、こういう組織が検査する組織に値するのかと思いますね。
金融庁職員が天下り斡旋をしていたことについて、どう思われましたか?