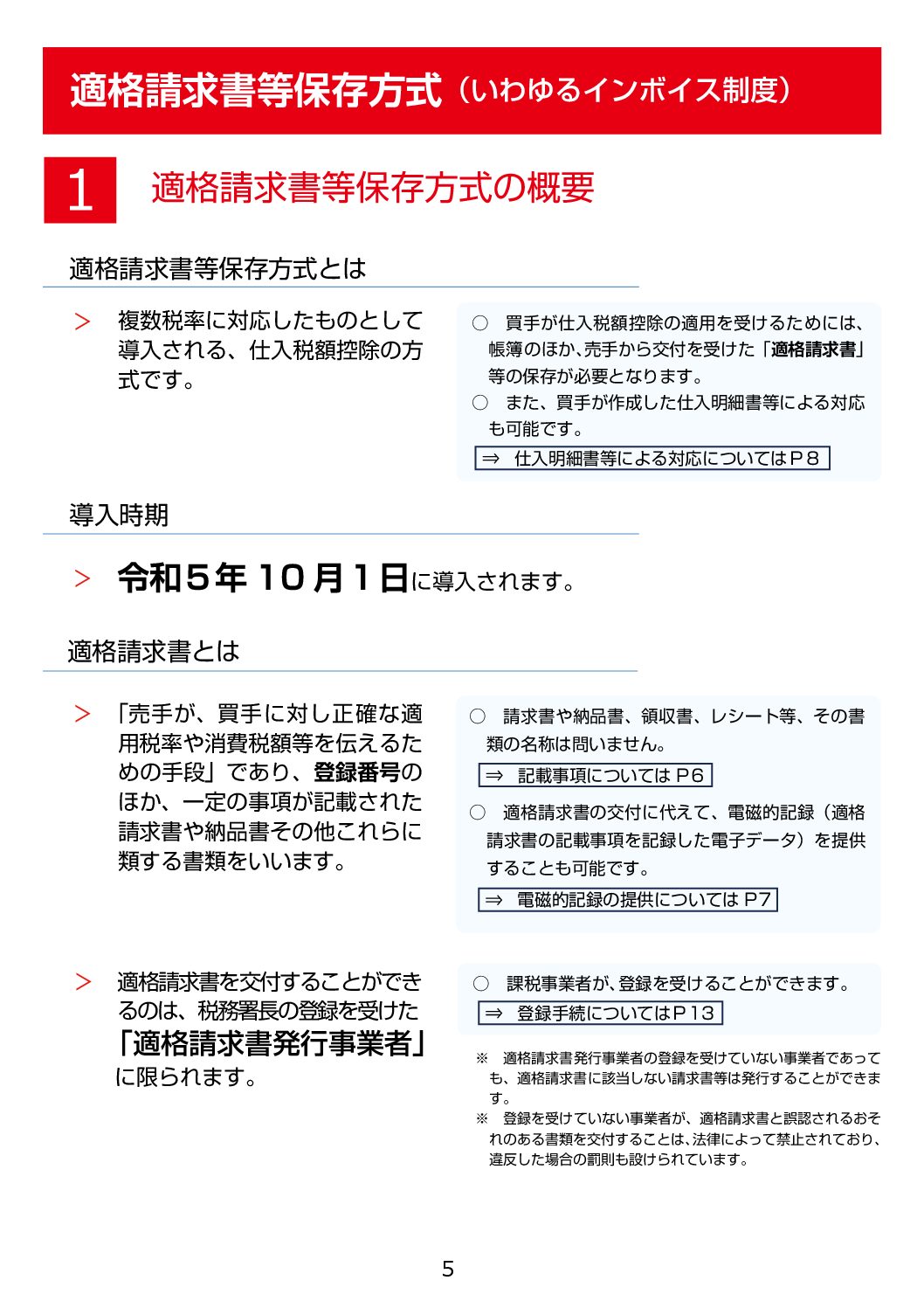事務所通信
2020年11月号『相続税と贈与税の一体化?』
毎年12月中旬に『税制改正大綱』が公表されますが、2020年は12月10日に公表されると言われています。
最近、税制調査会で『相続税と贈与税の一体化』について議論がされ、税制改正されるのではないかと言われています。
そこで今回は、『相続税と贈与税の一体化?』について、書きたいと思います。
1.相続税とは?
相続または遺贈により財産を取得した個人に対して、その財産の取得の時における時価を課税価格として課される税です。
2.贈与税とは?
個人から贈与により財産を取得した個人に対して、その財産の取得の時における時価を課税価格として課される税で、相続税の補完税としての性格を持っています。
(1)暦年課税
1年間に贈与により取得した財産の合計額から基礎控除(110万円)を控除した残額につき累進税率を適用し税額を計算します。
(2)相続時精算課税
贈与時の税負担を軽減し、相続時に相続税で精算するものです。
3.アメリカの贈与税・遺産税
『遺産税方式』が採られています。
贈与税と遺産税は統合されており、一生涯の累積贈与額と相続財産額に対して一体的に課税されます。
一生涯の生前贈与と相続で税負担は一定であり、資産移転の時期に『中立的』です。
4.ドイツ・フランスの贈与税・相続税
『遺産取得課税方式』が採られています。
贈与税と相続税は統合されており、一定期間(ドイツ10年、フランス15年)の累積贈与額と相続財産額に対して一体的に課税されます。
一生涯の生前贈与と相続で税負担は一定であり、資産移転の時期に『中立的』です。
5.日本の贈与税・相続税
暦年課税の場合、贈与税と相続税は別体系であり、相続前3年間の贈与のみ相続財産額に加算して相続税が課税されます。
生前贈与と相続では税負担が大きく異なり、資産移転の時期に『中立的でない』です。
相続時精算課税の場合、贈与税と相続税は別体系ですが、選択後の累積贈与額と相続財産額に対して一体的に課税されます。
選択後は生前贈与と相続で税負担は一定であり、資産移転の時期に『中立的』です。
6.論点
日本では、贈与税率が相続税率よりも高くなっているため、相続財産が少ない方は、相続税率に比べ相対的に贈与税率が高くなり、贈与をすると高い贈与税率が適用されることが多い一方、相続財産が多い方は、贈与を行うことで大きく相続税率を下げることが可能であり、『格差の固定化』につながっており、資産移転の時期によらず『中立的』であるべきかが議論されています。
7.最後に
改正されるかどうか分かりませんが、改正されると相続税対策というものが大きく変わることになるでしょうね。
なお、教育資金の一括贈与や結婚・子育て資金の一括贈与の廃止意見も出ています。
2020年11月30日 國村 年